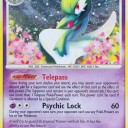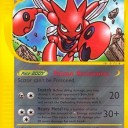【翻訳】50分+3ターン制の致命的な欠陥について
2014年2月2日コメント (2)
今回はThe Top Cutから。
約3ヶ月前、スイスラウンドで行われる海外大会が、1マッチ3ゲーム制、50分+追加3ターン制に移行したことと、その反応についての記事(http://ukinins.diarynote.jp/201311051833135718/)を訳しました。
3ゲーム制の50分+追加3ターン制とは、端的に説明すれば、
・50分で3ゲーム行い、2ゲーム取ったほうがそのマッチに勝利。
・途中で時間切れになったゲームはノーカウント。そこまでの成績で決める(=2ゲーム目で時間切れになったら1ゲーム目の勝者がマッチの勝者。3ゲーム目で時間切れになったら引き分け)
というものです(詳しくは上のリンク先をご覧ください)。
上の記事は制度移行直後のものでしたが、主な反応は、2本先取になったことで運要素が減るのはうれしいけれど、いろいろ大変になるなあ……というものでした。
あれから3ヶ月。実際にこの制度をしばらく経験した上での、この制度に関する記事が登場しました。
著者はJason Klaczynski。去年の世界大会優勝者にして合計3度の世界大会優勝者という、説明不要の最強プレイヤーです。
記事の内容は、この制度に対する激烈な批判。
この制度の何が駄目だったのか、そして、プレイヤーはどう感じているのか。
システム自体は日本と違えど、日本のプレイヤーにとっても、まったく無関係の内容ではないと思います。
いつもどおり、訳語の至らなさや誤訳の責任は、すべて僕うきにんに属します。
読みやすさを考慮して、改行を変更した部分があります。
(今回も例によって無許可翻訳なので、何かあればすぐに削除します)
◆ ◆ ◆ ◆ ◆
Five Fatal Flaws of 50+3
by Jason Klaczynski
Wednesday, January 29, 2014
ttp://thetopcut.net/2014/01/29/five-fatal-flaws-of-503/
たいていのカードゲームと同様、ポケカは運の要素に満ちている。ときに幸運の女神はあなたの側に来て、完璧な手札を引き込むだろう。またあるときには幸運の女神は機嫌を損ね、あなたは初手で、ゼニガメ1枚とエネ6枚を引いてしまう。ひどい初手を引くとことは、まともにプレイできないということを意味する。それゆえポケカコミュニティが、今シーズン、大規模大会ではスイスラウンドに3ゲーム制を採用するというアナウンスを好意的に受け入れたのも、驚くにはあたらない。しかしながら、ひとつ問題があった。3戦まとめてプレイできるだけの時間は、与えてもらえなかったのだ!
わずか50分と3ターン、そしてシャッフルと対戦準備には2分しか許されないという状況にあっては、3ゲーム制だと、1ゲームあたり平均すればたった15分(と1ターン)しか与えられないということになる! これがどれだけ短いのかを示すためには、何年ものあいだ広く受け入れられていた1試合の時間制限は30分であり、そしてそれでもなお、多くの試合では時間を使い果たしていたというのを思い出してもらいたい。50分+3ターン制の下では、ゲームは多くの場合で、もっと早い段階で時間切れを迎えてしまうだろう。決着のついていないチェスの対局やモノポリーのゲームが打ち切られたり、あるいは野球の試合が突然6回で中止されたりしたら、がっかりしてしまうし面白くもない。ポケカもそれと同じだ。時間制限の短さは、ポケカから面白さを抜き取ってしまう。
50分+3ターン制がマジで酷い要素を5つ見てみよう。
1.ほぼ5試合のうち1試合が、引き分けに終わっている
新規導入されたこの時間制限が、直近のRegionalsでその不適格ぶりを証明したところで、当然ながらポケカコミュニティにとっては驚くにあたらなかった。そこでは5試合に1試合が引き分けになってしまっていたが、理由は単純に、3ゲーム目を終わらせるだけの時間がないからだ。5試合に1試合の引き分けというのがそこまで多いと感じられないならば、注意してもらいたいのだが、これは3ゲーム目までもつれ込んだマッチだけでなく、すべてのマッチを含んだ数だ、ということだ(3ゲーム目までもつれ込んだマッチだけに限れば、引き分けの割合はもっと上がり、おそらく50%ぐらいになる)。加えて、50分以内に収まったマッチでも、必死になって時間を残すために、多くのプレイヤーは高速プレイを余儀なくされたし、まだ勝てる可能性の残るゲームを投了したりもした。なかには、引き分けになりそうだったのに片方の勝ちとして記録された対戦さえもあるが、それはお互いのプレイヤーが心に決めた上で、勝ち点1を避けるためにある種の合意を形成し、片方がもう片方に投了した、というものだ。
引き分けはつまらない。引き分けは結末を欠く物語のようなものだ。50分制のマッチにとっては、引き分けは残念な終わり方だ。しかも、引き分けでは両プレイヤーにはわずか勝ち点1しか与えられない(勝利3、敗北0)。両者に1点というのは、負けよりはわずかにマシというだけに過ぎず、だいたいの場合は両者のトップ8入りの可能性を狭めている。たとえば最近のフロリダのRegional Championshipでは、手堅く8勝1敗5分の成績を残したプレイヤーがトップ8入りを逃した。何てこった! その理由は引き分けにした5試合で上手くプレイできなかったからなのだろうか? まさか! もし十分な時間があれば、その5試合すべてに勝つことだってできたかもしれないのに!
2.無意味な途中終了のゲームをやる破目になる
こういう場面を思い描こう。3ゲーム制の対戦で、あなたと対戦相手は1ゲームずつ取っており、いま3ゲーム目を始めたところだ。相手のゲノセクトEXが速攻でサイドを何枚か取ってきて、まず相手が序盤のリードを奪った。だが、あなたはタイミングを見計らったNを打って巻き返しを図り、相手のゲノセクトEXを倒した。そしてあなたは大きな巻き返しを見せ、ゲームに勝とうとしていた、まさにそのとき、時間切れが告げられる。エクストラ3ターンが経っても、最後のサイドを引ききるにはあと1ターン足りなかった。そして対戦は引き分けが宣告される。
こんなあっけない幕切れが、50分+3ターン制ではあまりにありふれている。事実上、2-0か2-1で終わらなかったあらゆる対戦は、あなたと対戦相手が、何もカウントされない途中終了のゲームをやったということになる。悲しい話じゃないか! プレイヤーがポケカをやっているのは、それが楽しいからだ。国内や世界を旅して大会に出るのは、そこですばらしい対戦をしたいからだ。50分+3ターン制は、この体験をプレイヤーから奪ってしまう。この制度は、本来的にポケカが持っているすばらしい決着を、プレイヤーから奪い取ってしまうのだ。
3.遅延プレイを助長してしまう
ポケカではこれまでずっと、大会での遅延プレイが問題であり続けてきた。自分のターンにやることが多くあり、そして山札へのアクセス手段がそれだけあると、残念ながら、時間を浪費する方法はたくさん生まれてしまう。50分+3ターン制は、プレイを遅くしたくなる場面を絶えず生み出すがゆえに、この問題を悪化させてしまう。
こんな筋書きを想像してほしい。あなたはカメックス/ケルディオ/ブラックキュレムを使っていて、いまは3ゲーム目だ。あなたは1ターン目にベンチにゼニガメを置き、相手は1ターン目に、バトル場のビリジオンEXにエネルギーを貼ってきた。2ターン目、あなたはアメでカメックスを立て、バトル場にいたブラックキュレムEXにばくりゅうでエネをつけ、ブラックバリスタでビリジオンEXを倒した。相手の場にはエネルギーがなくなり、相手の勝つ見込みはほぼなくなった。
だが、ひとつだけ問題がある。ここまでのゲームカウントを鑑みれば、このマッチを引き分けにするには、対戦相手にとってみれば、このゲームを終わらせなければいいのだ。残り時間が10分ということで、相手は戦法を切り替え、バトル場にはEXの代わりに非EXポケモンを送り出してきた。これで毎ターン、あなたはサイド2枚でなく1枚ずつしか引けなくなった。相手は、ハイパーボールやレベルボールや、そういったカードを使って山札をサーチし、デッキをシャッフルすることもできる。あらゆる手段で、時間を消費するために(そしてそれらは何ら不法な手段ではなく、ルール通りの戦術なのだ)。そして10分後、もしあなたがサイド6枚を引き切ることができなければ、このゲームは全くの無駄に終わり、マッチは引き分けで終了する。このような失望的な決着が、50分+3ターン制では信じられないほど多く起こるのだ。
これと同様のシチュエーションが、1ゲーム目を長くかかって勝ったときにも起こりうる(そして実際よく起こっている)。もし1ゲーム目で20分以上消費していれば(それもよくあることだが)、勝った側は、もはや2ゲーム目で早くプレイする意味はどこにもない。このマッチを勝ちにするには2ゲーム目を取る必要は全くなく、むしろ負けなければいいだけなのだ。たとえ1ゲーム目に負けた側のプレイヤーが、50分+3ターン経過後に5枚のサイドを取っていても、6枚取りきられていなければ、そのマッチは1ゲーム目を取った側の勝利で終わる。1ゲーム目の勝者が、2ゲーム目で何枚サイドを取ったかとは関係なく、だ。
ジャッジは当然50分+3ターン制で遅延問題が起こってきたことを認識していて、今ではプレイヤーを急かさなければいけない立場にいっそう置かれている。ジャッジのなかには、以前ならそこまで厳しくも一般的でもなかったプレイ速度ガイドラインを厳しく強いてくる人もいて、プレイヤーにストレスを与えている。とはいえ、ガイドラインがどれだけ厳しく敷かれようとも、そしてどれだけ早くプレイしても、対戦相手は、15分かそれ以内の時間でゲームが終わらないようにやるのは可能なのだ(たいていの場合3ゲーム目は、これ以下の時間しか残っていない状態で始まるというのに!)。この時間制限は、端的に言って短すぎるのだ。
4.デッキの創造性や多様性を奪ってしまう
プレイ時間がこれだけ短いと、時間のかかる戦術のデッキは不利な立場になる。他デッキよりも勝つために時間のかかるデッキにとっては、1ゲーム目での敗北は、2ゲーム目での時間不足がありうる以上、多くの場合でマッチ自体の負けを意味する。このひとつの例がサザンドラデッキであり、何ターンにもわたって、ヤミラミのジャンクハントや回復を使って、ゆっくりと勝ちに行くからだ。もし対戦時間がもっと長くあれば、現行のスタンダードの広いカードプールから、創造性や多様性をもっと受け取ることができるはずなのだが。
5.倫理上の/スポーツマンシップ上のジレンマを引き起こす
こういう場面を想像してほしい。あなたは現在Regional Championshipで6勝2敗2分(勝ち点20)の成績にあり、いま11ラウンド目だ。噂によれば、トップ8に進むには最低でも勝ち点28が必要らしい。あと3ラウンドしか残っていないため、トップ8入りのためには、残る3ラウンドをすべて勝つ必要がある。そして対戦相手も勝ち点20で、同じ状況にあった。50分後、あなたは3ゲーム目をやっていて対戦は終了しておらず、つまりこのマッチは引き分けで終わりそうだった。だが、あなたも対戦相手も気づいているのだが、ここで引き分けに終われば、どちらもトップ8の可能性は消えるだろう。だがどちらかがここで投了すれば、勝者にはまだトップ8の目が残る。さて、片方が投了してもう片方にトップ8の目を残すのは、フェアプレイの精神に則っているのだろうか? それとも、投了することで本来は勝てなかった側を勝たせ、本来勝っていたはずの側をトップ8の可能性から弾き出してしまうのは、フェアプレイの精神に反することだろうか? そして、もし片方が投了するとして、投了する側はどうやって決めるのだろうか? サイド差? それも同じだったら? あるいは、今はサイド差で負けていても、明らかにこのままゲームに勝てそうだったとしたら?
プレイヤーは、引き分けが自分たちや相手を駄目にするとわかっている。だが、それでも何らかの合意に達するのは不可能だし、ときには勝者を決める上で、コインを投げたりさえもする!(実際これはルール違反だが、それでもジャッジがこれを防ぎ切るのは難しい) お分かりの通り、制限時間の不足は、大量の問題を生み出すだけでなく、スポーツマンシップ的にグレーゾーンな、奇怪な状況をも作り出す。そしてその問題は、対戦の外にいるプレイヤーにさえも及ぶのだ。
まとめると、3ゲーム制が失敗である理由は、
1.ほぼ5試合に1試合が引き分けに終わっている。両方のプレイヤーにとって不満な結果となるだけでなく、取れたはずの勝ち点3でなく1点しか与えられない。その結果、多くの場合でトップ8入りの可能性を狭めてしまう。
2.第3ゲーム目の多くが(ときには2ゲーム目も)制限時間内に終わらず、そうなると対戦成立としてカウントされない。そのため、プレイヤーは途中終了の無意味なゲームを行うことになる。
3.遅延行為を助長するような状況を絶えず作り出し、しかもジャッジがそれを防ぐのは難しい。
4.速度の遅いデッキが競技レベルで戦える可能性を狭め、大会でのデッキの多様性を低くしてしまう。
5.スポーツマンシップとフェアプレイ精神が衝突してしまうような、奇怪な状況を生み出してしまう。
◆ ◆ ◆ ◆ ◆
以上になります。お読みいただきありがとうございました。
このあとも記事は続くのですが、これ以降はJasonの提示する新システム案なので、今回は割愛しました。
ちなみにJasonの新システム案は、簡潔にまとめれば、1ゲーム30分制か3ゲーム75分制にしよう、というものです。
考え方は人それぞれなのでしょうけれど、お読みになったとおり、概してこの現行制度の評判は良くないのだと思います。
日本とはさまざまな部分で違いますが、考え方の面では、共通するところが多くあるのではないでしょうか。訳の上では割愛しましたが、この記事の最後は、「問題については、見えるところで議論をしよう。それは会社側にも届く」という形で締めくくられています。
日本の場合は、公式サイトにお問い合わせ窓口があります。DiaryNote的にはルールの細かい部分を突かれまくって可哀想なwお問い合わせ窓口ですが、大会制度やイベント進行のことなど、カード外の部分でも、気になることがあればどんどん要望を送ってみてはいかがでしょうか。
約3ヶ月前、スイスラウンドで行われる海外大会が、1マッチ3ゲーム制、50分+追加3ターン制に移行したことと、その反応についての記事(http://ukinins.diarynote.jp/201311051833135718/)を訳しました。
3ゲーム制の50分+追加3ターン制とは、端的に説明すれば、
・50分で3ゲーム行い、2ゲーム取ったほうがそのマッチに勝利。
・途中で時間切れになったゲームはノーカウント。そこまでの成績で決める(=2ゲーム目で時間切れになったら1ゲーム目の勝者がマッチの勝者。3ゲーム目で時間切れになったら引き分け)
というものです(詳しくは上のリンク先をご覧ください)。
上の記事は制度移行直後のものでしたが、主な反応は、2本先取になったことで運要素が減るのはうれしいけれど、いろいろ大変になるなあ……というものでした。
あれから3ヶ月。実際にこの制度をしばらく経験した上での、この制度に関する記事が登場しました。
著者はJason Klaczynski。去年の世界大会優勝者にして合計3度の世界大会優勝者という、説明不要の最強プレイヤーです。
記事の内容は、この制度に対する激烈な批判。
この制度の何が駄目だったのか、そして、プレイヤーはどう感じているのか。
システム自体は日本と違えど、日本のプレイヤーにとっても、まったく無関係の内容ではないと思います。
いつもどおり、訳語の至らなさや誤訳の責任は、すべて僕うきにんに属します。
読みやすさを考慮して、改行を変更した部分があります。
(今回も例によって無許可翻訳なので、何かあればすぐに削除します)
◆ ◆ ◆ ◆ ◆
Five Fatal Flaws of 50+3
by Jason Klaczynski
Wednesday, January 29, 2014
ttp://thetopcut.net/2014/01/29/five-fatal-flaws-of-503/
たいていのカードゲームと同様、ポケカは運の要素に満ちている。ときに幸運の女神はあなたの側に来て、完璧な手札を引き込むだろう。またあるときには幸運の女神は機嫌を損ね、あなたは初手で、ゼニガメ1枚とエネ6枚を引いてしまう。ひどい初手を引くとことは、まともにプレイできないということを意味する。それゆえポケカコミュニティが、今シーズン、大規模大会ではスイスラウンドに3ゲーム制を採用するというアナウンスを好意的に受け入れたのも、驚くにはあたらない。しかしながら、ひとつ問題があった。3戦まとめてプレイできるだけの時間は、与えてもらえなかったのだ!
わずか50分と3ターン、そしてシャッフルと対戦準備には2分しか許されないという状況にあっては、3ゲーム制だと、1ゲームあたり平均すればたった15分(と1ターン)しか与えられないということになる! これがどれだけ短いのかを示すためには、何年ものあいだ広く受け入れられていた1試合の時間制限は30分であり、そしてそれでもなお、多くの試合では時間を使い果たしていたというのを思い出してもらいたい。50分+3ターン制の下では、ゲームは多くの場合で、もっと早い段階で時間切れを迎えてしまうだろう。決着のついていないチェスの対局やモノポリーのゲームが打ち切られたり、あるいは野球の試合が突然6回で中止されたりしたら、がっかりしてしまうし面白くもない。ポケカもそれと同じだ。時間制限の短さは、ポケカから面白さを抜き取ってしまう。
50分+3ターン制がマジで酷い要素を5つ見てみよう。
1.ほぼ5試合のうち1試合が、引き分けに終わっている
新規導入されたこの時間制限が、直近のRegionalsでその不適格ぶりを証明したところで、当然ながらポケカコミュニティにとっては驚くにあたらなかった。そこでは5試合に1試合が引き分けになってしまっていたが、理由は単純に、3ゲーム目を終わらせるだけの時間がないからだ。5試合に1試合の引き分けというのがそこまで多いと感じられないならば、注意してもらいたいのだが、これは3ゲーム目までもつれ込んだマッチだけでなく、すべてのマッチを含んだ数だ、ということだ(3ゲーム目までもつれ込んだマッチだけに限れば、引き分けの割合はもっと上がり、おそらく50%ぐらいになる)。加えて、50分以内に収まったマッチでも、必死になって時間を残すために、多くのプレイヤーは高速プレイを余儀なくされたし、まだ勝てる可能性の残るゲームを投了したりもした。なかには、引き分けになりそうだったのに片方の勝ちとして記録された対戦さえもあるが、それはお互いのプレイヤーが心に決めた上で、勝ち点1を避けるためにある種の合意を形成し、片方がもう片方に投了した、というものだ。
引き分けはつまらない。引き分けは結末を欠く物語のようなものだ。50分制のマッチにとっては、引き分けは残念な終わり方だ。しかも、引き分けでは両プレイヤーにはわずか勝ち点1しか与えられない(勝利3、敗北0)。両者に1点というのは、負けよりはわずかにマシというだけに過ぎず、だいたいの場合は両者のトップ8入りの可能性を狭めている。たとえば最近のフロリダのRegional Championshipでは、手堅く8勝1敗5分の成績を残したプレイヤーがトップ8入りを逃した。何てこった! その理由は引き分けにした5試合で上手くプレイできなかったからなのだろうか? まさか! もし十分な時間があれば、その5試合すべてに勝つことだってできたかもしれないのに!
2.無意味な途中終了のゲームをやる破目になる
こういう場面を思い描こう。3ゲーム制の対戦で、あなたと対戦相手は1ゲームずつ取っており、いま3ゲーム目を始めたところだ。相手のゲノセクトEXが速攻でサイドを何枚か取ってきて、まず相手が序盤のリードを奪った。だが、あなたはタイミングを見計らったNを打って巻き返しを図り、相手のゲノセクトEXを倒した。そしてあなたは大きな巻き返しを見せ、ゲームに勝とうとしていた、まさにそのとき、時間切れが告げられる。エクストラ3ターンが経っても、最後のサイドを引ききるにはあと1ターン足りなかった。そして対戦は引き分けが宣告される。
こんなあっけない幕切れが、50分+3ターン制ではあまりにありふれている。事実上、2-0か2-1で終わらなかったあらゆる対戦は、あなたと対戦相手が、何もカウントされない途中終了のゲームをやったということになる。悲しい話じゃないか! プレイヤーがポケカをやっているのは、それが楽しいからだ。国内や世界を旅して大会に出るのは、そこですばらしい対戦をしたいからだ。50分+3ターン制は、この体験をプレイヤーから奪ってしまう。この制度は、本来的にポケカが持っているすばらしい決着を、プレイヤーから奪い取ってしまうのだ。
3.遅延プレイを助長してしまう
ポケカではこれまでずっと、大会での遅延プレイが問題であり続けてきた。自分のターンにやることが多くあり、そして山札へのアクセス手段がそれだけあると、残念ながら、時間を浪費する方法はたくさん生まれてしまう。50分+3ターン制は、プレイを遅くしたくなる場面を絶えず生み出すがゆえに、この問題を悪化させてしまう。
こんな筋書きを想像してほしい。あなたはカメックス/ケルディオ/ブラックキュレムを使っていて、いまは3ゲーム目だ。あなたは1ターン目にベンチにゼニガメを置き、相手は1ターン目に、バトル場のビリジオンEXにエネルギーを貼ってきた。2ターン目、あなたはアメでカメックスを立て、バトル場にいたブラックキュレムEXにばくりゅうでエネをつけ、ブラックバリスタでビリジオンEXを倒した。相手の場にはエネルギーがなくなり、相手の勝つ見込みはほぼなくなった。
だが、ひとつだけ問題がある。ここまでのゲームカウントを鑑みれば、このマッチを引き分けにするには、対戦相手にとってみれば、このゲームを終わらせなければいいのだ。残り時間が10分ということで、相手は戦法を切り替え、バトル場にはEXの代わりに非EXポケモンを送り出してきた。これで毎ターン、あなたはサイド2枚でなく1枚ずつしか引けなくなった。相手は、ハイパーボールやレベルボールや、そういったカードを使って山札をサーチし、デッキをシャッフルすることもできる。あらゆる手段で、時間を消費するために(そしてそれらは何ら不法な手段ではなく、ルール通りの戦術なのだ)。そして10分後、もしあなたがサイド6枚を引き切ることができなければ、このゲームは全くの無駄に終わり、マッチは引き分けで終了する。このような失望的な決着が、50分+3ターン制では信じられないほど多く起こるのだ。
これと同様のシチュエーションが、1ゲーム目を長くかかって勝ったときにも起こりうる(そして実際よく起こっている)。もし1ゲーム目で20分以上消費していれば(それもよくあることだが)、勝った側は、もはや2ゲーム目で早くプレイする意味はどこにもない。このマッチを勝ちにするには2ゲーム目を取る必要は全くなく、むしろ負けなければいいだけなのだ。たとえ1ゲーム目に負けた側のプレイヤーが、50分+3ターン経過後に5枚のサイドを取っていても、6枚取りきられていなければ、そのマッチは1ゲーム目を取った側の勝利で終わる。1ゲーム目の勝者が、2ゲーム目で何枚サイドを取ったかとは関係なく、だ。
ジャッジは当然50分+3ターン制で遅延問題が起こってきたことを認識していて、今ではプレイヤーを急かさなければいけない立場にいっそう置かれている。ジャッジのなかには、以前ならそこまで厳しくも一般的でもなかったプレイ速度ガイドラインを厳しく強いてくる人もいて、プレイヤーにストレスを与えている。とはいえ、ガイドラインがどれだけ厳しく敷かれようとも、そしてどれだけ早くプレイしても、対戦相手は、15分かそれ以内の時間でゲームが終わらないようにやるのは可能なのだ(たいていの場合3ゲーム目は、これ以下の時間しか残っていない状態で始まるというのに!)。この時間制限は、端的に言って短すぎるのだ。
4.デッキの創造性や多様性を奪ってしまう
プレイ時間がこれだけ短いと、時間のかかる戦術のデッキは不利な立場になる。他デッキよりも勝つために時間のかかるデッキにとっては、1ゲーム目での敗北は、2ゲーム目での時間不足がありうる以上、多くの場合でマッチ自体の負けを意味する。このひとつの例がサザンドラデッキであり、何ターンにもわたって、ヤミラミのジャンクハントや回復を使って、ゆっくりと勝ちに行くからだ。もし対戦時間がもっと長くあれば、現行のスタンダードの広いカードプールから、創造性や多様性をもっと受け取ることができるはずなのだが。
5.倫理上の/スポーツマンシップ上のジレンマを引き起こす
こういう場面を想像してほしい。あなたは現在Regional Championshipで6勝2敗2分(勝ち点20)の成績にあり、いま11ラウンド目だ。噂によれば、トップ8に進むには最低でも勝ち点28が必要らしい。あと3ラウンドしか残っていないため、トップ8入りのためには、残る3ラウンドをすべて勝つ必要がある。そして対戦相手も勝ち点20で、同じ状況にあった。50分後、あなたは3ゲーム目をやっていて対戦は終了しておらず、つまりこのマッチは引き分けで終わりそうだった。だが、あなたも対戦相手も気づいているのだが、ここで引き分けに終われば、どちらもトップ8の可能性は消えるだろう。だがどちらかがここで投了すれば、勝者にはまだトップ8の目が残る。さて、片方が投了してもう片方にトップ8の目を残すのは、フェアプレイの精神に則っているのだろうか? それとも、投了することで本来は勝てなかった側を勝たせ、本来勝っていたはずの側をトップ8の可能性から弾き出してしまうのは、フェアプレイの精神に反することだろうか? そして、もし片方が投了するとして、投了する側はどうやって決めるのだろうか? サイド差? それも同じだったら? あるいは、今はサイド差で負けていても、明らかにこのままゲームに勝てそうだったとしたら?
プレイヤーは、引き分けが自分たちや相手を駄目にするとわかっている。だが、それでも何らかの合意に達するのは不可能だし、ときには勝者を決める上で、コインを投げたりさえもする!(実際これはルール違反だが、それでもジャッジがこれを防ぎ切るのは難しい) お分かりの通り、制限時間の不足は、大量の問題を生み出すだけでなく、スポーツマンシップ的にグレーゾーンな、奇怪な状況をも作り出す。そしてその問題は、対戦の外にいるプレイヤーにさえも及ぶのだ。
まとめると、3ゲーム制が失敗である理由は、
1.ほぼ5試合に1試合が引き分けに終わっている。両方のプレイヤーにとって不満な結果となるだけでなく、取れたはずの勝ち点3でなく1点しか与えられない。その結果、多くの場合でトップ8入りの可能性を狭めてしまう。
2.第3ゲーム目の多くが(ときには2ゲーム目も)制限時間内に終わらず、そうなると対戦成立としてカウントされない。そのため、プレイヤーは途中終了の無意味なゲームを行うことになる。
3.遅延行為を助長するような状況を絶えず作り出し、しかもジャッジがそれを防ぐのは難しい。
4.速度の遅いデッキが競技レベルで戦える可能性を狭め、大会でのデッキの多様性を低くしてしまう。
5.スポーツマンシップとフェアプレイ精神が衝突してしまうような、奇怪な状況を生み出してしまう。
◆ ◆ ◆ ◆ ◆
以上になります。お読みいただきありがとうございました。
このあとも記事は続くのですが、これ以降はJasonの提示する新システム案なので、今回は割愛しました。
ちなみにJasonの新システム案は、簡潔にまとめれば、1ゲーム30分制か3ゲーム75分制にしよう、というものです。
考え方は人それぞれなのでしょうけれど、お読みになったとおり、概してこの現行制度の評判は良くないのだと思います。
日本とはさまざまな部分で違いますが、考え方の面では、共通するところが多くあるのではないでしょうか。訳の上では割愛しましたが、この記事の最後は、「問題については、見えるところで議論をしよう。それは会社側にも届く」という形で締めくくられています。
日本の場合は、公式サイトにお問い合わせ窓口があります。DiaryNote的にはルールの細かい部分を突かれまくって可哀想なwお問い合わせ窓口ですが、大会制度やイベント進行のことなど、カード外の部分でも、気になることがあればどんどん要望を送ってみてはいかがでしょうか。
抜いてきました(過去形)。
かかりつけにしている歯医者さんから「将来的に虫歯になるから抜いた方がいいですよー」と言われていた下の親知らずでしたが、4月からは抜くタイミングが無くなりそうだし、ということで、とうとう抜いてきました。ここまで前回のコピペ。これで両方です。
今回は前回以上に奥に埋まっていたらしく、麻酔の届いていない根元のほうを触られるたびに痛みで死にそうになっていましたが、何とか生還しました。
抜歯後は食べられるなら何を食べても良いそうなのですが、顎が腫れるので口が開かず、結局は柔らかいものしか食べられないというオチがつきます。前回でそれを学びました。食べられるなら、というのがフラグだったようです。
今週末のうきにん杯は口の中に糸が入ったままなのであまりしゃべりません。誰かMCを……。
かかりつけにしている歯医者さんから「将来的に虫歯になるから抜いた方がいいですよー」と言われていた下の親知らずでしたが、4月からは抜くタイミングが無くなりそうだし、ということで、とうとう抜いてきました。ここまで前回のコピペ。これで両方です。
今回は前回以上に奥に埋まっていたらしく、麻酔の届いていない根元のほうを触られるたびに痛みで死にそうになっていましたが、何とか生還しました。
抜歯後は食べられるなら何を食べても良いそうなのですが、顎が腫れるので口が開かず、結局は柔らかいものしか食べられないというオチがつきます。前回でそれを学びました。食べられるなら、というのがフラグだったようです。
今週末のうきにん杯は口の中に糸が入ったままなのであまりしゃべりません。誰かMCを……。
【デッキリスト】第37回うきにん杯トップ3デッキ
2014年2月9日
(大会の簡易報告はhttp://sipcup.diarynote.jp/201402102047215125/にあります)
順位、プレイヤー名(敬称略)、デッキは上から画像の順番に対応しています。
1st Place:レオン(フェアリーバレット)
2nd Place:クーポソ(フェアリーバレット)
3rd Place:会長(フェアリーバレット)
入賞された方々、おめでとうございます。
順位、プレイヤー名(敬称略)、デッキは上から画像の順番に対応しています。
1st Place:レオン(フェアリーバレット)
2nd Place:クーポソ(フェアリーバレット)
3rd Place:会長(フェアリーバレット)
入賞された方々、おめでとうございます。
奇跡の40日間?
2014年2月11日 2月5日に、海外でXYコレクションと30スターターに該当するパックが発売になりました。
これにより、いまの日本のカードプールと海外のカードプールは、ほぼ完全に一致しています(厳密には海外レギュはBW3以降ですが)。
この状態は、日本でワイルドブレイズが発売になる3月15日まで続きます。
僕が記憶している限り(もしかしたら間違っているかもしれませんが)、世界大会レギュを除けば、日本のカードプールと海外のカードプールが一致したことは、これまで無かったのではないかと思います。
かつては3~4ヶ月以上は離れているのが常だった販売サイクルの差がここまで縮まったのは、正直驚きとしか言いようがありません(いつか同時になればいいね!)。
個人的にうれしいのは、日本と海外の環境がほぼ同じになったことで、デッキや戦術の比較がこれまで以上に有効になるのではないかということです。
デッキや情報を伏せる、公開するは個人の考えだとは思いますが、デッキやコラムを読んで楽しむ側としては、みんないろいろ書いてくれたほうが面白くなるのにな、とは思う次第です。
(実際、海外勢は日本の情報探しに相当難儀しているようです。それは日本でもポケカ初心者の人が流行りのデッキを探せないのと同じですね)
海外では、XY2のワイルドブレイズに相当するFlashfireが5月7日に発売予定だそうです。そこからは再びカードプールが一致するでしょう。また、世界大会レギュはそのXY2まででほぼ確定だろうと言われています。
日本と海外の環境差が限りなく小さくなった現在は、ある意味では、これまでには無かった新しい時期を迎えているのかもしれません。
これにより、いまの日本のカードプールと海外のカードプールは、ほぼ完全に一致しています(厳密には海外レギュはBW3以降ですが)。
この状態は、日本でワイルドブレイズが発売になる3月15日まで続きます。
僕が記憶している限り(もしかしたら間違っているかもしれませんが)、世界大会レギュを除けば、日本のカードプールと海外のカードプールが一致したことは、これまで無かったのではないかと思います。
かつては3~4ヶ月以上は離れているのが常だった販売サイクルの差がここまで縮まったのは、正直驚きとしか言いようがありません(いつか同時になればいいね!)。
個人的にうれしいのは、日本と海外の環境がほぼ同じになったことで、デッキや戦術の比較がこれまで以上に有効になるのではないかということです。
デッキや情報を伏せる、公開するは個人の考えだとは思いますが、デッキやコラムを読んで楽しむ側としては、みんないろいろ書いてくれたほうが面白くなるのにな、とは思う次第です。
(実際、海外勢は日本の情報探しに相当難儀しているようです。それは日本でもポケカ初心者の人が流行りのデッキを探せないのと同じですね)
海外では、XY2のワイルドブレイズに相当するFlashfireが5月7日に発売予定だそうです。そこからは再びカードプールが一致するでしょう。また、世界大会レギュはそのXY2まででほぼ確定だろうと言われています。
日本と海外の環境差が限りなく小さくなった現在は、ある意味では、これまでには無かった新しい時期を迎えているのかもしれません。
今回は久々に60cards.netから。
かなり長めですが、デッキ構築に関する記事を紹介します。著者のJoao Lopes(ジョアン・ロペスと読むのでしょう)は去年のポルトガル大会の優勝者です。
内容は、いかにデッキを組むか。そしてデッキのやりたいこととは何か。
2008年の世界大会で優勝したサーナイト/エルレイド(PLOX)のリストを例に取り、デッキ構築について解説しています。
長い記事ですが、その分量に見合った抜群の面白さです。カードと直接関係のない部分もありますが、そこも非常に面白く読めると思います。
DP時代のカードが多く登場するため、当時を知っている方は、懐かしく思いながらお読みいただければと思います。また、知らない方でも、興味があればぜひ調べていただければと思います。どれも一世を風靡したカードたちです。
ちなみにタイトルにパート2とある通り、この記事はパート1もあります。今回パート2を訳したのは、単純にこちらの方が面白いからです。
いつもどおり、訳語の至らなさや誤訳の責任は、すべて僕うきにんに属します。
読みやすさを考慮して、改行を変更した部分があります。
(今回も例によって無許可翻訳なので、何かあればすぐに削除します)
◆ ◆ ◆ ◆ ◆
What to play? A non time fixed analysis of decklist choosing -- Part 2
Sunday, December 22, 2013
by Joao Lopes
ttp://60cards.net/blog/posts/detail/120
■デッキ構築は、ときに芸術と見なされる。
自分も含め、デッキ構築が趣味であり、かつ時間潰しの道具になる人もいる。デッキ構築はパズルのようなものだ。そこでならあなたはクリエイティブになることができ、新しい戦術を編み出せる。あるいは頭のおかしい勝ち方を想像して、メタゲームを倒すべく絶えずチャレンジすることができる。それは、デザインとソリューションの両立のようなものだ。
誰もが時間をかけてデッキ構築について書くわけではない。だからこそ、デッキはプレイテストにかけられ、調整をされる。デッキリストを拾ってきて使う人もいれば、デッキを自分で作り、自分の想像物を誇りにする人もいる。それは人それぞれだ。
デッキを作ったのが誰であったかに関わらず、あなたの選んだ60枚の束は、大会でどれだけやれるかを最も決定付ける要因になる。この一連の記事を書いている理由は、デッキを決める際に、念頭に置くべきものごとをすっかり理解してほしいからだ。願わくは、読者には何か新しいことを知っていってほしいと思う。もし書かれていることがすでにわかりきったことならば、それはあなたが正しい道を進んでいるということだ。この記事は、デッキ構築そのものではなく、大会で使う構築を選択することについて書かれている。これは、さきほど上で触れたプレイヤーそれぞれの側にとって、魅力的に映るはずだ。
ほとんどの場合、勝敗を決定付けるのはマッチアップだ。あなたは練習でひとつの構築だけを他のデッキと対戦させるかもしれないが、一方で上手いプレイヤーは、そのマッチアップを交互に行い、そして多くの場合、優れた構築が勝ち残るようにしている。
もちろんこのことは、プレイミスの可能性や運の要素があるがゆえに、常に当てはまるとは限らない。それでも、ここで話しているのは、普通の店舗大会ではなく、より高いレベルの場に向けたデッキリスト選びだ。そのため、両者による完璧なプレイングを常に想定しなければならない。
今回は、成功したデッキリストに踏み込んでみたい。なぜそれが他のものと違うのか、そして、その選択に至った理由は何なのか。このパート2の例として選んだのはこれだ。
■成功例:Jason Klaczynski、2008年世界大会
3度の世界大会優勝者であるJasonは、極めて基本に忠実なプレイングで知られている。彼は自分のプレイングの能力を信頼しており、ゆえにデッキリストは、その自信を反映したものになっている。彼は絶好の参考例となるはずだ。それでは、デッキリスト選択の際の彼の考え方に目を向け、それが対戦中にどう機能したかを見てみよう。
まず始めに、当時の背景を覗いてみたい。
■2007-2008年のメタゲーム
時は2007年にさかのぼる。ダイヤモンド&パールが絶妙なタイミングで世に出て、アメリカ選手権と世界大会を震撼させた。そこでは恒例のカードパワーの上昇が行われた(あらゆる新シリーズの最初の弾と同様だ)が、後に続いたセットと比べてみれば、それも霞んで見える(これもあらゆる新シリーズ最初の弾と同様だ)。
〔※訳注:DP初弾が出たのは2007年のNationals直前の5月〕
新セット登場によって、exの入っていないデッキが環境を制圧しつつあった。その理由は、それらのカードが旧来のexに匹敵するカードパワーを持っていたからだ。
ホロンのポワルン(PCG7)やオニドリルδ(PCG8)といったカードは、いまだデルタ種デッキを機能させてはいた。最も強力だったのがフライゴンexδ(PCG9)で、それに内蔵されたエンジン(フライゴンδ(PCG7))と強いたねのおかげで、周囲のカードパワー上昇の中でも、いまだに勢力を保ってはいた。それは、exの時代における最後の戦士だった。
2008年、その年の最初のエキスパンションであるGreat Encounters〔※訳注:DP4前後に相当〕が世に出ると、そこには、ポケカ史上で最も安定したドローエンジンが入っていた。ネンドールだ。それによって、2進化デッキの速度が何倍にもなり、馬鹿げた場の組み立てもできるようになった。おまけに、山札切れで負けることもなくなった。
もちろん、このエキスパンションから得られた良いカードはそれだけではなかった。ダークライLv.Xはマニューラと組み合わせればファンデッキの要になったし、トゲキッスはデカブツデッキの中心だった(お供のブーバーンとホウオウはどちらもSecret Wondersに入っていた)。〔※訳注:デカブツデッキの原語はramp decks。他のTCGでも、エネに相当するカードを大量に使って巨大生物で攻撃するデッキを指します〕
この新しいドローエンジンが環境にもたらしたのは、完全に新しい何かというわけではなかった。けれども、ついにその最終形態が現れた。怪物デッキ、PLOXだ。
サーナイトとエルレイドは、2007年のSecret Wonders〔※訳注:DP3に相当〕で登場していた。その強さにも関わらず、リリース時には、2ターン目からの速攻デッキの新たな王様(ジュペッタex)や、1進化の重戦車(ブーバーン)がいた。さらにPLOXが活躍するのを押し留めていたのは、ぶっ壊れカードのアブソルや、ハピナス単速攻で使われていた封印の結晶だった。
ドローエンジンがなければ、PLOXは競争相手となるデッキたちについていくことはできなかった。またロック能力も、そこまで多くのポケパワーが使われていなかった当時はあまり強くなかった。
ここに至って、ついにPLOXはドローエンジンという武器を得た。そしてギンガ団の賭けのポテンシャルをフルに使うこともできるようになった。それが環境最強デッキになるのに、長くはかからなかった。
唯一のライバルはブーバーン(DP4)だったが、それとてさほど恐るるに足らなかった。ジュペッタ/ハピナスのような対策デッキが、PLOXを沈めるために作られた。ジュペッタ/サクラビスのようなデッキは、ブーバーンを倒せるようにできていた。
2008年のアメリカ選手権前の最後のエキスパンションは、Majestic Dawn〔※訳注:DP4の残り+@に相当〕だった。そしてそれは、その名の通り、この暗黒の時代にあって祈りを捧げるプレイヤーたちに、答えを与えてくれたのだった。〔※訳注:Majestic Dawnは直訳すれば「壮大な夜明け」〕
ペラップは、究極の「緊急脱出」用カードだ。エネなしで「ものまねむすめ」が撃てて、にげるコストもない。しかも、W虹経由のサイコロックを耐え、サイコカッターにはサイド1枚めくりを(W虹付きなら2枚を)強要できた。
リーフィアLv.Xはブーバーンにエネをコンスタントに加速する新しい方法であり、また他のイーブイ進化系を選んで使うことで、複数のアーキタイプに対抗できる利点があった。そしてリーフィアは、新たにやってきた相手への、強烈なカウンターにもなっていた。エンペルトだ。
エンペルト(EP08)は、堅牢なHPと、2つの優秀なワザを持っていた。
・デュアルスプラッシュは、相手のたねを一掃できたり、あとで相手を一撃で落とすための致命的なダメージを乗せておくことができる。
・みんなでなみのりは、当時ではエルレイドぐらいしか出しえないような狂ったダメージ量を叩き出すことができる。しかも時間経過で火力が減ることもない。このワザとデュアルスプラッシュとは最高のコンビネーションだ。またこのワザは、サーナイトのHPをちょうど10残す。けれどそれは、すぐにドータクンで倒すことが可能だった。
この巨大な銅鐸は、ポケパワーに強く依存したデッキ(さてどれのことだろう)に劇的に効いたし、ダメージばらまきはエンペルトの最良のパートナーだった。下のワザは、湖の結界がある状態で、スクランブルエネルギーから起動させてサーナイトを一撃で倒し返すというのがよく行われた。〔※訳注:これ上のワザのことでは……?〕
環境は、少しであれ活況を帯びてきていた。けれどその年、対策が大量に存在していたにもかかわらず、Gino LombardiがPLOXを駆ってアメリカ選手権を制した。このデッキは、それでもあまりに強かったのだ……。ではここから、Jasonが世界大会に向けて、どのように考えていたのかを見てみよう。
■環境最強デッキを組む
Pojoに投稿された彼のレポート〔※訳注:ttp://www.pojo.com/CardofTheDay/2008/8-22.shtml〕のおかげで、彼の戦略と、大会に向けて最終版のデッキリストを選ぶ上で何を考えていたのかを、じっくりと見ることができる。
前回の記事では、デッキリストを選ぶ際に踏んでおくべきステップの例を示した。年間を通じてのメタゲームとその変化は今追ってきたばかりだから、環境は理解できている。ならばステップ2の時間だ。選択肢を絞ろう。
この時点でのJasonは、2つのデッキの狭間にいた。そう、2という数字は、1つのデッキに納得できていない限りは、最終決定にたどり着くまで何度も繰り返し出てくる数字だ。もし選択肢が3つ残っているなら、そのうち1つは残り2つほどは良くないはずだから、早々に省かれてしまうだろう。
彼のレポートから直接引用してみたい。
Jasonの頭の中には目標があった。この目標は、デッキ構築の際のガイドラインのようなものだ。常識はいつも正しいのだろうか? そうとも限らない。
たいていのプレイヤーにとっての問題は、どこで立ち止まるべきかがわからないことだ。我々はみな、どこかの段階で自分の欲望に負け、ひとつの目標を打ち立てるのではなく、デッキ内に複数の目標を作ってしまう。
我々は誰もがこういった可能性を夢見る。完璧な手札を引けたら、完璧に場が整ったら、そして不確実性をすべて無視できたなら……しかしそれは、所詮は夢でしかない。「過ぎたるは及ばざるが如し」という古い教訓は、ポケカにもしっかりと当てはまる。デッキリスト内であれこれやろうとすればするほど、上手くいく可能性は下がっていく。シンプルな戦略が、一番上手くいくというのに。
もうひとつの誤解は、単純な目標を設定すると、デッキリストをオートパイロット的なものにしてしまうのではないか、というものだ。それは手札を運任せなものにしてしまい、自分の「究極のポケカスキル」を発揮して相手を凌駕する余地がなくなってしまうのではないか、というたぐいの誤解だ。
自分は折に触れてこの問題に取り組もうとしてきた。それなら今ここで扱うべきだろう……この誤解について、例を挙げて説明させてほしい。
ゲームデザインにおいて、挑戦的な場面の設定は、難易度を高めるということを意味しない。難解なマップやステージを作ることは容易だし、難易度の高いボスをデザインするのはさらに簡単だ。
ゲームデザインにおいて難しいのは、面白いものを作るというところにある。
何か困難なことを乗り越えたとき、頭を使って上手くやったと感じられたなら、そこに楽しさが生まれる。自分の自尊心が高まる体験が嫌な人はいるだろうか? こういった、能力を得られたという仮想体験は、みんながテレビゲームを好きな理由のひとつだ。もし自分が、もっと上手くなって勝ちたいのならば、何度も負けたらフラストレーションがたまってしまう。
これは誰かを批判しようとして言っているわけではない。単純に本当のことなのだ。
より厳密な例を出せば、こうなる。
テレビゲームのゲームデザインについて勉強してきて気がついたのは、パズルというものが直線的で単純な仕組みになっているということだ。直線的、という言葉で何が言えるのだろうか? それにはどれほどの利点があるのだろうか?
パズルをやる上で必要なのは、多くのステップを踏むことだ。そうすれば、さらに先へ進めるようになる。オブジェやスイッチをどこへ置くべきか、そしてどこでレーザーを反射させればいいかを、理解する必要もある。これらは他の要素と組み合わせられて、数多くのプラットフォームゲームやハック&スラッシュゲームで用いられている。理由は、それらが上手く機能するからだ……。
〔※訳注:ゲームの種類のうち前者は、スーパーマリオ等の、主人公が平面の台の上を移動するゲーム。後者は敵をひたすら叩き切っていくようなゲーム〕
そういったステップは単純だが、数は多くある。3つも博士号を持っている大学教授ならば、これらのステップ全部を高速でこなしたときに、自分が頭を使ったと感じるだろう。
我々も自分が頭を使ってできたと感じることがあるし、それは別に難しいことではない。8歳の子供でも、自分が頭を使ったと感じることはあるだろう。ここに何かのパターンはあるのだろうか?
たとえば、一匹の犬がパズルの参加者になったとして、そのパズルをIQ200の大学教授と同じスピードで解いたとする。この場面には出くわしたことがある。そのパズルは極めて直線的で、間違えようがないものだった。できる行動はつねに一通りしかなく、そのため常に正しいものになっていた。
それをパズルと呼びたくないのはなぜだろう? これは単純な、簡単な種類のものだが、それでもパズルだ。楽しく遊べる余地の多くあるパズルだ。世界で一番出来の悪い子供でも解くことができ、大学教授と同じくらい自分が頭を使えたと感じられるようなパズルだ。そしてその両者が、ともに楽しめるようなものなのだ。
自分のスキルが試されるようなものが欲しい? 頭を使うよう要求されるようなものが欲しい? ならばどうしてあなたはこんな記事を読んでいるのだろう。数学や論理学の問題集でも解けば良いはずなのに。だが、その通り、そんなものは楽しくないのだ……。
このことは、どういう形でポケカに当てはまるのだろうか?
相手を「倒す」方法としてあまりにたくさんのことをやろうとし、それぞれのシチュエーションに全く異なったやり方で対処しようとするデッキがある。
「あ、ドラゴンダイブを撃ったね? 罠に掛かったな。こっちの手札にはエテボースGとダブル無色があるから、その攻撃にはカウンターさせてもらうよ」
「そんなばかな、想定通りのマッチアップの想定通りの場面でこれを使われるだなんて。やるじゃないか! でもこちらにはハマナがあるから、ドクロッグGと超エネを持ってくるよ。エテボースかレントラーがサイドを取ってきたときの自動プレイだ。サイドいただくよ!」
どうだろうか? 直線的とは……。
それでもプレイヤーたちは、デッキ内で多くのことをやろうとしてしまう。特定の場面に対処できなくなるのを恐れるあまり、1枚挿しが20種類も入って、アタッカーの線があまりに細くなってしまったようなデッキを見たことはないだろうか。たとえば、
2 ゴウカザルFB
1 ゴウカザルFB Lv.X
2 レントラーGL
1 レントラーGL Lv.X
1 アグノム(DP5)
1 何か
1 何か
1 何か
…
…
…
1 プレミアボール
これの何が駄目なのだろうか? アタッカーの線の細さだ。なぜそうなってしまったのだろうか? スペースがないからだ。なぜスペースがなくなったのだろうか? 強烈なカウンターカードがこんなに必要だから? 恐らくこの時代最強のデッキであるにもかかわらずこんなにたくさん? でも、リカバリーが速くできないから。どうして? それはアタッカーの線が細いから……。
カウンターカードが頭を使うプレイのように見えてしまうがために、デッキ内のラインはどんどん複雑になっていく。そして、安定しなくなっていく。
アタッカーを引っ張るのにアグノムを必要とする2-1ラインは、頭を使いそうに見える。プレミアボールもアタッカーとの置き換えで、それをサーチできるようになっている。だがこれは、カードの致命的なサイド落ちの危険性を高め、パワースプレーされる可能性もあれば初手スタートの可能性もあるカードへの依存度を、いっそう高めるだけだ。実際、初手スタートするかスプレーされるかでアグノムを失ったら、どうにもならなくなってしまう。
これはただ大変になっているだけであり、賢くやれているわけではない。このリストは頭を使いそうなデザインに見えるが、単なる脆弱な構築に過ぎず、安定した立ち上がりをさせたい使用者にストレスを与えるだけだ。繰り返しになるが、こういった不出来な構築でも頭を使えたと感じるならば、それはただ多くの選択肢があったからに過ぎない。だが説明したとおり、実際、そんなのはただの幻想だ。
あらゆる場面でそれに応じた特定のプレイを必要とするというのは、対戦相手の行動に対して自動で反応するロボットになるということだ。事実、ギミックの詰め込み過ぎは、プレイを予想のできるものにする。相手がギミックを理解できてしまえば、サプライズ要素など消え去り、こちらが次にやろうとする行動を相手が知っているということになる(もっとも、安定しないデッキでちゃんと行動できればの話だが)。
おおざっぱにまとめればこういうことだ。相手に解答を探させるような、能動的なプレイヤーになろう。相手の行動に応じて解決策を探すような、受動的なプレイヤーになってはいけない。
ギミックと安定性を巡る永遠の葛藤については、次回の記事で触れようと思う。今は、誰もが知っている次の事実を指摘しておこう。
+ギミック=-安定性
同様に、
多くをやろうとすればするほど、できることは少なくなっていく。
■Jasonの優勝PLOXリスト
機能するデッキには目標がひとつしかないことは上で述べた。なぜJasonは2つ言っていたのだろうか?
目標は安定性だ。それは、常に自分の戦略を機能させてくれる。ミラーで強みを持たせるというのは、安定性に到達する上での心構えに過ぎない。強烈な対策ギミックを加えるというのは、それとは正反対のことだ。
あるマッチアップで強みを持たせるというのは、デッキに馴染むオプションを加えることで達成できる。それは、柔軟性のあるリストにすることを意味する。
強烈な対策カードは、ある特定の場面では有効だが、機械的なリアクションとなる。その一方で、柔軟性のあるカードならば、2つ以上の目的を持たせることができ、デッキのメイン戦略から外れることもない。それこそが本当の意味でのデッキに馴染むオプションといえる。それは、ただ自分が頭を使ったと感じるだけの幻想とは違うものだ。
では、デッキリストを見ていこう。
PLOX by Jason Klaczynski - 2008年世界大会優勝
4 ラルトス(DP3)
2 キルリア(DP3)
3 サーナイト(DP4)
1 サーナイトLv.X(DP4)
2 エルレイド(DP3)
2 ヤジロン(DP4)
2 ネンドール(DP4)
1 ヨマワル(DP1)
1 ヨノワール(DP1)
1 ペラップ(DP4)
1 ジラーチex(PCG8)
1 サンダース☆(promo)
彼のレポートと同じように、それぞれの部分を個別に見ていきたい。まずはポケモンからだ。
シンプルで、安定している。デッキの機能に忠実になろうというのがその考え方だ。相手より速く展開できれば、相手の対策カードも追いつけなくなる。
アタッカーのライン以外で目に付くのは、ヨノワールでの精神的なプレッシャー(相手デッキがアブソル(BW8)入りと知っている状況と比べてほしい)と、追加の「サイコロック」になるジラーチexだ。そして、サンダースが入っている……。
サンダースは柔軟性の最初の例だ。相手を一撃で倒すのに10点だけ足りなかったりすると、相手は追加の1ターンを得てしまう。サンダースは、サーチ可能なプラスパワーとなることで、そういった状況を避けることができる。そのような追加のダメージカウンターは、PLOXのダメージ計算では欠かせないものだ。
・W虹付きのサイコロックは、よく使われるたねポケを落とせないことがある(たとえばペラップ)。
・湖の結界が場にある状態で、PLOXはW虹付きだと相手のサーナイトに100ダメージ、エルレイドに120ダメージしか与えられない。
・サーナイトLv.Xはサイコロックを10残して耐える。
・ジラーチexのちょうねんりきはサーナイトに100ダメージしか飛ばない。
・エルレイドがエンペルトを落とすとき、サイド4枚ではなく3枚めくるだけで済むようになる。
・ホロンエネFFつきのハピナス(DP2)に対しても、サンダースなしだとエルレイドはサイドを4枚めくる破目になる。
・相手のジラーチexに対しても、サンダースなしだとエルレイドはサイド3枚の代わりに2枚めくりで済むようになる。〔※訳注:恐らく1枚の間違い?〕
これが柔軟性ということだ。それがお助けカードにしかならないようなマッチアップでも、少なくとも2つ以上の状況で働いてくれる。致命的な使い方のできるその他のマッチアップでなら、有効なギミックになりうる。
再びおおざっぱなまとめをしたい。死に札は作らないようにしよう。そしてほとんどの場合、対策カードは死に札なのだ。
4 ハマナのリサーチ
4 ニシキのネットワーク
2 ミズキの検索
2 ギンガ団の賭け
2 ダイゴのアドバイス
この記事の趣旨を鑑みれば、ここをあえて強調する必要はないだろう。安定した枚数が入っていて、ネンドールと、サーナイト(このデッキの核だ)を可能な限り速く立てることに注力されている。
4 ふしぎなアメ
2 暴風
2 ワープポイント
2 湖の結界
湖の結界については上で何度か触れたので、有用性は明らかだろう。
このカードの主な目的は、このデッキにとって重要なW虹やスクランブルを無効化してしまうクリスタルビーチを割ることだ。Jasonはスタジアムや封印の結晶を割るため暴風を2枚入れているだけでなく、様々な状況で便利なこのスタジアムも2枚入れている。同時にそれは、このデッキにとって脅威になるカードに対する、効果的なカウンターにもなっている。
繰り返しになるが、用途が多いということは、デッキの弱点を取り除くと同時に、死に札にならないということだ。より多くのオプション、さらなる安定性、そして、より高い柔軟性。
4 コールエネルギー
3 超エネルギー
1 サイクロンエネルギー
4 Wレインボーエネルギー
3 スクランブルエネルギー
このエネルギーの部分を最後に残したのは、特に興味深い箇所はないからだ。4枚のコールエネとW虹は高速展開の可能性を最大限に高めてくれるし、1枚おしゃれに積まれたサイクロンエネは、封印の結晶対策になると同時に、ダメージを稼がれてしまう相手の壁カードへの対策になっている。
このデッキを何度か(特にミラーを)回してみたあとでは、4枚目の超エネルギーがあっていいかもしれないと思った。だがそのために抜けそうなカードは、おそらくそのエネルギーよりも重要なカードだろう。
最後に、別のリストと見比べてみたい。
■比較例
PLOX by Gino Lombardi - 2008年世界大会3位, 2008年アメリカ選手権優勝
4 ラルトス(DP3-3,PCG6-1)
2 キルリア(DP3)
3 サーナイト(DP4)
1 サーナイトLv.X(DP4)
2 エルレイド(DP3)
2 ヤジロン(DP4)
2 ネンドール(DP4)
1 クレセリア(DP4)
1 クレセリアLv.X(DP4)
1 ベトベター(DP3)
1 ベトベトン(DP3)
1 パチリス(DP4)
1 ジラーチex(PCG8)
1 フィオネ(DP4)
3 ハマナのリサーチ
2 ニシキのネットワーク
2 ミズキの検索
2 ギンガ団の賭け
3 ダイゴのアドバイス
4 ふしぎなアメ
1 ワープポイント
1 湖の結界
1 夜のメンテナンス
1 ちからのかけら
2 フヨウのスタジアム
3 コールエネルギー
5 超エネルギー
4 Wレインボーエネルギー
3 スクランブルエネルギー
この年はGinoの黄金期だった。その年最大の大会で優勝し、そして世界大会でもトップ4になったのだから、偉業と言わず何と言おう。
このリストには、目立った欠点がいくつかある。
・初手スタートすると弱いカードが多い。
・貧弱なサポーターのライン
・封印の結晶への解答がない。
・コールエネルギーが3枚のみ。
ギミックが数多く詰め込まれているせいで、このデッキは、そう頻繁には完璧な立ち上がりができるわけじゃない。それに加えこのデッキには、ミラーマッチ以外では完全な死に札になる、対策カードが入っている。これだけ多くの1枚挿しがあると解答がサイド落ちする可能性があるし、クレセリアを手助けする手段がワープポイント1枚しかない。
サポーターラインを削り、ギミックを増やして、100%ポケパワーに依存したデッキにとっては、封印の結晶への対策がないのは致命的だ。クリスタルビーチを割るためにフヨウのスタジアムが2枚入っているが、ときたまいるキノガッサに好き放題やられるのを防げて、かつ非常に用途の多い湖の結界は、1枚しか入っていない。もうひとつ欠点を挙げればヨノワールが入っていないことだ。それだけで相手が息を吹き返せるだけの(文字通りの)余分なスペースを与えてしまう。そのスペースは、エンペルトが海辺でみんなでなみのりを(シャレじゃない)するのに欠かせないものだというのに。
それでもGinoは優秀なプレイヤーであり、このリストで相当に上の方まで進むことができた。そして、それは幸運のおかげだけではなかったのだ。
・ワープポイントが1枚だけとはいえ、フヨウのスタジアムはクレセリアを立てるのに大きな助けとなる。クレセリアは一度立ってしまえば、回復と同時に半永久的なプラスパワーになれる。エンペルトのデュアルスプラッシュに対しても強くなる。
・ベトベトンは強烈な対策カードだ。だが、よく機能した。W虹や起動済みのスクランブルエネのついた相手なら、何でも毒状態にできたのだ。このカードは特定の場面でのみ強いカードだが、それでも実際は大半のプレイヤーがPLOXを使っていたせいで、ミラーでの強烈な対策カードは、多大なアドバンテージになった。
・フィオネはW虹つきのサイコロックなら耐えることができ、その間にサーナイトやエルレイドを育てられる。パチリスでも同様のことが言えるが、思うにこのカードは、4枚目のコールエネの代わりになっていたのだ。
・ちからのかけらは、封印の結晶のようなどうぐを使ってくる多くの相手に対して、テレパス経由で探しに行くカードだ。だが、テレパスを止めてくる封印の結晶への対策がなければ、そこまで有効にはなりえない。またこのカードは、相手のサイコロックでサンダースが封じられた状況下で使うこともできる。
だが、過去に思いを巡らすことの意義とは何なのだろう? これらの話から、いったい何を得られるのだろうか。
異なったメタゲームや愛すべきゲームの歴史を学ぶことは楽しい。だがそれとは別に我々は、フォーマットに関係なく機能するものとは何かを学ぶことができる。
これらの記事の究極の目標は、プレイヤーが、どんなフォーマットにも、どんな状況にも適応できるよう手助けをすることだ。とあるプレイヤーがとあるデッキで結果を残せていたとしても、そのプレイヤーは、別のデッキでは結果を残せないかもしれないし、新弾が出ても自分のデッキをそれに適応させられないかもしれない。つまるところ、この記事がやりたいのは、プレイヤーの小さなミスを見つけ、スキルを完璧なものにするための手助けをすることだ。
少し先走りすぎたかもしれないが、ここで、学んできたことを使ってひとつ実践的なサンプルを見せたいと思う。
■トップメタデッキにおける柔軟性:現代編
自分の考えでは、完成形になって以来ずっと強力で、かつローテーションまで消えないであろうデッキのひとつは、カメックスだ。
このデッキは強いデッキだと誰もが知っているし、当たったときのために準備をする必要がある。そのため、大会でカメックスを使うのは悪くない賭けだと考えてもいい。プレイがあまり難しくなく、非常に強力だ。
目の前には、他のプレイヤーにとって脅威になるデッキがある。彼らがこのカメックスを脅威と感じる理由を、下記のガイドラインから裏付けてみよう。
安定させること。そしてその延長線上で、ミラーで強みを持たせること。また、ありがちな欠点に対して、柔軟な解決策を持たせること。
まずはポケモンから始めよう。
Standard Blastoise by Joao Lopes
4 ゼニガメ
3 カメックス
2 ケルディオEX
2 ブラックキュレムEX
1 ブラックキュレム
1 ジラーチEX
1 タマタマ
ポケモンキャッチャーが無くなったことで、ジラーチEXはカメックスにとって手堅い利点になった。ジラーチEXは、ハイパーボールや、ときにはレベルボールを、ビーチや、アメや、カメックスや、アララギや、スーエネ回収や、Nにも変えてくれる。このおかげで安定性が驚くほど増しているし、1ターン目のゼニガメ/ビーチや2ターン目のカメックス+アタッカーのような破壊的な展開を手助けしてくれる。
カードを少し引いたあとでならカメックスを見つけるのは容易だが、ゼニガメでスタートするのは簡単ではない。そのため、安定性を最大化するのにゼニガメ4は必須だ。余ったゼニガメは、あとでハイパーボールやスーエネ回収で捨てることができる。
カードを捨てることに関して言えば、このデッキのすべてのカードはあのおおざっぱなまとめ話に従っている。つまり、どんなマッチアップでも、無駄になるカードは入っていない。それを頭に入れておくと、上で触れたボール系や回収系は、捨てる余裕のないはずのカードを切ってしまう破目に陥る、ということになる。コストを軽減するためのタマタマは、1キルがほとんどない環境なので、安全に使うことができる。
アタッカーについては、それぞれを2枚ずつ入れれば十分に足りる。3枚目は必要にならないし、デッキがきちんと動けば1枚でもたいてい非常に良い仕事をしてくれる。考え方としては、ほとんどの対戦で非EXポケモン1枚とEXポケモンを2枚倒されるということになっている。アタッカーが4枚いれば、3枚目のEXがゲーム終盤で使えるようになるだろう。
さて、柔軟性のあるカードでミラーに強みを持たせよう。非EXのブラックキュレムだ。これはよく知られたギミックだが、そこまで使われてはいない。ドラゴンの殴り合いになればこのカードは1枚でサイド2枚と交換になり、相手のプランを崩壊させられる。この見え見えの使い道以外だと、バトル場に放置された相手のゼニガメやタマタマをこれで倒すというものがある。自分のデカブツをわざわざ危ないところに出さなくて済む、というわけだ。
ミラー以外だと、非EXポケモンがいれば重要なアタッカーを使わず生かしたままにしておける。一番良くある相手がヤミラミだ。このオプションは、考える以上に有効だ。また、このカードがあれば、ケルディオEXが倒されたあとでもガブリアスあたりの適当なドラゴンを狩ることができるし、レックエンブのような相性の悪いマッチアップも5分5分で戦うことができる。
4 アララギ博士
3 N
4 フウロ
2 アクロマ
自分はいつもサポーターの最低ラインは14枚にしているが、今回の場合は、ジラーチEXがボールをサポーターに変えてくれる。そのため、サポーターの枚数カウントはもっと多いものとして扱える。
ここでもうひとつ指摘したいのは、4枚目のNを入れていないことだ。Nは本当に強力なサポーターだが、このデッキは、Nを使い倒せるようなデッキではない。その代わり、アクロマ2枚が、中終盤では最強のサポーターになってくれる。ときにアクロマの入っていないデッキがあるのは、このカードが序盤では役立たずだからだ。だがこのデッキなら序盤はフウロとトロピカルビーチに依存するし、サポーターを切り替えるころには、アクロマはオーキド博士の新理論と同等かそれ以上の働きをしてくれる。それでもN3枚とアクロマ2枚にしているのは、このデッキが序盤の数ターンで展開する必要があること、そして、デッキのメインの目的に絞って構築する必要があるからだ。
フウロ4枚は疑いの余地ない選択だ。このデッキが一番必要とするカードであるし、このデッキの手札はいつも、完璧なものからはグッズ1枚ぶん足りない。そういうとき、フウロは最高の相方になってくれる。アララギに関して言えば……アララギはアララギだ。可能なら、10枚でも使いたいカードだ。
4 ハイパーボール
2 レベルボール
4 ふしぎなアメ
4 スーパーエネルギー回収
3 トロピカルビーチ
2 ツールスクラッパー
2 エネルギー転送
1 ポケモン回収サイクロン
ボール系が6枚というのは、Jasonのデッキでサーチ系のサポーターが6枚だったのと同様だ。ここでは、2ターン目のカメックスを保障してくれる。ハイパーボールを最大枚数入れておけば、1ターン目にゼニガメを引く方法は6枚もあるし、2ターン目にカメックスやアタッカーを引くカードも4枚確保できる。
ダストダスが常に脅威である以上は、ツールスクラッパー投入はマストだ(封印の結晶に対しての暴風と同じだ)。おまけとして、エンペルト(最近流行ってきている)のシルバーバングルを剥がすことができるし、他のデッキのかるいしを剥がして妨害することもできる。
2枚のエネルギー転送は、この氷のドラゴンのために雷エネルギーを引くのに必要であり、またケルディオのために水エネルギーを確保する手段でもある。困ったときにはフウロがエネにもなる。2枚しか入れていないのは、エネの総数を減らしてあっという間にエネ切れを起こすのを防ぐためだ。
ポケモン回収サイクロンは、自分の住んでいる地域でカメックスを使っているプレイヤーから拝借したアイディアだ。まんたんのくすりよりも強いカードだし、ジラーチEXを再利用したり、エネを捨てずに逃げることができたりと、多くの場面で使えるカードだ。構築が安定していればパソコン通信は必ずしも必要ではないし、このカードは、相手の前のターンの動きを無駄にできたり、それ以上のこともできる。
2 雷エネルギー
9 水エネルギー
エネルギー転送は、水と雷の両方を探せるという点以外にも、雷エネの実数を削って水エネの使える量を増やせるという点がある。
このデッキリストは、オプションを組み入れつつ安定性を目指すという原則に基づいて構築されたものだ。カメックスのような、動きが一直線なデッキでも、それは可能だ。
もちろん、環境や、そのプレイヤーのメタ読みの能力にも依存する。数枚変えただけで、特定のマッチアップ相性が改善することだってある。とはいえ、環境への適応については、日を改めて議論をするとしよう……。
■結論
複雑な戦術が展開できたときの美しい光景には、みなが魅了されがちだ。だが現実は、手の込んだことをやって失敗するよりも、シンプルなことを正しくやるのが一番なのだ。
当たり前の知恵は忘れられやすい。我々はみな、戦術を完遂して純粋な安定性で勝ちに行くよりも、あらゆるデッキに対して何らかの解答を用意しようとしてしまう。
ある状況で強いカードは、別の状況では邪魔なカードになる。柔軟性は、ギミックと安定性のあいだでバランスを保ってくれるものなのだ。
次の記事ではデッキ構築における別の要素について書いてみたい。大会だ。League Challengeから世界大会まで、その違いを見出すのは簡単だ。つまり、難易度が上がり、プレイヤーが増える。だが、とある構築が大会環境に合っていたとして、その翌年には、その大会環境に合う構築が全く変わってしまうとしたら?
次回は、環境に適応することについてだ。Pesadelo Prism (2012)とStraight Darkrai (2013)を取り上げてみたい。〔※訳注:前者は2012年の世界大会優勝のダークライM2。後者は恐らく2013年の世界大会優勝のダークライ。〕
◆ ◆ ◆ ◆ ◆
以上になります。お読みいただきありがとうございました。
文字数にして15000超えという非常に長い記事でした。それでも、最後までお読みいただいた方にとっては、必ずや得られるものがあっただろうと思います。
かく言う僕にとっても、実は2007~2008年ごろは某MtGにかまけていたので、なかなか新鮮な内容の多い記事でした。
ふたつのサーナイト/エルレイドの比較のあたりは白眉ですね。また、ゲームデザインを例に出して、なぜギミックは有効性が低いのかを語るくだりも、大変ためになるものだったと思います。
この著者は、次回はふたつのダークライデッキを取り上げてくれるようですね。次回にも期待大です。
かなり長めですが、デッキ構築に関する記事を紹介します。著者のJoao Lopes(ジョアン・ロペスと読むのでしょう)は去年のポルトガル大会の優勝者です。
内容は、いかにデッキを組むか。そしてデッキのやりたいこととは何か。
2008年の世界大会で優勝したサーナイト/エルレイド(PLOX)のリストを例に取り、デッキ構築について解説しています。
長い記事ですが、その分量に見合った抜群の面白さです。カードと直接関係のない部分もありますが、そこも非常に面白く読めると思います。
DP時代のカードが多く登場するため、当時を知っている方は、懐かしく思いながらお読みいただければと思います。また、知らない方でも、興味があればぜひ調べていただければと思います。どれも一世を風靡したカードたちです。
ちなみにタイトルにパート2とある通り、この記事はパート1もあります。今回パート2を訳したのは、単純にこちらの方が面白いからです。
いつもどおり、訳語の至らなさや誤訳の責任は、すべて僕うきにんに属します。
読みやすさを考慮して、改行を変更した部分があります。
(今回も例によって無許可翻訳なので、何かあればすぐに削除します)
◆ ◆ ◆ ◆ ◆
What to play? A non time fixed analysis of decklist choosing -- Part 2
Sunday, December 22, 2013
by Joao Lopes
ttp://60cards.net/blog/posts/detail/120
■デッキ構築は、ときに芸術と見なされる。
自分も含め、デッキ構築が趣味であり、かつ時間潰しの道具になる人もいる。デッキ構築はパズルのようなものだ。そこでならあなたはクリエイティブになることができ、新しい戦術を編み出せる。あるいは頭のおかしい勝ち方を想像して、メタゲームを倒すべく絶えずチャレンジすることができる。それは、デザインとソリューションの両立のようなものだ。
誰もが時間をかけてデッキ構築について書くわけではない。だからこそ、デッキはプレイテストにかけられ、調整をされる。デッキリストを拾ってきて使う人もいれば、デッキを自分で作り、自分の想像物を誇りにする人もいる。それは人それぞれだ。
デッキを作ったのが誰であったかに関わらず、あなたの選んだ60枚の束は、大会でどれだけやれるかを最も決定付ける要因になる。この一連の記事を書いている理由は、デッキを決める際に、念頭に置くべきものごとをすっかり理解してほしいからだ。願わくは、読者には何か新しいことを知っていってほしいと思う。もし書かれていることがすでにわかりきったことならば、それはあなたが正しい道を進んでいるということだ。この記事は、デッキ構築そのものではなく、大会で使う構築を選択することについて書かれている。これは、さきほど上で触れたプレイヤーそれぞれの側にとって、魅力的に映るはずだ。
ほとんどの場合、勝敗を決定付けるのはマッチアップだ。あなたは練習でひとつの構築だけを他のデッキと対戦させるかもしれないが、一方で上手いプレイヤーは、そのマッチアップを交互に行い、そして多くの場合、優れた構築が勝ち残るようにしている。
もちろんこのことは、プレイミスの可能性や運の要素があるがゆえに、常に当てはまるとは限らない。それでも、ここで話しているのは、普通の店舗大会ではなく、より高いレベルの場に向けたデッキリスト選びだ。そのため、両者による完璧なプレイングを常に想定しなければならない。
今回は、成功したデッキリストに踏み込んでみたい。なぜそれが他のものと違うのか、そして、その選択に至った理由は何なのか。このパート2の例として選んだのはこれだ。
■成功例:Jason Klaczynski、2008年世界大会
3度の世界大会優勝者であるJasonは、極めて基本に忠実なプレイングで知られている。彼は自分のプレイングの能力を信頼しており、ゆえにデッキリストは、その自信を反映したものになっている。彼は絶好の参考例となるはずだ。それでは、デッキリスト選択の際の彼の考え方に目を向け、それが対戦中にどう機能したかを見てみよう。
まず始めに、当時の背景を覗いてみたい。
■2007-2008年のメタゲーム
時は2007年にさかのぼる。ダイヤモンド&パールが絶妙なタイミングで世に出て、アメリカ選手権と世界大会を震撼させた。そこでは恒例のカードパワーの上昇が行われた(あらゆる新シリーズの最初の弾と同様だ)が、後に続いたセットと比べてみれば、それも霞んで見える(これもあらゆる新シリーズ最初の弾と同様だ)。
〔※訳注:DP初弾が出たのは2007年のNationals直前の5月〕
新セット登場によって、exの入っていないデッキが環境を制圧しつつあった。その理由は、それらのカードが旧来のexに匹敵するカードパワーを持っていたからだ。
ホロンのポワルン(PCG7)やオニドリルδ(PCG8)といったカードは、いまだデルタ種デッキを機能させてはいた。最も強力だったのがフライゴンexδ(PCG9)で、それに内蔵されたエンジン(フライゴンδ(PCG7))と強いたねのおかげで、周囲のカードパワー上昇の中でも、いまだに勢力を保ってはいた。それは、exの時代における最後の戦士だった。
2008年、その年の最初のエキスパンションであるGreat Encounters〔※訳注:DP4前後に相当〕が世に出ると、そこには、ポケカ史上で最も安定したドローエンジンが入っていた。ネンドールだ。それによって、2進化デッキの速度が何倍にもなり、馬鹿げた場の組み立てもできるようになった。おまけに、山札切れで負けることもなくなった。
もちろん、このエキスパンションから得られた良いカードはそれだけではなかった。ダークライLv.Xはマニューラと組み合わせればファンデッキの要になったし、トゲキッスはデカブツデッキの中心だった(お供のブーバーンとホウオウはどちらもSecret Wondersに入っていた)。〔※訳注:デカブツデッキの原語はramp decks。他のTCGでも、エネに相当するカードを大量に使って巨大生物で攻撃するデッキを指します〕
この新しいドローエンジンが環境にもたらしたのは、完全に新しい何かというわけではなかった。けれども、ついにその最終形態が現れた。怪物デッキ、PLOXだ。
サーナイトとエルレイドは、2007年のSecret Wonders〔※訳注:DP3に相当〕で登場していた。その強さにも関わらず、リリース時には、2ターン目からの速攻デッキの新たな王様(ジュペッタex)や、1進化の重戦車(ブーバーン)がいた。さらにPLOXが活躍するのを押し留めていたのは、ぶっ壊れカードのアブソルや、ハピナス単速攻で使われていた封印の結晶だった。
ドローエンジンがなければ、PLOXは競争相手となるデッキたちについていくことはできなかった。またロック能力も、そこまで多くのポケパワーが使われていなかった当時はあまり強くなかった。
ここに至って、ついにPLOXはドローエンジンという武器を得た。そしてギンガ団の賭けのポテンシャルをフルに使うこともできるようになった。それが環境最強デッキになるのに、長くはかからなかった。
唯一のライバルはブーバーン(DP4)だったが、それとてさほど恐るるに足らなかった。ジュペッタ/ハピナスのような対策デッキが、PLOXを沈めるために作られた。ジュペッタ/サクラビスのようなデッキは、ブーバーンを倒せるようにできていた。
2008年のアメリカ選手権前の最後のエキスパンションは、Majestic Dawn〔※訳注:DP4の残り+@に相当〕だった。そしてそれは、その名の通り、この暗黒の時代にあって祈りを捧げるプレイヤーたちに、答えを与えてくれたのだった。〔※訳注:Majestic Dawnは直訳すれば「壮大な夜明け」〕
ペラップは、究極の「緊急脱出」用カードだ。エネなしで「ものまねむすめ」が撃てて、にげるコストもない。しかも、W虹経由のサイコロックを耐え、サイコカッターにはサイド1枚めくりを(W虹付きなら2枚を)強要できた。
リーフィアLv.Xはブーバーンにエネをコンスタントに加速する新しい方法であり、また他のイーブイ進化系を選んで使うことで、複数のアーキタイプに対抗できる利点があった。そしてリーフィアは、新たにやってきた相手への、強烈なカウンターにもなっていた。エンペルトだ。
エンペルト(EP08)は、堅牢なHPと、2つの優秀なワザを持っていた。
・デュアルスプラッシュは、相手のたねを一掃できたり、あとで相手を一撃で落とすための致命的なダメージを乗せておくことができる。
・みんなでなみのりは、当時ではエルレイドぐらいしか出しえないような狂ったダメージ量を叩き出すことができる。しかも時間経過で火力が減ることもない。このワザとデュアルスプラッシュとは最高のコンビネーションだ。またこのワザは、サーナイトのHPをちょうど10残す。けれどそれは、すぐにドータクンで倒すことが可能だった。
この巨大な銅鐸は、ポケパワーに強く依存したデッキ(さてどれのことだろう)に劇的に効いたし、ダメージばらまきはエンペルトの最良のパートナーだった。下のワザは、湖の結界がある状態で、スクランブルエネルギーから起動させてサーナイトを一撃で倒し返すというのがよく行われた。〔※訳注:これ上のワザのことでは……?〕
環境は、少しであれ活況を帯びてきていた。けれどその年、対策が大量に存在していたにもかかわらず、Gino LombardiがPLOXを駆ってアメリカ選手権を制した。このデッキは、それでもあまりに強かったのだ……。ではここから、Jasonが世界大会に向けて、どのように考えていたのかを見てみよう。
■環境最強デッキを組む
Pojoに投稿された彼のレポート〔※訳注:ttp://www.pojo.com/CardofTheDay/2008/8-22.shtml〕のおかげで、彼の戦略と、大会に向けて最終版のデッキリストを選ぶ上で何を考えていたのかを、じっくりと見ることができる。
前回の記事では、デッキリストを選ぶ際に踏んでおくべきステップの例を示した。年間を通じてのメタゲームとその変化は今追ってきたばかりだから、環境は理解できている。ならばステップ2の時間だ。選択肢を絞ろう。
この時点でのJasonは、2つのデッキの狭間にいた。そう、2という数字は、1つのデッキに納得できていない限りは、最終決定にたどり着くまで何度も繰り返し出てくる数字だ。もし選択肢が3つ残っているなら、そのうち1つは残り2つほどは良くないはずだから、早々に省かれてしまうだろう。
彼のレポートから直接引用してみたい。
一方の手にあったのは、サーナイト/エルレイドでした……。見てきたとおり、メリットとデメリットを並べ、それらを照らし合わせるのは、最後の段階の選択を吟味する上で、また、決定版リストへ「根拠」を与えるという意味でも、一番良い方法だ。この「根拠」は自信の元になるし、ときには時間ぎりぎりの調整で悪い方へ進むのを防いでくれる。
1.これは私が今シーズンずっと使ってきたデッキでした。ポケカにおいては、大会に出る際に、慣れないデッキで出ることほど不愉快なことはありません。
2.サーナイト/エルレイドには、不利なマッチアップはありませんでした。確かに、エンペルト/ドータクンにはこのデッキに対する強みがあります。でも、それはどれほどでしょうか?
3.エンペルト/ドータクンを使っていたプレイヤーの多くは、そこまで上手いプレイヤーではありませんでした。トッププレイヤーたちは、サーナイト/エルレイドの方を気に入っているようでした。
4.エンペルトはダグトリオ(PCG8)で対策される可能性もありました。
仮にエンペルト/ドータクンの肩を持つならば……、
1.このデッキは、現状もっとも使われているデッキを倒すことができました。サーナイト/エルレイドです。一番使われているデッキへの対抗策を持たずに、世界大会を勝つことはできるでしょうか?
2.世界大会の時間制限が40分に延長されました。エンペルトは、ときどき30分では勝ちきれないことがありました。
最終的に、私は腹を決めました。サーナイト/エルレイドを使うことにしたのです。そしてまた、私は、振り返ったときに、大会において限りなく完璧なリストだったと言えるものを使うことにしました。私のデッキリストは、ふたつの考え方を巡って作られています。
1.安定しているか
2.ミラーでの決め手はあるか
Jasonの頭の中には目標があった。この目標は、デッキ構築の際のガイドラインのようなものだ。常識はいつも正しいのだろうか? そうとも限らない。
たいていのプレイヤーにとっての問題は、どこで立ち止まるべきかがわからないことだ。我々はみな、どこかの段階で自分の欲望に負け、ひとつの目標を打ち立てるのではなく、デッキ内に複数の目標を作ってしまう。
我々は誰もがこういった可能性を夢見る。完璧な手札を引けたら、完璧に場が整ったら、そして不確実性をすべて無視できたなら……しかしそれは、所詮は夢でしかない。「過ぎたるは及ばざるが如し」という古い教訓は、ポケカにもしっかりと当てはまる。デッキリスト内であれこれやろうとすればするほど、上手くいく可能性は下がっていく。シンプルな戦略が、一番上手くいくというのに。
もうひとつの誤解は、単純な目標を設定すると、デッキリストをオートパイロット的なものにしてしまうのではないか、というものだ。それは手札を運任せなものにしてしまい、自分の「究極のポケカスキル」を発揮して相手を凌駕する余地がなくなってしまうのではないか、というたぐいの誤解だ。
自分は折に触れてこの問題に取り組もうとしてきた。それなら今ここで扱うべきだろう……この誤解について、例を挙げて説明させてほしい。
ゲームデザインにおいて、挑戦的な場面の設定は、難易度を高めるということを意味しない。難解なマップやステージを作ることは容易だし、難易度の高いボスをデザインするのはさらに簡単だ。
ゲームデザインにおいて難しいのは、面白いものを作るというところにある。
何か困難なことを乗り越えたとき、頭を使って上手くやったと感じられたなら、そこに楽しさが生まれる。自分の自尊心が高まる体験が嫌な人はいるだろうか? こういった、能力を得られたという仮想体験は、みんながテレビゲームを好きな理由のひとつだ。もし自分が、もっと上手くなって勝ちたいのならば、何度も負けたらフラストレーションがたまってしまう。
これは誰かを批判しようとして言っているわけではない。単純に本当のことなのだ。
より厳密な例を出せば、こうなる。
テレビゲームのゲームデザインについて勉強してきて気がついたのは、パズルというものが直線的で単純な仕組みになっているということだ。直線的、という言葉で何が言えるのだろうか? それにはどれほどの利点があるのだろうか?
パズルをやる上で必要なのは、多くのステップを踏むことだ。そうすれば、さらに先へ進めるようになる。オブジェやスイッチをどこへ置くべきか、そしてどこでレーザーを反射させればいいかを、理解する必要もある。これらは他の要素と組み合わせられて、数多くのプラットフォームゲームやハック&スラッシュゲームで用いられている。理由は、それらが上手く機能するからだ……。
〔※訳注:ゲームの種類のうち前者は、スーパーマリオ等の、主人公が平面の台の上を移動するゲーム。後者は敵をひたすら叩き切っていくようなゲーム〕
そういったステップは単純だが、数は多くある。3つも博士号を持っている大学教授ならば、これらのステップ全部を高速でこなしたときに、自分が頭を使ったと感じるだろう。
我々も自分が頭を使ってできたと感じることがあるし、それは別に難しいことではない。8歳の子供でも、自分が頭を使ったと感じることはあるだろう。ここに何かのパターンはあるのだろうか?
たとえば、一匹の犬がパズルの参加者になったとして、そのパズルをIQ200の大学教授と同じスピードで解いたとする。この場面には出くわしたことがある。そのパズルは極めて直線的で、間違えようがないものだった。できる行動はつねに一通りしかなく、そのため常に正しいものになっていた。
それをパズルと呼びたくないのはなぜだろう? これは単純な、簡単な種類のものだが、それでもパズルだ。楽しく遊べる余地の多くあるパズルだ。世界で一番出来の悪い子供でも解くことができ、大学教授と同じくらい自分が頭を使えたと感じられるようなパズルだ。そしてその両者が、ともに楽しめるようなものなのだ。
自分のスキルが試されるようなものが欲しい? 頭を使うよう要求されるようなものが欲しい? ならばどうしてあなたはこんな記事を読んでいるのだろう。数学や論理学の問題集でも解けば良いはずなのに。だが、その通り、そんなものは楽しくないのだ……。
このことは、どういう形でポケカに当てはまるのだろうか?
相手を「倒す」方法としてあまりにたくさんのことをやろうとし、それぞれのシチュエーションに全く異なったやり方で対処しようとするデッキがある。
「あ、ドラゴンダイブを撃ったね? 罠に掛かったな。こっちの手札にはエテボースGとダブル無色があるから、その攻撃にはカウンターさせてもらうよ」
「そんなばかな、想定通りのマッチアップの想定通りの場面でこれを使われるだなんて。やるじゃないか! でもこちらにはハマナがあるから、ドクロッグGと超エネを持ってくるよ。エテボースかレントラーがサイドを取ってきたときの自動プレイだ。サイドいただくよ!」
どうだろうか? 直線的とは……。
それでもプレイヤーたちは、デッキ内で多くのことをやろうとしてしまう。特定の場面に対処できなくなるのを恐れるあまり、1枚挿しが20種類も入って、アタッカーの線があまりに細くなってしまったようなデッキを見たことはないだろうか。たとえば、
2 ゴウカザルFB
1 ゴウカザルFB Lv.X
2 レントラーGL
1 レントラーGL Lv.X
1 アグノム(DP5)
1 何か
1 何か
1 何か
…
…
…
1 プレミアボール
これの何が駄目なのだろうか? アタッカーの線の細さだ。なぜそうなってしまったのだろうか? スペースがないからだ。なぜスペースがなくなったのだろうか? 強烈なカウンターカードがこんなに必要だから? 恐らくこの時代最強のデッキであるにもかかわらずこんなにたくさん? でも、リカバリーが速くできないから。どうして? それはアタッカーの線が細いから……。
カウンターカードが頭を使うプレイのように見えてしまうがために、デッキ内のラインはどんどん複雑になっていく。そして、安定しなくなっていく。
アタッカーを引っ張るのにアグノムを必要とする2-1ラインは、頭を使いそうに見える。プレミアボールもアタッカーとの置き換えで、それをサーチできるようになっている。だがこれは、カードの致命的なサイド落ちの危険性を高め、パワースプレーされる可能性もあれば初手スタートの可能性もあるカードへの依存度を、いっそう高めるだけだ。実際、初手スタートするかスプレーされるかでアグノムを失ったら、どうにもならなくなってしまう。
これはただ大変になっているだけであり、賢くやれているわけではない。このリストは頭を使いそうなデザインに見えるが、単なる脆弱な構築に過ぎず、安定した立ち上がりをさせたい使用者にストレスを与えるだけだ。繰り返しになるが、こういった不出来な構築でも頭を使えたと感じるならば、それはただ多くの選択肢があったからに過ぎない。だが説明したとおり、実際、そんなのはただの幻想だ。
あらゆる場面でそれに応じた特定のプレイを必要とするというのは、対戦相手の行動に対して自動で反応するロボットになるということだ。事実、ギミックの詰め込み過ぎは、プレイを予想のできるものにする。相手がギミックを理解できてしまえば、サプライズ要素など消え去り、こちらが次にやろうとする行動を相手が知っているということになる(もっとも、安定しないデッキでちゃんと行動できればの話だが)。
おおざっぱにまとめればこういうことだ。相手に解答を探させるような、能動的なプレイヤーになろう。相手の行動に応じて解決策を探すような、受動的なプレイヤーになってはいけない。
ギミックと安定性を巡る永遠の葛藤については、次回の記事で触れようと思う。今は、誰もが知っている次の事実を指摘しておこう。
+ギミック=-安定性
同様に、
多くをやろうとすればするほど、できることは少なくなっていく。
■Jasonの優勝PLOXリスト
機能するデッキには目標がひとつしかないことは上で述べた。なぜJasonは2つ言っていたのだろうか?
目標は安定性だ。それは、常に自分の戦略を機能させてくれる。ミラーで強みを持たせるというのは、安定性に到達する上での心構えに過ぎない。強烈な対策ギミックを加えるというのは、それとは正反対のことだ。
あるマッチアップで強みを持たせるというのは、デッキに馴染むオプションを加えることで達成できる。それは、柔軟性のあるリストにすることを意味する。
強烈な対策カードは、ある特定の場面では有効だが、機械的なリアクションとなる。その一方で、柔軟性のあるカードならば、2つ以上の目的を持たせることができ、デッキのメイン戦略から外れることもない。それこそが本当の意味でのデッキに馴染むオプションといえる。それは、ただ自分が頭を使ったと感じるだけの幻想とは違うものだ。
では、デッキリストを見ていこう。
PLOX by Jason Klaczynski - 2008年世界大会優勝
4 ラルトス(DP3)
2 キルリア(DP3)
3 サーナイト(DP4)
1 サーナイトLv.X(DP4)
2 エルレイド(DP3)
2 ヤジロン(DP4)
2 ネンドール(DP4)
1 ヨマワル(DP1)
1 ヨノワール(DP1)
1 ペラップ(DP4)
1 ジラーチex(PCG8)
1 サンダース☆(promo)
彼のレポートと同じように、それぞれの部分を個別に見ていきたい。まずはポケモンからだ。
シンプルで、安定している。デッキの機能に忠実になろうというのがその考え方だ。相手より速く展開できれば、相手の対策カードも追いつけなくなる。
アタッカーのライン以外で目に付くのは、ヨノワールでの精神的なプレッシャー(相手デッキがアブソル(BW8)入りと知っている状況と比べてほしい)と、追加の「サイコロック」になるジラーチexだ。そして、サンダースが入っている……。
サンダースは柔軟性の最初の例だ。相手を一撃で倒すのに10点だけ足りなかったりすると、相手は追加の1ターンを得てしまう。サンダースは、サーチ可能なプラスパワーとなることで、そういった状況を避けることができる。そのような追加のダメージカウンターは、PLOXのダメージ計算では欠かせないものだ。
・W虹付きのサイコロックは、よく使われるたねポケを落とせないことがある(たとえばペラップ)。
・湖の結界が場にある状態で、PLOXはW虹付きだと相手のサーナイトに100ダメージ、エルレイドに120ダメージしか与えられない。
・サーナイトLv.Xはサイコロックを10残して耐える。
・ジラーチexのちょうねんりきはサーナイトに100ダメージしか飛ばない。
・エルレイドがエンペルトを落とすとき、サイド4枚ではなく3枚めくるだけで済むようになる。
・ホロンエネFFつきのハピナス(DP2)に対しても、サンダースなしだとエルレイドはサイドを4枚めくる破目になる。
・相手のジラーチexに対しても、サンダースなしだとエルレイドはサイド3枚の代わりに2枚めくりで済むようになる。〔※訳注:恐らく1枚の間違い?〕
これが柔軟性ということだ。それがお助けカードにしかならないようなマッチアップでも、少なくとも2つ以上の状況で働いてくれる。致命的な使い方のできるその他のマッチアップでなら、有効なギミックになりうる。
再びおおざっぱなまとめをしたい。死に札は作らないようにしよう。そしてほとんどの場合、対策カードは死に札なのだ。
4 ハマナのリサーチ
4 ニシキのネットワーク
2 ミズキの検索
2 ギンガ団の賭け
2 ダイゴのアドバイス
この記事の趣旨を鑑みれば、ここをあえて強調する必要はないだろう。安定した枚数が入っていて、ネンドールと、サーナイト(このデッキの核だ)を可能な限り速く立てることに注力されている。
4 ふしぎなアメ
2 暴風
2 ワープポイント
2 湖の結界
湖の結界については上で何度か触れたので、有用性は明らかだろう。
このカードの主な目的は、このデッキにとって重要なW虹やスクランブルを無効化してしまうクリスタルビーチを割ることだ。Jasonはスタジアムや封印の結晶を割るため暴風を2枚入れているだけでなく、様々な状況で便利なこのスタジアムも2枚入れている。同時にそれは、このデッキにとって脅威になるカードに対する、効果的なカウンターにもなっている。
繰り返しになるが、用途が多いということは、デッキの弱点を取り除くと同時に、死に札にならないということだ。より多くのオプション、さらなる安定性、そして、より高い柔軟性。
4 コールエネルギー
3 超エネルギー
1 サイクロンエネルギー
4 Wレインボーエネルギー
3 スクランブルエネルギー
このエネルギーの部分を最後に残したのは、特に興味深い箇所はないからだ。4枚のコールエネとW虹は高速展開の可能性を最大限に高めてくれるし、1枚おしゃれに積まれたサイクロンエネは、封印の結晶対策になると同時に、ダメージを稼がれてしまう相手の壁カードへの対策になっている。
このデッキを何度か(特にミラーを)回してみたあとでは、4枚目の超エネルギーがあっていいかもしれないと思った。だがそのために抜けそうなカードは、おそらくそのエネルギーよりも重要なカードだろう。
最後に、別のリストと見比べてみたい。
■比較例
PLOX by Gino Lombardi - 2008年世界大会3位, 2008年アメリカ選手権優勝
4 ラルトス(DP3-3,PCG6-1)
2 キルリア(DP3)
3 サーナイト(DP4)
1 サーナイトLv.X(DP4)
2 エルレイド(DP3)
2 ヤジロン(DP4)
2 ネンドール(DP4)
1 クレセリア(DP4)
1 クレセリアLv.X(DP4)
1 ベトベター(DP3)
1 ベトベトン(DP3)
1 パチリス(DP4)
1 ジラーチex(PCG8)
1 フィオネ(DP4)
3 ハマナのリサーチ
2 ニシキのネットワーク
2 ミズキの検索
2 ギンガ団の賭け
3 ダイゴのアドバイス
4 ふしぎなアメ
1 ワープポイント
1 湖の結界
1 夜のメンテナンス
1 ちからのかけら
2 フヨウのスタジアム
3 コールエネルギー
5 超エネルギー
4 Wレインボーエネルギー
3 スクランブルエネルギー
この年はGinoの黄金期だった。その年最大の大会で優勝し、そして世界大会でもトップ4になったのだから、偉業と言わず何と言おう。
このリストには、目立った欠点がいくつかある。
・初手スタートすると弱いカードが多い。
・貧弱なサポーターのライン
・封印の結晶への解答がない。
・コールエネルギーが3枚のみ。
ギミックが数多く詰め込まれているせいで、このデッキは、そう頻繁には完璧な立ち上がりができるわけじゃない。それに加えこのデッキには、ミラーマッチ以外では完全な死に札になる、対策カードが入っている。これだけ多くの1枚挿しがあると解答がサイド落ちする可能性があるし、クレセリアを手助けする手段がワープポイント1枚しかない。
サポーターラインを削り、ギミックを増やして、100%ポケパワーに依存したデッキにとっては、封印の結晶への対策がないのは致命的だ。クリスタルビーチを割るためにフヨウのスタジアムが2枚入っているが、ときたまいるキノガッサに好き放題やられるのを防げて、かつ非常に用途の多い湖の結界は、1枚しか入っていない。もうひとつ欠点を挙げればヨノワールが入っていないことだ。それだけで相手が息を吹き返せるだけの(文字通りの)余分なスペースを与えてしまう。そのスペースは、エンペルトが海辺でみんなでなみのりを(シャレじゃない)するのに欠かせないものだというのに。
それでもGinoは優秀なプレイヤーであり、このリストで相当に上の方まで進むことができた。そして、それは幸運のおかげだけではなかったのだ。
・ワープポイントが1枚だけとはいえ、フヨウのスタジアムはクレセリアを立てるのに大きな助けとなる。クレセリアは一度立ってしまえば、回復と同時に半永久的なプラスパワーになれる。エンペルトのデュアルスプラッシュに対しても強くなる。
・ベトベトンは強烈な対策カードだ。だが、よく機能した。W虹や起動済みのスクランブルエネのついた相手なら、何でも毒状態にできたのだ。このカードは特定の場面でのみ強いカードだが、それでも実際は大半のプレイヤーがPLOXを使っていたせいで、ミラーでの強烈な対策カードは、多大なアドバンテージになった。
・フィオネはW虹つきのサイコロックなら耐えることができ、その間にサーナイトやエルレイドを育てられる。パチリスでも同様のことが言えるが、思うにこのカードは、4枚目のコールエネの代わりになっていたのだ。
・ちからのかけらは、封印の結晶のようなどうぐを使ってくる多くの相手に対して、テレパス経由で探しに行くカードだ。だが、テレパスを止めてくる封印の結晶への対策がなければ、そこまで有効にはなりえない。またこのカードは、相手のサイコロックでサンダースが封じられた状況下で使うこともできる。
だが、過去に思いを巡らすことの意義とは何なのだろう? これらの話から、いったい何を得られるのだろうか。
異なったメタゲームや愛すべきゲームの歴史を学ぶことは楽しい。だがそれとは別に我々は、フォーマットに関係なく機能するものとは何かを学ぶことができる。
これらの記事の究極の目標は、プレイヤーが、どんなフォーマットにも、どんな状況にも適応できるよう手助けをすることだ。とあるプレイヤーがとあるデッキで結果を残せていたとしても、そのプレイヤーは、別のデッキでは結果を残せないかもしれないし、新弾が出ても自分のデッキをそれに適応させられないかもしれない。つまるところ、この記事がやりたいのは、プレイヤーの小さなミスを見つけ、スキルを完璧なものにするための手助けをすることだ。
少し先走りすぎたかもしれないが、ここで、学んできたことを使ってひとつ実践的なサンプルを見せたいと思う。
■トップメタデッキにおける柔軟性:現代編
自分の考えでは、完成形になって以来ずっと強力で、かつローテーションまで消えないであろうデッキのひとつは、カメックスだ。
このデッキは強いデッキだと誰もが知っているし、当たったときのために準備をする必要がある。そのため、大会でカメックスを使うのは悪くない賭けだと考えてもいい。プレイがあまり難しくなく、非常に強力だ。
目の前には、他のプレイヤーにとって脅威になるデッキがある。彼らがこのカメックスを脅威と感じる理由を、下記のガイドラインから裏付けてみよう。
安定させること。そしてその延長線上で、ミラーで強みを持たせること。また、ありがちな欠点に対して、柔軟な解決策を持たせること。
まずはポケモンから始めよう。
Standard Blastoise by Joao Lopes
4 ゼニガメ
3 カメックス
2 ケルディオEX
2 ブラックキュレムEX
1 ブラックキュレム
1 ジラーチEX
1 タマタマ
ポケモンキャッチャーが無くなったことで、ジラーチEXはカメックスにとって手堅い利点になった。ジラーチEXは、ハイパーボールや、ときにはレベルボールを、ビーチや、アメや、カメックスや、アララギや、スーエネ回収や、Nにも変えてくれる。このおかげで安定性が驚くほど増しているし、1ターン目のゼニガメ/ビーチや2ターン目のカメックス+アタッカーのような破壊的な展開を手助けしてくれる。
カードを少し引いたあとでならカメックスを見つけるのは容易だが、ゼニガメでスタートするのは簡単ではない。そのため、安定性を最大化するのにゼニガメ4は必須だ。余ったゼニガメは、あとでハイパーボールやスーエネ回収で捨てることができる。
カードを捨てることに関して言えば、このデッキのすべてのカードはあのおおざっぱなまとめ話に従っている。つまり、どんなマッチアップでも、無駄になるカードは入っていない。それを頭に入れておくと、上で触れたボール系や回収系は、捨てる余裕のないはずのカードを切ってしまう破目に陥る、ということになる。コストを軽減するためのタマタマは、1キルがほとんどない環境なので、安全に使うことができる。
アタッカーについては、それぞれを2枚ずつ入れれば十分に足りる。3枚目は必要にならないし、デッキがきちんと動けば1枚でもたいてい非常に良い仕事をしてくれる。考え方としては、ほとんどの対戦で非EXポケモン1枚とEXポケモンを2枚倒されるということになっている。アタッカーが4枚いれば、3枚目のEXがゲーム終盤で使えるようになるだろう。
さて、柔軟性のあるカードでミラーに強みを持たせよう。非EXのブラックキュレムだ。これはよく知られたギミックだが、そこまで使われてはいない。ドラゴンの殴り合いになればこのカードは1枚でサイド2枚と交換になり、相手のプランを崩壊させられる。この見え見えの使い道以外だと、バトル場に放置された相手のゼニガメやタマタマをこれで倒すというものがある。自分のデカブツをわざわざ危ないところに出さなくて済む、というわけだ。
ミラー以外だと、非EXポケモンがいれば重要なアタッカーを使わず生かしたままにしておける。一番良くある相手がヤミラミだ。このオプションは、考える以上に有効だ。また、このカードがあれば、ケルディオEXが倒されたあとでもガブリアスあたりの適当なドラゴンを狩ることができるし、レックエンブのような相性の悪いマッチアップも5分5分で戦うことができる。
4 アララギ博士
3 N
4 フウロ
2 アクロマ
自分はいつもサポーターの最低ラインは14枚にしているが、今回の場合は、ジラーチEXがボールをサポーターに変えてくれる。そのため、サポーターの枚数カウントはもっと多いものとして扱える。
ここでもうひとつ指摘したいのは、4枚目のNを入れていないことだ。Nは本当に強力なサポーターだが、このデッキは、Nを使い倒せるようなデッキではない。その代わり、アクロマ2枚が、中終盤では最強のサポーターになってくれる。ときにアクロマの入っていないデッキがあるのは、このカードが序盤では役立たずだからだ。だがこのデッキなら序盤はフウロとトロピカルビーチに依存するし、サポーターを切り替えるころには、アクロマはオーキド博士の新理論と同等かそれ以上の働きをしてくれる。それでもN3枚とアクロマ2枚にしているのは、このデッキが序盤の数ターンで展開する必要があること、そして、デッキのメインの目的に絞って構築する必要があるからだ。
フウロ4枚は疑いの余地ない選択だ。このデッキが一番必要とするカードであるし、このデッキの手札はいつも、完璧なものからはグッズ1枚ぶん足りない。そういうとき、フウロは最高の相方になってくれる。アララギに関して言えば……アララギはアララギだ。可能なら、10枚でも使いたいカードだ。
4 ハイパーボール
2 レベルボール
4 ふしぎなアメ
4 スーパーエネルギー回収
3 トロピカルビーチ
2 ツールスクラッパー
2 エネルギー転送
1 ポケモン回収サイクロン
ボール系が6枚というのは、Jasonのデッキでサーチ系のサポーターが6枚だったのと同様だ。ここでは、2ターン目のカメックスを保障してくれる。ハイパーボールを最大枚数入れておけば、1ターン目にゼニガメを引く方法は6枚もあるし、2ターン目にカメックスやアタッカーを引くカードも4枚確保できる。
ダストダスが常に脅威である以上は、ツールスクラッパー投入はマストだ(封印の結晶に対しての暴風と同じだ)。おまけとして、エンペルト(最近流行ってきている)のシルバーバングルを剥がすことができるし、他のデッキのかるいしを剥がして妨害することもできる。
2枚のエネルギー転送は、この氷のドラゴンのために雷エネルギーを引くのに必要であり、またケルディオのために水エネルギーを確保する手段でもある。困ったときにはフウロがエネにもなる。2枚しか入れていないのは、エネの総数を減らしてあっという間にエネ切れを起こすのを防ぐためだ。
ポケモン回収サイクロンは、自分の住んでいる地域でカメックスを使っているプレイヤーから拝借したアイディアだ。まんたんのくすりよりも強いカードだし、ジラーチEXを再利用したり、エネを捨てずに逃げることができたりと、多くの場面で使えるカードだ。構築が安定していればパソコン通信は必ずしも必要ではないし、このカードは、相手の前のターンの動きを無駄にできたり、それ以上のこともできる。
2 雷エネルギー
9 水エネルギー
エネルギー転送は、水と雷の両方を探せるという点以外にも、雷エネの実数を削って水エネの使える量を増やせるという点がある。
このデッキリストは、オプションを組み入れつつ安定性を目指すという原則に基づいて構築されたものだ。カメックスのような、動きが一直線なデッキでも、それは可能だ。
もちろん、環境や、そのプレイヤーのメタ読みの能力にも依存する。数枚変えただけで、特定のマッチアップ相性が改善することだってある。とはいえ、環境への適応については、日を改めて議論をするとしよう……。
■結論
複雑な戦術が展開できたときの美しい光景には、みなが魅了されがちだ。だが現実は、手の込んだことをやって失敗するよりも、シンプルなことを正しくやるのが一番なのだ。
当たり前の知恵は忘れられやすい。我々はみな、戦術を完遂して純粋な安定性で勝ちに行くよりも、あらゆるデッキに対して何らかの解答を用意しようとしてしまう。
ある状況で強いカードは、別の状況では邪魔なカードになる。柔軟性は、ギミックと安定性のあいだでバランスを保ってくれるものなのだ。
次の記事ではデッキ構築における別の要素について書いてみたい。大会だ。League Challengeから世界大会まで、その違いを見出すのは簡単だ。つまり、難易度が上がり、プレイヤーが増える。だが、とある構築が大会環境に合っていたとして、その翌年には、その大会環境に合う構築が全く変わってしまうとしたら?
次回は、環境に適応することについてだ。Pesadelo Prism (2012)とStraight Darkrai (2013)を取り上げてみたい。〔※訳注:前者は2012年の世界大会優勝のダークライM2。後者は恐らく2013年の世界大会優勝のダークライ。〕
◆ ◆ ◆ ◆ ◆
以上になります。お読みいただきありがとうございました。
文字数にして15000超えという非常に長い記事でした。それでも、最後までお読みいただいた方にとっては、必ずや得られるものがあっただろうと思います。
かく言う僕にとっても、実は2007~2008年ごろは某MtGにかまけていたので、なかなか新鮮な内容の多い記事でした。
ふたつのサーナイト/エルレイドの比較のあたりは白眉ですね。また、ゲームデザインを例に出して、なぜギミックは有効性が低いのかを語るくだりも、大変ためになるものだったと思います。
この著者は、次回はふたつのダークライデッキを取り上げてくれるようですね。次回にも期待大です。
第2回トキワ杯に惨敗する
2014年2月16日 予選4-0抜けから決勝一没でした。一没王子たちの気持ちが理解できました。
デッキはイエティ。竜王戦レギュ脳内メタ一周の結果の謎チョイスでした。
前日までの調整で、フェアリーバレットやっぱ強えわに落ち着く。どのデッキにも大きな不利がつかないデッキなので、真面目に潰そうとするとイベルダスト+シャドーサークルみたいなデッキになりかねません(厳密にはフェアリー対レックビールは45-55くらいだと思います)。
ただ、現環境のダークダスト系は個人的にあまり評価していなくて、理由はいくつかあるのですが、現環境ダークダスト派生が去年の世界大会段階のダークダストとは構築コンセプトが正反対で違う、というのが一番の理由です。
デッキのポテンシャル自体が高く、そこに苦手を潰すためにダストを乗せた2013世界ダークダストと、始めからダストありきで考えられている現環境ダークダスト系では、元々のデッキパワーがかなり違ってくるはずだからです。
もちろん、ダストが刺されば使用を正当化する理由になりえますし、事実、現環境のダストは相当に刺さるのですが。
余談ですがポケカでは基本的に後ろ向きのカードは弱いので、シャドーサークルも実際は評価に困るカードです。でも強いんだよなあ、イベルタルとシャドーサークル。
あとはまあ、竜王戦レギュなのでハイパーボールドラゴントラッシュが単に嫌というのはあります。
(ちなみにここまでが前日の読みで、実際はハル父さんのイベルダスト優勝で盛大なフラグと化したわけですが)
そんなわけで脳内はフェアリーバレットとレックビールの2強になりました。ひっそり組んでたマフォエンブはゲノとダスト両方ケアすると60枚に収まらず、マニュタマはフェアリーバレットにボコボコにされて諦めました。最終兵器ダストアギルダーは竜王戦では無理でした。
イエティは、改造ハンマー(フェアリーだと死)が来てもぎりぎり戦えて、ダスト(レックビールだと心折れる)相手にもぎりぎり戦えて、フェアリーとレックビールにもぎりぎり戦えるという、全デッキに勝率45%みたいなデッキです。
でも先週のことがあるのでフェアリーはメタられてるはずだし、レックビールはミラー練る気が起きなかったので、最終的にイエティに決めたというわけです。
一応いじってたやつ全部デッキ貼ります。
4 デオキシスEX
2 ボルトロスEX
2 ルギアEX
2 カビゴン
1 パルキアEX
1 ゲノセクトEX
4 アララギ博士
4 N
3 アクロマ
2 フウロ
1 ベル
1 ダークトリニティ
4 アクロママシーン
3 ちからのハチマキ
3 あなぬけのヒモ
3 かるいし
2 ツールスクラッパー
2 ハイパーボール
1 プラズマ団のモンスターボール
1 スクランブルスイッチ
4 ダブル無色エネルギー
4 プラズマエネルギー
4 雷エネルギー
2 プリズムエネルギー
4 シビシラス
4 シビビール
2 ゼクロム
2 レックウザEX
1 レックウザ
1 ライコウEX
1 バリヤード
1 ジラーチEX
4 アララギ博士
4 N
4 アクロマ
4 ハイパーボール
3 レベルボール
3 ツールスクラッパー
2 はかせのてがみ
2 ちからのハチマキ
2 すごいつりざお
2 ポケモンいれかえ
1 あなぬけのヒモ
1 スカイアローブリッジ
1 ダウジングマシン
7 雷エネルギー
4 炎エネルギー
3 シュシュプ
3 フレフワン
2 ランドロスEX
2 ボルトロスEX
2 ゲノセクトEX
2 ダークライEX
1 ビリジオンEX
1 ギラティナEX
1 コバルオンEX
4 アララギ博士
4 N
3 アクロマ
2 フウロ
1 ベル
4 ハイパーボール
1 レベルボール
3 ちからのハチマキ
2 かたいおまもり
2 まんたんのくすり
2 ツールスクラッパー
1 げんきのかけら
1 ダウジングマシン
4 レインボーエネルギー
4 プリズムエネルギー
4 プラズマエネルギー
1 フェアリーエネルギー
イエティはパルキア抜きたい。フレフワンは色々あってのスイクン抜き。そして良く見るとダスト対策がいろいろ施してあるレックビールとフレフワン。僕は幼女に興味がないのでサナは使ってません。
予選はフェアリーパルキアランドダストフェアリーに勝って抜け、決勝1回戦目でレオンさんのフェアリーに負けて死。事故ってパルキアで殴らざるを得なくなってのジリ貧負けでした。なぜイエティ使ったし。
というわけで竜王戦予選レギュとの戦いは個人的には終了。でも本番は来週末だからね……!
デッキはイエティ。竜王戦レギュ脳内メタ一周の結果の謎チョイスでした。
前日までの調整で、フェアリーバレットやっぱ強えわに落ち着く。どのデッキにも大きな不利がつかないデッキなので、真面目に潰そうとするとイベルダスト+シャドーサークルみたいなデッキになりかねません(厳密にはフェアリー対レックビールは45-55くらいだと思います)。
ただ、現環境のダークダスト系は個人的にあまり評価していなくて、理由はいくつかあるのですが、現環境ダークダスト派生が去年の世界大会段階のダークダストとは構築コンセプトが正反対で違う、というのが一番の理由です。
デッキのポテンシャル自体が高く、そこに苦手を潰すためにダストを乗せた2013世界ダークダストと、始めからダストありきで考えられている現環境ダークダスト系では、元々のデッキパワーがかなり違ってくるはずだからです。
もちろん、ダストが刺されば使用を正当化する理由になりえますし、事実、現環境のダストは相当に刺さるのですが。
余談ですがポケカでは基本的に後ろ向きのカードは弱いので、シャドーサークルも実際は評価に困るカードです。でも強いんだよなあ、イベルタルとシャドーサークル。
あとはまあ、竜王戦レギュなのでハイパーボールドラゴントラッシュが単に嫌というのはあります。
(ちなみにここまでが前日の読みで、実際はハル父さんのイベルダスト優勝で盛大なフラグと化したわけですが)
そんなわけで脳内はフェアリーバレットとレックビールの2強になりました。ひっそり組んでたマフォエンブはゲノとダスト両方ケアすると60枚に収まらず、マニュタマはフェアリーバレットにボコボコにされて諦めました。最終兵器ダストアギルダーは竜王戦では無理でした。
イエティは、改造ハンマー(フェアリーだと死)が来てもぎりぎり戦えて、ダスト(レックビールだと心折れる)相手にもぎりぎり戦えて、フェアリーとレックビールにもぎりぎり戦えるという、全デッキに勝率45%みたいなデッキです。
でも先週のことがあるのでフェアリーはメタられてるはずだし、レックビールはミラー練る気が起きなかったので、最終的にイエティに決めたというわけです。
一応いじってたやつ全部デッキ貼ります。
4 デオキシスEX
2 ボルトロスEX
2 ルギアEX
2 カビゴン
1 パルキアEX
1 ゲノセクトEX
4 アララギ博士
4 N
3 アクロマ
2 フウロ
1 ベル
1 ダークトリニティ
4 アクロママシーン
3 ちからのハチマキ
3 あなぬけのヒモ
3 かるいし
2 ツールスクラッパー
2 ハイパーボール
1 プラズマ団のモンスターボール
1 スクランブルスイッチ
4 ダブル無色エネルギー
4 プラズマエネルギー
4 雷エネルギー
2 プリズムエネルギー
4 シビシラス
4 シビビール
2 ゼクロム
2 レックウザEX
1 レックウザ
1 ライコウEX
1 バリヤード
1 ジラーチEX
4 アララギ博士
4 N
4 アクロマ
4 ハイパーボール
3 レベルボール
3 ツールスクラッパー
2 はかせのてがみ
2 ちからのハチマキ
2 すごいつりざお
2 ポケモンいれかえ
1 あなぬけのヒモ
1 スカイアローブリッジ
1 ダウジングマシン
7 雷エネルギー
4 炎エネルギー
3 シュシュプ
3 フレフワン
2 ランドロスEX
2 ボルトロスEX
2 ゲノセクトEX
2 ダークライEX
1 ビリジオンEX
1 ギラティナEX
1 コバルオンEX
4 アララギ博士
4 N
3 アクロマ
2 フウロ
1 ベル
4 ハイパーボール
1 レベルボール
3 ちからのハチマキ
2 かたいおまもり
2 まんたんのくすり
2 ツールスクラッパー
1 げんきのかけら
1 ダウジングマシン
4 レインボーエネルギー
4 プリズムエネルギー
4 プラズマエネルギー
1 フェアリーエネルギー
イエティはパルキア抜きたい。フレフワンは色々あってのスイクン抜き。そして良く見るとダスト対策がいろいろ施してあるレックビールとフレフワン。僕は幼女に興味がないのでサナは使ってません。
予選はフェアリーパルキアランドダストフェアリーに勝って抜け、決勝1回戦目でレオンさんのフェアリーに負けて死。事故ってパルキアで殴らざるを得なくなってのジリ貧負けでした。なぜイエティ使ったし。
というわけで竜王戦予選レギュとの戦いは個人的には終了。でも本番は来週末だからね……!
【翻訳】No.004:私のポケカライフ2002
2014年2月19日
今回は60cards.netから。大和さんの記事第4弾の翻訳になります。
春の惜敗からのリベンジを期す大和さん。ゲンダイルを相棒に仙台大会へと臨みますが、そこにいたのは堅牢なハッサムの群れ。絶体絶命の状況の中、打開策を求めてカードファイルを覗くと、そこには……。
という、あらすじにしただけで既に面白い物語が今回のメインです。
e時代の懐かしいカードに浸りながら、ぜひ今回もお楽しみください。
いつもどおり、訳語の至らなさや誤訳の責任は、すべて僕うきにんに属します。
斜体は引用文です。読みやすさを考慮して、改行を変更した部分があります。
テキストの引用は前回同様ポケモンWikiさんからです。
(今回も例によって無許可翻訳なので、何かあればすぐに削除します)
◆ ◆ ◆ ◆ ◆
No.004 My Pokemoncard Life 2002
by Tsuguyoshi Yamato, trans. Majyo
Thursday, February 13, 2014
ttp://60cards.net/blog/posts/detail/126
読者のみなさん、こんにちは! チームアチャモの大和です!
これは私のポケカライフ記事で4番目にあたります。今回は、2002年の後半部分について書きたいと思います。
3番目の記事では、2001年夏の大会で3位になれたこと、その一方で、2002年春の大会では決勝トーナメントの初戦で負けてしまったことについて書きました。2年続けて仙台大会で優勝したいと願っていたにもかかわらず、それは叶わなかったわけです。それでも、その試合に負けたことは自分にとって大きな経験となりました。時間管理という、大事な教訓を学ぶことができたのですから。
学んだことに思いをめぐらせながら、私は2002年の夏にリベンジを期そうと準備していました。
使用可能カードの量自体には、あまり大きな変化はありませんでした。春以降は、eシリーズ第3弾しか発売されていなかったからです。eシリーズ初弾が出たのが2001年の12月で、次が2002年の3月、そして第3弾が出たのが2002年の5月です。ここで追加されたのは、わずか90枚のカードでした。しかしそれでも、現行のメタゲームを変えてしまうには十分だったんです。
(※英訳者注:これらの拡張パックを見直していて思い出したのですが、eシリーズは、日本では5弾まであるにもかかわらず、海外のたいていの場所では3弾までしかありません。原則として、Expeditionには日本でいうeシリーズ第1弾が入っています。Aquapolisには第2弾と第3弾、Skyridgeには第4弾と第5弾です。なので基本的には、当時の使用可能カードはAquapolisまでということになります)
当時のメタゲームで最も強かったカードのうちの1枚は、ハッサム(e3)でした。HPはそこまで高くありませんが、特殊鋼エネルギーがつくと、簡単には落ちなくなります。またレインボーエネルギーも、コインが必要とはいえヘビーメタルの打点を上げるのに大きく寄与していました。
また、オオタチ(e3)のたからさがしは、1ターンにあまり多くのカードをドローできなくても、鋼やレインボーエネルギーを簡単に探すことができました。
ハッサムにはもうひとつ強いワザがあり、ねらってつかむとプラスパワーを使えば、相手ベンチのベイビィポケモンを倒すことができました。ベンチのベイビィを攻撃するときは、コインを投げる必要はなかったんです!
ハッサムは他のどんな2進化よりも強く、強力なワザも2つありました。トップメタになるには十分な強さでした。その当時見られたほとんどのデッキは、ハッサムか、ハッサムアンチのデッキでした。
ところで、マルマイン(e2)のポケパワーを日本語で何と言うか、聞いたことがあるでしょうか? マルマインのポケパワーとシビビールのとくせいは、効果が違うにも関わらず、全く同じ名前なんです!
マルマインのエレキダイナモの効果はシビビールのとかなり似ているにもかかわらず、シビビールの方がずっと強いのですから、名前が同じというのはちょっと信じられませんね。それでも、新しいカードが古いカードを参照していると気づいたときは、非常に面白かったです。
では、大会ルールを見てみましょう。
前回同様、ジュニアとシニアはネオシリーズからeシリーズまで、マスターは一番最初の弾からeシリーズまででした。しかしこの大会は、昔のセットが使えた最後の大会となりました。
予選のデッキは30枚で、決勝トーナメントのデッキは60枚です。このルールは非常に長い期間にわたって用いられました。そしてまた、それぞれのリーグで優勝すれば、日本一決定戦に参加する権利を得ることができました。
ここからは、この当時のデッキを紹介させてください。
ハッサム(e3)/オオタチ(e3)
上のほうで説明したとおり、このデッキは当時のトップメタでした。オオタチのポケパワーで特殊エネルギーを引いてこれるため、鋼エネ4枚と虹エネ4枚をまとめて貼ってしまうこともそう難しくなかったんです。また、いったんハッサムに鋼エネが2、3枚ついてしまえば、デッキにはきずぐすりも入っているため、そう簡単には落ちなくなります。ヘビーメタルが特定の色エネを要求しないので、多少のサブアタッカーを選ぶ余地もありました。とはいえ、ハッサムの弱点が炎のため、たいていのプレイヤーはサブアタッカーに水ポケモンを選択していました。
デンリュウ(e1)/キュウコン(e1)
ハッサムを倒しやすいようにと、大きな打点を出せるデッキもありました。このデッキは、そのうちの代表的なものです。
キュウコンのよみのほのおがメインアタッカーですが、ついていたエネルギーをすべてトラッシュしてしまうため、デンリュウがサポート役としてデッキに入っています。
デンリュウのポケパワーのエナジーコネクトで、キュウコンが途切れずに攻撃できるようになっていました。
R団のバンギラス(VS)/超エネルギーリムーブetc
(※英訳者注:R団のバンギラスはVSシリーズのカードで、このカードは日本でしかリリースされていません。VSシリーズには特別なテーマデッキがあり、トロピカルメガバトルでは使うことができました。このデッキはもともと日本で映画の『セレビィ』のためにスペシャルテーマデッキとして作られたもので、そのなかにR団のバンギラスが入っていました。トロピカルメガバトルでは、このデッキはそれぞれの国の代表の言葉ごとに作られましたが、カードは非公式カードとして扱われたうえ、それらの中にはR団のバンギラスは入っておらず、代わりにトロピカルウィンドが入っていました。
ちなみにR団のバンギラス自体はシークレットカードとして扱われていたにもかかわらず、拡張パックからは手に入れることができませんでした)
さて、R団のバンギラスのワザを見てみましょう。
超エネルギーリムーブ2やデストロイビームで一度表が出てしまえば、ハッサムの攻撃と防御をくい止めるのはそう難しくはありません。とはいえ、悪タイプで大きな打点を出せるポケモンがいなかったため、このデッキは完全にアンチハッサムデッキとなっていました。
さて私はどうしたでしょうか? 前回同様、私はシニアかマスターに出ることができました。リベンジのため、いつものように仙台に、そしてシニアに参加することにしたんです。
予選ラウンドでは、6人から10人が1グループとなって3戦を行い、それぞれのグループで1位になった人が決勝ラウンドで戦うことができます。
予選ラウンドで私が使ったのは、前回と同じ、カリンのバンギラス/ゲンガー(e1)でした。
(※英訳者注:このデッキのことを覚えていない方は、大和さんの3番目の記事をどうぞ。ttp://60cards.net/blog/posts/detail/121)
なぜ前回と同じデッキを選んだんでしょうか? 答えは……ハーフデッキを練習する時間がなかったからです!!
運良く私は予選を1位で抜けることができました。ところでハッサムは? 事実、予選にもハッサムは多くいました。しかし私のデッキには、ハッサムに勝てるようなカードが何枚か入っていたんです。
ついに決勝トーナメントです! デッキは60枚になり、私はゲンガー(e1)/オーダイル(e1)を使うことにしました。
(※英訳者注:このデッキについても前回記事をどうぞ! ttp://60cards.net/blog/posts/detail/121)
前回の記事で書いたように、この2体のコンビネーションはすばらしく、ワザも非常に強力です。しかしどちらも2進化なので、立てるのに時間がかかります。時間切れで負けないように、かなり気をつける必要がありました。
また、このデッキを選んだ理由ですが、実はハッサムがメタ内デッキだとは知らなかったからなんです。それを知ったのは、知り合いのプレイヤーがハッサムの動きを見せてくれた当日の朝でした! 自分のデッキではハッサムに勝てないとわかったのですが、かといって他に上手く使えるデッキもありませんでした(デンリュウ/キュウコンも持っていましたが、調整できていませんでした。ハッサムには勝てても、優勝は難しそうでした)。それに、ゲンガー/オーダイルは使いたいデッキだったんです。ハッサムに勝てるヒントはないものかと、私はカードファイルを覗きました。すると、見つけたんです――ミュウ(e1)!
ハッサムがものすごく強いのはエネが大量についているときですが、一度エネが多くついてしまえば、ミュウのネオサイコウェーブで一気に持っていくことができます。あまりエネのついていないハッサムなら全く強くありません。そのため、ミュウを1枚加えたことで、ハッサムにはずいぶん勝ちやすくなりました。そういえば、私はよく大会直前になってデッキ内のカードを何枚か変えたりします。プレイヤーの多くはそれには反対だとわかってはいるのですが、自分ではいまだにそれが正しいと思っています。あのデッキに関しては、前回からはあまり中身を変えていなかったのですが、私の方のプレイスタイルはかなり変わっていました。以前は攻撃に移る前にまず場を整えようとしていましたが、今は攻撃を優先するようになっていたんです。
メタの解説はもう十分でしょう。対戦はどうなっていたのでしょうか? ハッサムとアンチハッサムデッキが勝ち上がっており、私はその両方とも対戦しましたし、そうでないデッキとも当たりました。
どんなデッキに対しても、私はオーダイルを立て、すぐ攻撃に移りました。たとえオーダイルが倒されて攻撃できないターンがあっても、相手がサイドを3枚以上取ればカオスムーブが使えるので、特に問題には思いませんでした。
ハッサムと対戦したとき、相手はハッサムに大量にエネルギーを貼ってきました。ハッサムにエネがたくさん付いてから、私はミュウを出しました。ハッサムはエネを捨てて逃げることもできたはずですが、ベンチのハッサムにはエネがついていませんでした。ハッサムが攻撃を選択すれば、すぐにミュウに倒されるはずです。
デッキにミュウは1枚だけでしたが、このゲームを勝つ上で大きなアドバンテージを与えてくれました。また、アンチハッサムデッキとも当たりましたが、相手は炎タイプなので、こちらのオーダイルが水タイプな以上は問題になりませんでした。どんな相手に対しても、勝つのに全く困難なことはありませんでした。前回負けたのが信じられないほどです! そうして私はリベンジを果たし、優勝することができました!
前回の大会のときは、このデッキの本当の強さに気づいていなかったんです。また私は、勝つためには完璧な場を作らなければいけないと誤解していましたし、その間に相手がどんな動きをしてくるかを予想するだけの力もありませんでした。今回勝てたのは、前回の敗北があったからだと思います。今回は、相手に十分なプレッシャーをかけ、そして時間消費にも気を配っていました。
プレイスキル以外の点で言えば、ぎりぎりになってデッキリストを変更したことが勝ちにつながりました。その段階でデッキを変更するのはかなりの冒険でした。しかしながら、そうするだけの度胸がなければ勝てていなかっただろうと今は確信しています(それでも、1枚変えただけでトップメタに勝てるようになったというのは、とても運が良かったと思います)。
仙台大会で優勝したことで、日本一決定戦への出場権を獲得できました。準備期間は1ヶ月以上あったため、私は懸命に研究しました。
次回の記事は、その日本一決定戦についてです。そこでは素晴らしい対戦と素晴らしい出会いがあり、私のポケカ人生でも深く思い出に残っている大会のひとつになりました。
また次回の記事でお会いしましょう!
◆ ◆ ◆ ◆ ◆
以上になります。お読みいただきありがとうございました。
繰り返しになりますが、訳文に問題があるとすれば、大和さんや魔女さんではなく責任は翻訳した僕にあります。間違いなどあれば遠慮なくご指摘ください。
今回の主役は、色々な意味でハッサム(e3)でしたね。ハッサムのカードはだいたい強いのですが、その中でも一、二を争う強さのハッサムです(exも強いしね)。命運を分けたのは直前のデッキ変更。そこでミュウにたどり着いてしまうところが、大和さんの大和さんたるゆえんなのかもしれません。
また、地味に重要なのが、プレイスタイルの見直しですね。場を作ればいいと思っていた動き方から、積極的に相手にプレッシャーをかけるプレイの方が重要だと気づいたことが、今回の優勝につながったと書かれています。
ポケカでは構築が重要視されがちですが、むしろ文章化されにくいプレイにこそ、順位を分ける秘訣があるのだと思います。
次回は日本一決定戦だそうで、これも楽しみです。
春の惜敗からのリベンジを期す大和さん。ゲンダイルを相棒に仙台大会へと臨みますが、そこにいたのは堅牢なハッサムの群れ。絶体絶命の状況の中、打開策を求めてカードファイルを覗くと、そこには……。
という、あらすじにしただけで既に面白い物語が今回のメインです。
e時代の懐かしいカードに浸りながら、ぜひ今回もお楽しみください。
いつもどおり、訳語の至らなさや誤訳の責任は、すべて僕うきにんに属します。
斜体は引用文です。読みやすさを考慮して、改行を変更した部分があります。
テキストの引用は前回同様ポケモンWikiさんからです。
(今回も例によって無許可翻訳なので、何かあればすぐに削除します)
◆ ◆ ◆ ◆ ◆
No.004 My Pokemoncard Life 2002
by Tsuguyoshi Yamato, trans. Majyo
Thursday, February 13, 2014
ttp://60cards.net/blog/posts/detail/126
読者のみなさん、こんにちは! チームアチャモの大和です!
これは私のポケカライフ記事で4番目にあたります。今回は、2002年の後半部分について書きたいと思います。
3番目の記事では、2001年夏の大会で3位になれたこと、その一方で、2002年春の大会では決勝トーナメントの初戦で負けてしまったことについて書きました。2年続けて仙台大会で優勝したいと願っていたにもかかわらず、それは叶わなかったわけです。それでも、その試合に負けたことは自分にとって大きな経験となりました。時間管理という、大事な教訓を学ぶことができたのですから。
学んだことに思いをめぐらせながら、私は2002年の夏にリベンジを期そうと準備していました。
使用可能カードの量自体には、あまり大きな変化はありませんでした。春以降は、eシリーズ第3弾しか発売されていなかったからです。eシリーズ初弾が出たのが2001年の12月で、次が2002年の3月、そして第3弾が出たのが2002年の5月です。ここで追加されたのは、わずか90枚のカードでした。しかしそれでも、現行のメタゲームを変えてしまうには十分だったんです。
(※英訳者注:これらの拡張パックを見直していて思い出したのですが、eシリーズは、日本では5弾まであるにもかかわらず、海外のたいていの場所では3弾までしかありません。原則として、Expeditionには日本でいうeシリーズ第1弾が入っています。Aquapolisには第2弾と第3弾、Skyridgeには第4弾と第5弾です。なので基本的には、当時の使用可能カードはAquapolisまでということになります)
当時のメタゲームで最も強かったカードのうちの1枚は、ハッサム(e3)でした。HPはそこまで高くありませんが、特殊鋼エネルギーがつくと、簡単には落ちなくなります。またレインボーエネルギーも、コインが必要とはいえヘビーメタルの打点を上げるのに大きく寄与していました。
また、オオタチ(e3)のたからさがしは、1ターンにあまり多くのカードをドローできなくても、鋼やレインボーエネルギーを簡単に探すことができました。
ハッサムにはもうひとつ強いワザがあり、ねらってつかむとプラスパワーを使えば、相手ベンチのベイビィポケモンを倒すことができました。ベンチのベイビィを攻撃するときは、コインを投げる必要はなかったんです!
ハッサムは他のどんな2進化よりも強く、強力なワザも2つありました。トップメタになるには十分な強さでした。その当時見られたほとんどのデッキは、ハッサムか、ハッサムアンチのデッキでした。
ところで、マルマイン(e2)のポケパワーを日本語で何と言うか、聞いたことがあるでしょうか? マルマインのポケパワーとシビビールのとくせいは、効果が違うにも関わらず、全く同じ名前なんです!
マルマインのエレキダイナモの効果はシビビールのとかなり似ているにもかかわらず、シビビールの方がずっと強いのですから、名前が同じというのはちょっと信じられませんね。それでも、新しいカードが古いカードを参照していると気づいたときは、非常に面白かったです。
では、大会ルールを見てみましょう。
前回同様、ジュニアとシニアはネオシリーズからeシリーズまで、マスターは一番最初の弾からeシリーズまででした。しかしこの大会は、昔のセットが使えた最後の大会となりました。
予選のデッキは30枚で、決勝トーナメントのデッキは60枚です。このルールは非常に長い期間にわたって用いられました。そしてまた、それぞれのリーグで優勝すれば、日本一決定戦に参加する権利を得ることができました。
ここからは、この当時のデッキを紹介させてください。
ハッサム(e3)/オオタチ(e3)
上のほうで説明したとおり、このデッキは当時のトップメタでした。オオタチのポケパワーで特殊エネルギーを引いてこれるため、鋼エネ4枚と虹エネ4枚をまとめて貼ってしまうこともそう難しくなかったんです。また、いったんハッサムに鋼エネが2、3枚ついてしまえば、デッキにはきずぐすりも入っているため、そう簡単には落ちなくなります。ヘビーメタルが特定の色エネを要求しないので、多少のサブアタッカーを選ぶ余地もありました。とはいえ、ハッサムの弱点が炎のため、たいていのプレイヤーはサブアタッカーに水ポケモンを選択していました。
デンリュウ(e1)/キュウコン(e1)
ハッサムを倒しやすいようにと、大きな打点を出せるデッキもありました。このデッキは、そのうちの代表的なものです。
キュウコンのよみのほのおがメインアタッカーですが、ついていたエネルギーをすべてトラッシュしてしまうため、デンリュウがサポート役としてデッキに入っています。
デンリュウのポケパワーのエナジーコネクトで、キュウコンが途切れずに攻撃できるようになっていました。
R団のバンギラス(VS)/超エネルギーリムーブetc
(※英訳者注:R団のバンギラスはVSシリーズのカードで、このカードは日本でしかリリースされていません。VSシリーズには特別なテーマデッキがあり、トロピカルメガバトルでは使うことができました。このデッキはもともと日本で映画の『セレビィ』のためにスペシャルテーマデッキとして作られたもので、そのなかにR団のバンギラスが入っていました。トロピカルメガバトルでは、このデッキはそれぞれの国の代表の言葉ごとに作られましたが、カードは非公式カードとして扱われたうえ、それらの中にはR団のバンギラスは入っておらず、代わりにトロピカルウィンドが入っていました。
ちなみにR団のバンギラス自体はシークレットカードとして扱われていたにもかかわらず、拡張パックからは手に入れることができませんでした)
さて、R団のバンギラスのワザを見てみましょう。
悪 デストロイビーム大ダメージを与える代わりに、このデッキはエネルギーを剥がすことでハッサムを止めようとします。R団のバンギラスのデストロイビームとエネルギーリムーブを使えば、ハッサムについているエネルギーを剥がすことができます。さきほど書いたとおり、ハッサムについているエネルギーはたいてい特殊鋼かレインボーです。ほとんどのデッキには特殊エネを場に戻す手段がないので、いったん特殊エネがトラッシュされてしまうと、ハッサムは倒されやすくなると同時に、大きな打点も出せなくなります。
コインを1回投げ、「おもて」なら、相手についている「エネルギーカード」を、1枚トラッシュする。
無無無 たたきつける 30×
コインを2回投げ、「おもて」の数×30ダメージ。
超エネルギーリムーブ2やデストロイビームで一度表が出てしまえば、ハッサムの攻撃と防御をくい止めるのはそう難しくはありません。とはいえ、悪タイプで大きな打点を出せるポケモンがいなかったため、このデッキは完全にアンチハッサムデッキとなっていました。
さて私はどうしたでしょうか? 前回同様、私はシニアかマスターに出ることができました。リベンジのため、いつものように仙台に、そしてシニアに参加することにしたんです。
予選ラウンドでは、6人から10人が1グループとなって3戦を行い、それぞれのグループで1位になった人が決勝ラウンドで戦うことができます。
予選ラウンドで私が使ったのは、前回と同じ、カリンのバンギラス/ゲンガー(e1)でした。
(※英訳者注:このデッキのことを覚えていない方は、大和さんの3番目の記事をどうぞ。ttp://60cards.net/blog/posts/detail/121)
なぜ前回と同じデッキを選んだんでしょうか? 答えは……ハーフデッキを練習する時間がなかったからです!!
運良く私は予選を1位で抜けることができました。ところでハッサムは? 事実、予選にもハッサムは多くいました。しかし私のデッキには、ハッサムに勝てるようなカードが何枚か入っていたんです。
ついに決勝トーナメントです! デッキは60枚になり、私はゲンガー(e1)/オーダイル(e1)を使うことにしました。
(※英訳者注:このデッキについても前回記事をどうぞ! ttp://60cards.net/blog/posts/detail/121)
前回の記事で書いたように、この2体のコンビネーションはすばらしく、ワザも非常に強力です。しかしどちらも2進化なので、立てるのに時間がかかります。時間切れで負けないように、かなり気をつける必要がありました。
また、このデッキを選んだ理由ですが、実はハッサムがメタ内デッキだとは知らなかったからなんです。それを知ったのは、知り合いのプレイヤーがハッサムの動きを見せてくれた当日の朝でした! 自分のデッキではハッサムに勝てないとわかったのですが、かといって他に上手く使えるデッキもありませんでした(デンリュウ/キュウコンも持っていましたが、調整できていませんでした。ハッサムには勝てても、優勝は難しそうでした)。それに、ゲンガー/オーダイルは使いたいデッキだったんです。ハッサムに勝てるヒントはないものかと、私はカードファイルを覗きました。すると、見つけたんです――ミュウ(e1)!
ハッサムがものすごく強いのはエネが大量についているときですが、一度エネが多くついてしまえば、ミュウのネオサイコウェーブで一気に持っていくことができます。あまりエネのついていないハッサムなら全く強くありません。そのため、ミュウを1枚加えたことで、ハッサムにはずいぶん勝ちやすくなりました。そういえば、私はよく大会直前になってデッキ内のカードを何枚か変えたりします。プレイヤーの多くはそれには反対だとわかってはいるのですが、自分ではいまだにそれが正しいと思っています。あのデッキに関しては、前回からはあまり中身を変えていなかったのですが、私の方のプレイスタイルはかなり変わっていました。以前は攻撃に移る前にまず場を整えようとしていましたが、今は攻撃を優先するようになっていたんです。
メタの解説はもう十分でしょう。対戦はどうなっていたのでしょうか? ハッサムとアンチハッサムデッキが勝ち上がっており、私はその両方とも対戦しましたし、そうでないデッキとも当たりました。
どんなデッキに対しても、私はオーダイルを立て、すぐ攻撃に移りました。たとえオーダイルが倒されて攻撃できないターンがあっても、相手がサイドを3枚以上取ればカオスムーブが使えるので、特に問題には思いませんでした。
ハッサムと対戦したとき、相手はハッサムに大量にエネルギーを貼ってきました。ハッサムにエネがたくさん付いてから、私はミュウを出しました。ハッサムはエネを捨てて逃げることもできたはずですが、ベンチのハッサムにはエネがついていませんでした。ハッサムが攻撃を選択すれば、すぐにミュウに倒されるはずです。
デッキにミュウは1枚だけでしたが、このゲームを勝つ上で大きなアドバンテージを与えてくれました。また、アンチハッサムデッキとも当たりましたが、相手は炎タイプなので、こちらのオーダイルが水タイプな以上は問題になりませんでした。どんな相手に対しても、勝つのに全く困難なことはありませんでした。前回負けたのが信じられないほどです! そうして私はリベンジを果たし、優勝することができました!
前回の大会のときは、このデッキの本当の強さに気づいていなかったんです。また私は、勝つためには完璧な場を作らなければいけないと誤解していましたし、その間に相手がどんな動きをしてくるかを予想するだけの力もありませんでした。今回勝てたのは、前回の敗北があったからだと思います。今回は、相手に十分なプレッシャーをかけ、そして時間消費にも気を配っていました。
プレイスキル以外の点で言えば、ぎりぎりになってデッキリストを変更したことが勝ちにつながりました。その段階でデッキを変更するのはかなりの冒険でした。しかしながら、そうするだけの度胸がなければ勝てていなかっただろうと今は確信しています(それでも、1枚変えただけでトップメタに勝てるようになったというのは、とても運が良かったと思います)。
仙台大会で優勝したことで、日本一決定戦への出場権を獲得できました。準備期間は1ヶ月以上あったため、私は懸命に研究しました。
次回の記事は、その日本一決定戦についてです。そこでは素晴らしい対戦と素晴らしい出会いがあり、私のポケカ人生でも深く思い出に残っている大会のひとつになりました。
また次回の記事でお会いしましょう!
◆ ◆ ◆ ◆ ◆
以上になります。お読みいただきありがとうございました。
繰り返しになりますが、訳文に問題があるとすれば、大和さんや魔女さんではなく責任は翻訳した僕にあります。間違いなどあれば遠慮なくご指摘ください。
今回の主役は、色々な意味でハッサム(e3)でしたね。ハッサムのカードはだいたい強いのですが、その中でも一、二を争う強さのハッサムです(exも強いしね)。命運を分けたのは直前のデッキ変更。そこでミュウにたどり着いてしまうところが、大和さんの大和さんたるゆえんなのかもしれません。
また、地味に重要なのが、プレイスタイルの見直しですね。場を作ればいいと思っていた動き方から、積極的に相手にプレッシャーをかけるプレイの方が重要だと気づいたことが、今回の優勝につながったと書かれています。
ポケカでは構築が重要視されがちですが、むしろ文章化されにくいプレイにこそ、順位を分ける秘訣があるのだと思います。
次回は日本一決定戦だそうで、これも楽しみです。
いよいよ日曜日は北海道のポケモン竜王戦本番です。ジュニアたち&お父さんお母さんは頑張ってください!
当のうきにんさんは枠問題により入場できるかどうかハラハラです。が、カード貸し出しキモヲタお兄さんとして会場までは行く予定です。
レンタル希望カードがあれば、当日でもメールでもコメントでも、言って下さればいくらでもお貸しします。最近やたら高価になってしまったグッズ系もだいたい揃ってます。
当日はうまい具合に保護者枠で観戦できれば一番なのですが……会場に入れなかったらカードだけ貸して、そのまま昼の街に消える予定です。会場の立地だけは抜群だしね。
問題は大会の開始時間というか選手集合時間がわかっていないことです。まさかの会場一番乗りパターンか。
当のうきにんさんは枠問題により入場できるかどうかハラハラです。が、カード貸し出し
レンタル希望カードがあれば、当日でもメールでもコメントでも、言って下さればいくらでもお貸しします。最近やたら高価になってしまったグッズ系もだいたい揃ってます。
当日はうまい具合に保護者枠で観戦できれば一番なのですが……会場に入れなかったらカードだけ貸して、そのまま昼の街に消える予定です。会場の立地だけは抜群だしね。
問題は大会の開始時間というか選手集合時間がわかっていないことです。まさかの会場一番乗りパターンか。
竜王戦北海道大会!とうきにん
2014年2月23日コメント (10)
感じたことや掛けたい言葉はとにかくたくさんあるのですが、かなこぉ↑↑ちゃんとガウくん代表獲得おめでとう!
知り合い同士の潰し合いが残酷なぐらい多く生じている中で、地元北海道のプレイヤーが権利を取ってくれて本当に嬉しいです。2人とも長いあいだうきにん杯(SIP杯)に参加してくれているというのも嬉しすぎることです。
また、惜しくも届かなかったジュニアたちも本当にがんばったと思います。
相性の悪いマッチアップ、不運な事故、色々あったはずです。それでも、決勝戦のモニタをみんな一心に見つめている様子は、北海道ジュニア始まってるな、と 心の底から思った瞬間でした。
画像は本日のハイライト。レッドカーペットを闊歩する北海道代表にひれ伏す大きなお兄ちゃん2人。
知り合い同士の潰し合いが残酷なぐらい多く生じている中で、地元北海道のプレイヤーが権利を取ってくれて本当に嬉しいです。2人とも長いあいだうきにん杯(SIP杯)に参加してくれているというのも嬉しすぎることです。
また、惜しくも届かなかったジュニアたちも本当にがんばったと思います。
相性の悪いマッチアップ、不運な事故、色々あったはずです。それでも、決勝戦のモニタをみんな一心に見つめている様子は、北海道ジュニア始まってるな、と 心の底から思った瞬間でした。
画像は本日のハイライト。レッドカーペットを闊歩する北海道代表にひれ伏す大きなお兄ちゃん2人。