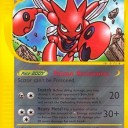【翻訳】No.004:私のポケカライフ2002
2014年2月19日
今回は60cards.netから。大和さんの記事第4弾の翻訳になります。
春の惜敗からのリベンジを期す大和さん。ゲンダイルを相棒に仙台大会へと臨みますが、そこにいたのは堅牢なハッサムの群れ。絶体絶命の状況の中、打開策を求めてカードファイルを覗くと、そこには……。
という、あらすじにしただけで既に面白い物語が今回のメインです。
e時代の懐かしいカードに浸りながら、ぜひ今回もお楽しみください。
いつもどおり、訳語の至らなさや誤訳の責任は、すべて僕うきにんに属します。
斜体は引用文です。読みやすさを考慮して、改行を変更した部分があります。
テキストの引用は前回同様ポケモンWikiさんからです。
(今回も例によって無許可翻訳なので、何かあればすぐに削除します)
◆ ◆ ◆ ◆ ◆
No.004 My Pokemoncard Life 2002
by Tsuguyoshi Yamato, trans. Majyo
Thursday, February 13, 2014
ttp://60cards.net/blog/posts/detail/126
読者のみなさん、こんにちは! チームアチャモの大和です!
これは私のポケカライフ記事で4番目にあたります。今回は、2002年の後半部分について書きたいと思います。
3番目の記事では、2001年夏の大会で3位になれたこと、その一方で、2002年春の大会では決勝トーナメントの初戦で負けてしまったことについて書きました。2年続けて仙台大会で優勝したいと願っていたにもかかわらず、それは叶わなかったわけです。それでも、その試合に負けたことは自分にとって大きな経験となりました。時間管理という、大事な教訓を学ぶことができたのですから。
学んだことに思いをめぐらせながら、私は2002年の夏にリベンジを期そうと準備していました。
使用可能カードの量自体には、あまり大きな変化はありませんでした。春以降は、eシリーズ第3弾しか発売されていなかったからです。eシリーズ初弾が出たのが2001年の12月で、次が2002年の3月、そして第3弾が出たのが2002年の5月です。ここで追加されたのは、わずか90枚のカードでした。しかしそれでも、現行のメタゲームを変えてしまうには十分だったんです。
(※英訳者注:これらの拡張パックを見直していて思い出したのですが、eシリーズは、日本では5弾まであるにもかかわらず、海外のたいていの場所では3弾までしかありません。原則として、Expeditionには日本でいうeシリーズ第1弾が入っています。Aquapolisには第2弾と第3弾、Skyridgeには第4弾と第5弾です。なので基本的には、当時の使用可能カードはAquapolisまでということになります)
当時のメタゲームで最も強かったカードのうちの1枚は、ハッサム(e3)でした。HPはそこまで高くありませんが、特殊鋼エネルギーがつくと、簡単には落ちなくなります。またレインボーエネルギーも、コインが必要とはいえヘビーメタルの打点を上げるのに大きく寄与していました。
また、オオタチ(e3)のたからさがしは、1ターンにあまり多くのカードをドローできなくても、鋼やレインボーエネルギーを簡単に探すことができました。
ハッサムにはもうひとつ強いワザがあり、ねらってつかむとプラスパワーを使えば、相手ベンチのベイビィポケモンを倒すことができました。ベンチのベイビィを攻撃するときは、コインを投げる必要はなかったんです!
ハッサムは他のどんな2進化よりも強く、強力なワザも2つありました。トップメタになるには十分な強さでした。その当時見られたほとんどのデッキは、ハッサムか、ハッサムアンチのデッキでした。
ところで、マルマイン(e2)のポケパワーを日本語で何と言うか、聞いたことがあるでしょうか? マルマインのポケパワーとシビビールのとくせいは、効果が違うにも関わらず、全く同じ名前なんです!
マルマインのエレキダイナモの効果はシビビールのとかなり似ているにもかかわらず、シビビールの方がずっと強いのですから、名前が同じというのはちょっと信じられませんね。それでも、新しいカードが古いカードを参照していると気づいたときは、非常に面白かったです。
では、大会ルールを見てみましょう。
前回同様、ジュニアとシニアはネオシリーズからeシリーズまで、マスターは一番最初の弾からeシリーズまででした。しかしこの大会は、昔のセットが使えた最後の大会となりました。
予選のデッキは30枚で、決勝トーナメントのデッキは60枚です。このルールは非常に長い期間にわたって用いられました。そしてまた、それぞれのリーグで優勝すれば、日本一決定戦に参加する権利を得ることができました。
ここからは、この当時のデッキを紹介させてください。
ハッサム(e3)/オオタチ(e3)
上のほうで説明したとおり、このデッキは当時のトップメタでした。オオタチのポケパワーで特殊エネルギーを引いてこれるため、鋼エネ4枚と虹エネ4枚をまとめて貼ってしまうこともそう難しくなかったんです。また、いったんハッサムに鋼エネが2、3枚ついてしまえば、デッキにはきずぐすりも入っているため、そう簡単には落ちなくなります。ヘビーメタルが特定の色エネを要求しないので、多少のサブアタッカーを選ぶ余地もありました。とはいえ、ハッサムの弱点が炎のため、たいていのプレイヤーはサブアタッカーに水ポケモンを選択していました。
デンリュウ(e1)/キュウコン(e1)
ハッサムを倒しやすいようにと、大きな打点を出せるデッキもありました。このデッキは、そのうちの代表的なものです。
キュウコンのよみのほのおがメインアタッカーですが、ついていたエネルギーをすべてトラッシュしてしまうため、デンリュウがサポート役としてデッキに入っています。
デンリュウのポケパワーのエナジーコネクトで、キュウコンが途切れずに攻撃できるようになっていました。
R団のバンギラス(VS)/超エネルギーリムーブetc
(※英訳者注:R団のバンギラスはVSシリーズのカードで、このカードは日本でしかリリースされていません。VSシリーズには特別なテーマデッキがあり、トロピカルメガバトルでは使うことができました。このデッキはもともと日本で映画の『セレビィ』のためにスペシャルテーマデッキとして作られたもので、そのなかにR団のバンギラスが入っていました。トロピカルメガバトルでは、このデッキはそれぞれの国の代表の言葉ごとに作られましたが、カードは非公式カードとして扱われたうえ、それらの中にはR団のバンギラスは入っておらず、代わりにトロピカルウィンドが入っていました。
ちなみにR団のバンギラス自体はシークレットカードとして扱われていたにもかかわらず、拡張パックからは手に入れることができませんでした)
さて、R団のバンギラスのワザを見てみましょう。
超エネルギーリムーブ2やデストロイビームで一度表が出てしまえば、ハッサムの攻撃と防御をくい止めるのはそう難しくはありません。とはいえ、悪タイプで大きな打点を出せるポケモンがいなかったため、このデッキは完全にアンチハッサムデッキとなっていました。
さて私はどうしたでしょうか? 前回同様、私はシニアかマスターに出ることができました。リベンジのため、いつものように仙台に、そしてシニアに参加することにしたんです。
予選ラウンドでは、6人から10人が1グループとなって3戦を行い、それぞれのグループで1位になった人が決勝ラウンドで戦うことができます。
予選ラウンドで私が使ったのは、前回と同じ、カリンのバンギラス/ゲンガー(e1)でした。
(※英訳者注:このデッキのことを覚えていない方は、大和さんの3番目の記事をどうぞ。ttp://60cards.net/blog/posts/detail/121)
なぜ前回と同じデッキを選んだんでしょうか? 答えは……ハーフデッキを練習する時間がなかったからです!!
運良く私は予選を1位で抜けることができました。ところでハッサムは? 事実、予選にもハッサムは多くいました。しかし私のデッキには、ハッサムに勝てるようなカードが何枚か入っていたんです。
ついに決勝トーナメントです! デッキは60枚になり、私はゲンガー(e1)/オーダイル(e1)を使うことにしました。
(※英訳者注:このデッキについても前回記事をどうぞ! ttp://60cards.net/blog/posts/detail/121)
前回の記事で書いたように、この2体のコンビネーションはすばらしく、ワザも非常に強力です。しかしどちらも2進化なので、立てるのに時間がかかります。時間切れで負けないように、かなり気をつける必要がありました。
また、このデッキを選んだ理由ですが、実はハッサムがメタ内デッキだとは知らなかったからなんです。それを知ったのは、知り合いのプレイヤーがハッサムの動きを見せてくれた当日の朝でした! 自分のデッキではハッサムに勝てないとわかったのですが、かといって他に上手く使えるデッキもありませんでした(デンリュウ/キュウコンも持っていましたが、調整できていませんでした。ハッサムには勝てても、優勝は難しそうでした)。それに、ゲンガー/オーダイルは使いたいデッキだったんです。ハッサムに勝てるヒントはないものかと、私はカードファイルを覗きました。すると、見つけたんです――ミュウ(e1)!
ハッサムがものすごく強いのはエネが大量についているときですが、一度エネが多くついてしまえば、ミュウのネオサイコウェーブで一気に持っていくことができます。あまりエネのついていないハッサムなら全く強くありません。そのため、ミュウを1枚加えたことで、ハッサムにはずいぶん勝ちやすくなりました。そういえば、私はよく大会直前になってデッキ内のカードを何枚か変えたりします。プレイヤーの多くはそれには反対だとわかってはいるのですが、自分ではいまだにそれが正しいと思っています。あのデッキに関しては、前回からはあまり中身を変えていなかったのですが、私の方のプレイスタイルはかなり変わっていました。以前は攻撃に移る前にまず場を整えようとしていましたが、今は攻撃を優先するようになっていたんです。
メタの解説はもう十分でしょう。対戦はどうなっていたのでしょうか? ハッサムとアンチハッサムデッキが勝ち上がっており、私はその両方とも対戦しましたし、そうでないデッキとも当たりました。
どんなデッキに対しても、私はオーダイルを立て、すぐ攻撃に移りました。たとえオーダイルが倒されて攻撃できないターンがあっても、相手がサイドを3枚以上取ればカオスムーブが使えるので、特に問題には思いませんでした。
ハッサムと対戦したとき、相手はハッサムに大量にエネルギーを貼ってきました。ハッサムにエネがたくさん付いてから、私はミュウを出しました。ハッサムはエネを捨てて逃げることもできたはずですが、ベンチのハッサムにはエネがついていませんでした。ハッサムが攻撃を選択すれば、すぐにミュウに倒されるはずです。
デッキにミュウは1枚だけでしたが、このゲームを勝つ上で大きなアドバンテージを与えてくれました。また、アンチハッサムデッキとも当たりましたが、相手は炎タイプなので、こちらのオーダイルが水タイプな以上は問題になりませんでした。どんな相手に対しても、勝つのに全く困難なことはありませんでした。前回負けたのが信じられないほどです! そうして私はリベンジを果たし、優勝することができました!
前回の大会のときは、このデッキの本当の強さに気づいていなかったんです。また私は、勝つためには完璧な場を作らなければいけないと誤解していましたし、その間に相手がどんな動きをしてくるかを予想するだけの力もありませんでした。今回勝てたのは、前回の敗北があったからだと思います。今回は、相手に十分なプレッシャーをかけ、そして時間消費にも気を配っていました。
プレイスキル以外の点で言えば、ぎりぎりになってデッキリストを変更したことが勝ちにつながりました。その段階でデッキを変更するのはかなりの冒険でした。しかしながら、そうするだけの度胸がなければ勝てていなかっただろうと今は確信しています(それでも、1枚変えただけでトップメタに勝てるようになったというのは、とても運が良かったと思います)。
仙台大会で優勝したことで、日本一決定戦への出場権を獲得できました。準備期間は1ヶ月以上あったため、私は懸命に研究しました。
次回の記事は、その日本一決定戦についてです。そこでは素晴らしい対戦と素晴らしい出会いがあり、私のポケカ人生でも深く思い出に残っている大会のひとつになりました。
また次回の記事でお会いしましょう!
◆ ◆ ◆ ◆ ◆
以上になります。お読みいただきありがとうございました。
繰り返しになりますが、訳文に問題があるとすれば、大和さんや魔女さんではなく責任は翻訳した僕にあります。間違いなどあれば遠慮なくご指摘ください。
今回の主役は、色々な意味でハッサム(e3)でしたね。ハッサムのカードはだいたい強いのですが、その中でも一、二を争う強さのハッサムです(exも強いしね)。命運を分けたのは直前のデッキ変更。そこでミュウにたどり着いてしまうところが、大和さんの大和さんたるゆえんなのかもしれません。
また、地味に重要なのが、プレイスタイルの見直しですね。場を作ればいいと思っていた動き方から、積極的に相手にプレッシャーをかけるプレイの方が重要だと気づいたことが、今回の優勝につながったと書かれています。
ポケカでは構築が重要視されがちですが、むしろ文章化されにくいプレイにこそ、順位を分ける秘訣があるのだと思います。
次回は日本一決定戦だそうで、これも楽しみです。
春の惜敗からのリベンジを期す大和さん。ゲンダイルを相棒に仙台大会へと臨みますが、そこにいたのは堅牢なハッサムの群れ。絶体絶命の状況の中、打開策を求めてカードファイルを覗くと、そこには……。
という、あらすじにしただけで既に面白い物語が今回のメインです。
e時代の懐かしいカードに浸りながら、ぜひ今回もお楽しみください。
いつもどおり、訳語の至らなさや誤訳の責任は、すべて僕うきにんに属します。
斜体は引用文です。読みやすさを考慮して、改行を変更した部分があります。
テキストの引用は前回同様ポケモンWikiさんからです。
(今回も例によって無許可翻訳なので、何かあればすぐに削除します)
◆ ◆ ◆ ◆ ◆
No.004 My Pokemoncard Life 2002
by Tsuguyoshi Yamato, trans. Majyo
Thursday, February 13, 2014
ttp://60cards.net/blog/posts/detail/126
読者のみなさん、こんにちは! チームアチャモの大和です!
これは私のポケカライフ記事で4番目にあたります。今回は、2002年の後半部分について書きたいと思います。
3番目の記事では、2001年夏の大会で3位になれたこと、その一方で、2002年春の大会では決勝トーナメントの初戦で負けてしまったことについて書きました。2年続けて仙台大会で優勝したいと願っていたにもかかわらず、それは叶わなかったわけです。それでも、その試合に負けたことは自分にとって大きな経験となりました。時間管理という、大事な教訓を学ぶことができたのですから。
学んだことに思いをめぐらせながら、私は2002年の夏にリベンジを期そうと準備していました。
使用可能カードの量自体には、あまり大きな変化はありませんでした。春以降は、eシリーズ第3弾しか発売されていなかったからです。eシリーズ初弾が出たのが2001年の12月で、次が2002年の3月、そして第3弾が出たのが2002年の5月です。ここで追加されたのは、わずか90枚のカードでした。しかしそれでも、現行のメタゲームを変えてしまうには十分だったんです。
(※英訳者注:これらの拡張パックを見直していて思い出したのですが、eシリーズは、日本では5弾まであるにもかかわらず、海外のたいていの場所では3弾までしかありません。原則として、Expeditionには日本でいうeシリーズ第1弾が入っています。Aquapolisには第2弾と第3弾、Skyridgeには第4弾と第5弾です。なので基本的には、当時の使用可能カードはAquapolisまでということになります)
当時のメタゲームで最も強かったカードのうちの1枚は、ハッサム(e3)でした。HPはそこまで高くありませんが、特殊鋼エネルギーがつくと、簡単には落ちなくなります。またレインボーエネルギーも、コインが必要とはいえヘビーメタルの打点を上げるのに大きく寄与していました。
また、オオタチ(e3)のたからさがしは、1ターンにあまり多くのカードをドローできなくても、鋼やレインボーエネルギーを簡単に探すことができました。
ハッサムにはもうひとつ強いワザがあり、ねらってつかむとプラスパワーを使えば、相手ベンチのベイビィポケモンを倒すことができました。ベンチのベイビィを攻撃するときは、コインを投げる必要はなかったんです!
ハッサムは他のどんな2進化よりも強く、強力なワザも2つありました。トップメタになるには十分な強さでした。その当時見られたほとんどのデッキは、ハッサムか、ハッサムアンチのデッキでした。
ところで、マルマイン(e2)のポケパワーを日本語で何と言うか、聞いたことがあるでしょうか? マルマインのポケパワーとシビビールのとくせいは、効果が違うにも関わらず、全く同じ名前なんです!
マルマインのエレキダイナモの効果はシビビールのとかなり似ているにもかかわらず、シビビールの方がずっと強いのですから、名前が同じというのはちょっと信じられませんね。それでも、新しいカードが古いカードを参照していると気づいたときは、非常に面白かったです。
では、大会ルールを見てみましょう。
前回同様、ジュニアとシニアはネオシリーズからeシリーズまで、マスターは一番最初の弾からeシリーズまででした。しかしこの大会は、昔のセットが使えた最後の大会となりました。
予選のデッキは30枚で、決勝トーナメントのデッキは60枚です。このルールは非常に長い期間にわたって用いられました。そしてまた、それぞれのリーグで優勝すれば、日本一決定戦に参加する権利を得ることができました。
ここからは、この当時のデッキを紹介させてください。
ハッサム(e3)/オオタチ(e3)
上のほうで説明したとおり、このデッキは当時のトップメタでした。オオタチのポケパワーで特殊エネルギーを引いてこれるため、鋼エネ4枚と虹エネ4枚をまとめて貼ってしまうこともそう難しくなかったんです。また、いったんハッサムに鋼エネが2、3枚ついてしまえば、デッキにはきずぐすりも入っているため、そう簡単には落ちなくなります。ヘビーメタルが特定の色エネを要求しないので、多少のサブアタッカーを選ぶ余地もありました。とはいえ、ハッサムの弱点が炎のため、たいていのプレイヤーはサブアタッカーに水ポケモンを選択していました。
デンリュウ(e1)/キュウコン(e1)
ハッサムを倒しやすいようにと、大きな打点を出せるデッキもありました。このデッキは、そのうちの代表的なものです。
キュウコンのよみのほのおがメインアタッカーですが、ついていたエネルギーをすべてトラッシュしてしまうため、デンリュウがサポート役としてデッキに入っています。
デンリュウのポケパワーのエナジーコネクトで、キュウコンが途切れずに攻撃できるようになっていました。
R団のバンギラス(VS)/超エネルギーリムーブetc
(※英訳者注:R団のバンギラスはVSシリーズのカードで、このカードは日本でしかリリースされていません。VSシリーズには特別なテーマデッキがあり、トロピカルメガバトルでは使うことができました。このデッキはもともと日本で映画の『セレビィ』のためにスペシャルテーマデッキとして作られたもので、そのなかにR団のバンギラスが入っていました。トロピカルメガバトルでは、このデッキはそれぞれの国の代表の言葉ごとに作られましたが、カードは非公式カードとして扱われたうえ、それらの中にはR団のバンギラスは入っておらず、代わりにトロピカルウィンドが入っていました。
ちなみにR団のバンギラス自体はシークレットカードとして扱われていたにもかかわらず、拡張パックからは手に入れることができませんでした)
さて、R団のバンギラスのワザを見てみましょう。
悪 デストロイビーム大ダメージを与える代わりに、このデッキはエネルギーを剥がすことでハッサムを止めようとします。R団のバンギラスのデストロイビームとエネルギーリムーブを使えば、ハッサムについているエネルギーを剥がすことができます。さきほど書いたとおり、ハッサムについているエネルギーはたいてい特殊鋼かレインボーです。ほとんどのデッキには特殊エネを場に戻す手段がないので、いったん特殊エネがトラッシュされてしまうと、ハッサムは倒されやすくなると同時に、大きな打点も出せなくなります。
コインを1回投げ、「おもて」なら、相手についている「エネルギーカード」を、1枚トラッシュする。
無無無 たたきつける 30×
コインを2回投げ、「おもて」の数×30ダメージ。
超エネルギーリムーブ2やデストロイビームで一度表が出てしまえば、ハッサムの攻撃と防御をくい止めるのはそう難しくはありません。とはいえ、悪タイプで大きな打点を出せるポケモンがいなかったため、このデッキは完全にアンチハッサムデッキとなっていました。
さて私はどうしたでしょうか? 前回同様、私はシニアかマスターに出ることができました。リベンジのため、いつものように仙台に、そしてシニアに参加することにしたんです。
予選ラウンドでは、6人から10人が1グループとなって3戦を行い、それぞれのグループで1位になった人が決勝ラウンドで戦うことができます。
予選ラウンドで私が使ったのは、前回と同じ、カリンのバンギラス/ゲンガー(e1)でした。
(※英訳者注:このデッキのことを覚えていない方は、大和さんの3番目の記事をどうぞ。ttp://60cards.net/blog/posts/detail/121)
なぜ前回と同じデッキを選んだんでしょうか? 答えは……ハーフデッキを練習する時間がなかったからです!!
運良く私は予選を1位で抜けることができました。ところでハッサムは? 事実、予選にもハッサムは多くいました。しかし私のデッキには、ハッサムに勝てるようなカードが何枚か入っていたんです。
ついに決勝トーナメントです! デッキは60枚になり、私はゲンガー(e1)/オーダイル(e1)を使うことにしました。
(※英訳者注:このデッキについても前回記事をどうぞ! ttp://60cards.net/blog/posts/detail/121)
前回の記事で書いたように、この2体のコンビネーションはすばらしく、ワザも非常に強力です。しかしどちらも2進化なので、立てるのに時間がかかります。時間切れで負けないように、かなり気をつける必要がありました。
また、このデッキを選んだ理由ですが、実はハッサムがメタ内デッキだとは知らなかったからなんです。それを知ったのは、知り合いのプレイヤーがハッサムの動きを見せてくれた当日の朝でした! 自分のデッキではハッサムに勝てないとわかったのですが、かといって他に上手く使えるデッキもありませんでした(デンリュウ/キュウコンも持っていましたが、調整できていませんでした。ハッサムには勝てても、優勝は難しそうでした)。それに、ゲンガー/オーダイルは使いたいデッキだったんです。ハッサムに勝てるヒントはないものかと、私はカードファイルを覗きました。すると、見つけたんです――ミュウ(e1)!
ハッサムがものすごく強いのはエネが大量についているときですが、一度エネが多くついてしまえば、ミュウのネオサイコウェーブで一気に持っていくことができます。あまりエネのついていないハッサムなら全く強くありません。そのため、ミュウを1枚加えたことで、ハッサムにはずいぶん勝ちやすくなりました。そういえば、私はよく大会直前になってデッキ内のカードを何枚か変えたりします。プレイヤーの多くはそれには反対だとわかってはいるのですが、自分ではいまだにそれが正しいと思っています。あのデッキに関しては、前回からはあまり中身を変えていなかったのですが、私の方のプレイスタイルはかなり変わっていました。以前は攻撃に移る前にまず場を整えようとしていましたが、今は攻撃を優先するようになっていたんです。
メタの解説はもう十分でしょう。対戦はどうなっていたのでしょうか? ハッサムとアンチハッサムデッキが勝ち上がっており、私はその両方とも対戦しましたし、そうでないデッキとも当たりました。
どんなデッキに対しても、私はオーダイルを立て、すぐ攻撃に移りました。たとえオーダイルが倒されて攻撃できないターンがあっても、相手がサイドを3枚以上取ればカオスムーブが使えるので、特に問題には思いませんでした。
ハッサムと対戦したとき、相手はハッサムに大量にエネルギーを貼ってきました。ハッサムにエネがたくさん付いてから、私はミュウを出しました。ハッサムはエネを捨てて逃げることもできたはずですが、ベンチのハッサムにはエネがついていませんでした。ハッサムが攻撃を選択すれば、すぐにミュウに倒されるはずです。
デッキにミュウは1枚だけでしたが、このゲームを勝つ上で大きなアドバンテージを与えてくれました。また、アンチハッサムデッキとも当たりましたが、相手は炎タイプなので、こちらのオーダイルが水タイプな以上は問題になりませんでした。どんな相手に対しても、勝つのに全く困難なことはありませんでした。前回負けたのが信じられないほどです! そうして私はリベンジを果たし、優勝することができました!
前回の大会のときは、このデッキの本当の強さに気づいていなかったんです。また私は、勝つためには完璧な場を作らなければいけないと誤解していましたし、その間に相手がどんな動きをしてくるかを予想するだけの力もありませんでした。今回勝てたのは、前回の敗北があったからだと思います。今回は、相手に十分なプレッシャーをかけ、そして時間消費にも気を配っていました。
プレイスキル以外の点で言えば、ぎりぎりになってデッキリストを変更したことが勝ちにつながりました。その段階でデッキを変更するのはかなりの冒険でした。しかしながら、そうするだけの度胸がなければ勝てていなかっただろうと今は確信しています(それでも、1枚変えただけでトップメタに勝てるようになったというのは、とても運が良かったと思います)。
仙台大会で優勝したことで、日本一決定戦への出場権を獲得できました。準備期間は1ヶ月以上あったため、私は懸命に研究しました。
次回の記事は、その日本一決定戦についてです。そこでは素晴らしい対戦と素晴らしい出会いがあり、私のポケカ人生でも深く思い出に残っている大会のひとつになりました。
また次回の記事でお会いしましょう!
◆ ◆ ◆ ◆ ◆
以上になります。お読みいただきありがとうございました。
繰り返しになりますが、訳文に問題があるとすれば、大和さんや魔女さんではなく責任は翻訳した僕にあります。間違いなどあれば遠慮なくご指摘ください。
今回の主役は、色々な意味でハッサム(e3)でしたね。ハッサムのカードはだいたい強いのですが、その中でも一、二を争う強さのハッサムです(exも強いしね)。命運を分けたのは直前のデッキ変更。そこでミュウにたどり着いてしまうところが、大和さんの大和さんたるゆえんなのかもしれません。
また、地味に重要なのが、プレイスタイルの見直しですね。場を作ればいいと思っていた動き方から、積極的に相手にプレッシャーをかけるプレイの方が重要だと気づいたことが、今回の優勝につながったと書かれています。
ポケカでは構築が重要視されがちですが、むしろ文章化されにくいプレイにこそ、順位を分ける秘訣があるのだと思います。
次回は日本一決定戦だそうで、これも楽しみです。