【翻訳】納得の計算――最小で最大のメタ外、「アリスメティック」解説
2014年10月4日
今回もSixPrizesから。
面白そうな記事が未訳のままいくつか貯まっているのですが、そのなかのひとつをようやくご紹介します。
内容をおおざっぱに言えば、07-08シーズンのトップメタに対する、とあるアンチデッキの解説。なのですが、読んでみると、記事の主眼はそこではないことに気づきます。
どんなTCGにも存在する、トップメタへのアンチカード。ポケカでのそのようなアンチカードについて、どう考え、どう使っていくべきなのか。
記事中盤のデッキ解説も、記事後半の考え方も、ポケカに慣れた人にとってこそ、新鮮でとても面白い内容だと思います。
読むにあたって07-08シーズンのメタについて知っておくと便利なので、サーナイト/エルレイドに関してはこのあたり(http://ukinins.diarynote.jp/201402141235031960/)をご参照ください。また、DP時代のカードも検索すれば簡単にテキストがわかるので、ぜひ目を通してみてください。
いつもどおり、訳語の至らなさや誤訳の責任は、すべて僕うきにんに属します。
読みやすさを考慮して、改行を変更した部分があります。
(今回も例によって無許可翻訳なので、何かあればすぐに削除します)
◆ ◆ ◆ ◆ ◆
“It All Adds Up” -- Summarizing Arithmetic, The Little Rogue That Could
by Erik Nance
Friday, September 19, 2014
ttp://sixprizes.com/2014/09/19/it-all-adds-up-summarizing-arithmetic-the-little-rogue-that-could/
■イントロダクション
もしあなたがポケカを始めたのが比較的最近ならば、サーナイトやエルレイドについて他のプレイヤーと話をしているとき、そこにひとつの特徴があるのに気づいたことがあるかもしれない。ポケカを長くやっているプレイヤーにとって、サーナイトとエルレイドは、1シーズン全体を根本的に支配していたという点において、特別な重要性を持っている。「サーナイト/エルレイド」「サナレイド」「GG」「PLOX」……これらは、07-08シーズンのポケカの大半を支配したデッキに付けられた名前の数々だ。
あのシーズンにプレイしていた古参プレイヤーたちは、このデッキに関して真っ二つの立場を取った。前例のないフォーマットから生まれた激しいミラーマッチを楽しむプレイヤーがいる一方で、当時を露骨に嫌な顔をして振り返りながら、あれはポケカ史上で最もつまらない期間だったと言うプレイヤーもいる。しかし、それでもなお、この支配勢力を打ち倒すために努力を重ねたプレイヤーたちもいた。その中の一人が、Jimmy Ballardだ。
Jimmy Ballardのことをあまり知らない人のために言えば、彼はこれまでのポケカにおいて、最もクリエイティブなデッキビルダーのうちの一人だ。彼のデッキは大きな大会で優勝したことがそれほどあるわけではない。その一方でデッキはたいてい好成績を残すし、メタ外デッキと呼ばれることもほとんどない。付言すれば、彼は、ひたすら丸い穴に四角い杭を打ち込もうとするような大多数のメタ外デッキからは距離を置いていた。ある意味で彼は、「ガチ勢の中のメタ外デッキビルダー」だ。
彼が発案したデッキには、ピジョット/イーブイ進化系、「アンブッシュ」(エンペルト/ガラガラ)、「ソーセージ」(ジュペッタ/ハピナス)、そして「アリスメティック」などがある。このリストの最初のデッキで彼は、2006年世界大会で2位という成績を収めた。そして最後のデッキのおかげで僕は2007年のSoutheast Regionalsで優勝することができた。この記事でも、そのデッキを中心に扱う予定でいる。
〔※訳注:最初のイーブイデッキに関してはttp://bulbapedia.bulbagarden.net/wiki/Eeveelutions_%28TCG%29〕
横道に逸れたが、話を始めよう。今回の記事では、アリスメティックを直接に扱う。どのようなデッキなのか、どう動くのか、そして現代の我々はそのデッキから何を学べるのか。デッキの解説はカード1枚1枚行うつもりでいる。そしてまた、主流のデッキへの明確に効果的な対策カードを、なぜ多くのプレイヤーが見逃しがちなのか、その理由も説明したいと思う。
■では、アリスメティックとは?
正直に言って僕は、Jimmy Ballardが自分の編み出したデッキにつける名前をどうやって思いつくのかわからない。2007年のアメリカ選手権で、僕は「ソーセージ」という奇妙な名前をした彼の別のデッキを使ったが、その日は1日じゅう微妙に落ち着かなかった。とはいえ、勝てる可能性が高くなるのならば、僕はデッキの名前が「グルーピーグローワームマックスプロペラ」だったとしても喜んで使うだろう。ちなみに、今ちょうどデッドマウスの"Infra Turbo Pigcart Racer"がプレイリストに出てきたところだ。まあ要するに、何にだって相応の名前はある。
〔※訳注:デッドマウスのは実在の曲名〕
ことアリスメティックに関して言えば、以前に、このデッキ名はふさわしいものなんだと聞いたことがある。このデッキの基本戦術をこなす上で必要なのは――ご想像のとおり――算数だけだからだ、と。デッキ内のカードを見れば、確かにそのように思える。
〔※訳注:今回はデッキ名をカタカナで呼んでますが、アリスメティック("arithmetic")は「算術・計算」といった意味です〕
ジュペッタ(DP3)はサーナイト/エルレイドへの高速カウンターであり、序盤からゴーストヘッドでダメカンを乗せたり、うらみつらみでダメージを与えたりできる。うらみつらみは、トラッシュにジュペッタがあるかないかで、40か80のダメージを与えられるワザだ。ギャラドス(DP2)は当時、ブーバーン(DP4)にとって難攻不落の壁であり、ポケボディを利用すればコイキングのじたばたが30ダメージ追加で使うことができた。つまり足し算。
その一方で、クレセリアLV.Xは手軽にダメカンの置き換えができた。ポケパワーのまんげつのまいで、片方の場からダメージを引いて、もう片方の場にダメージを足す。これは相手の場のポケモンにダメージを追加で与えたり、ギャラドスの打点を強化することにも使えた。どちらにしても、足し算と引き算だ。
ネンドール(DP4)はこれらのカードの接着剤の役割を果たす。コスモパワーは多くのプレイヤーにとってお馴染みで、ポケカにおいて最良のポケパワーのうちのひとつだ。ネンドールに馴染みのない人のために言えば、このカードはサポートポケモンで、これのようなデッキの場の組み立てを可能にする。それゆえ、ネンドールが存在していた当時のデッキリストと現在のデッキリストは、非常に違って見える。
■デッキ詳細
端的に言えば、アリスメティックが成功した理由は、当時最も流行していた2つのデッキへのカウンターになっていたからだった。サーナイト/エルレイドと、ブーバーン派生(バシャーモ(DP4)入りもあった)だ。ギャラドスとジュペッタは単体ではそこまで強いカードではないが、それら2つのデッキと対戦した際には、この2枚ならダメージを多く与えることができた。
以下のリストは、僕が2007年のSoutheast Regionalsを優勝したときのものだ。
4 カゲボウズ
4 ジュペッタ(DP3)
2 コイキング
2 ギャラドス(DP2)
2 クレセリア
2 クレセリアLV.X
2 ヤジロン
2 ネンドール(DP4)
1 ミュウ(DP3)
4 TVレポーター
2 モノマネむすめ
3 ミズキの検索
2 ホロンの導師
4 ワープポイント
3 マスターボール
3 スーパーボール
1 夜のメンテナンス
3 湖の結界
8 超エネルギー
4 Wレインボーエネルギー
2 ホロンエネルギー水超
メモ:しばらくポケカをやってない人のために言えば、マスターボールとスーパーボールは当時と効果がまったく変わっていることに注意してほしい。当時のマスターボールは、現在のスーパーボールと同一のテキストだ。山札を上から7枚見てポケモンを1枚選び、それを相手に見せてから残った6枚を山札に戻してシャッフルする。一方でスーパーボールは、たねポケモン(exは除く)を1枚山札から探し、ベンチに出す。また、当時のワープポイントは、現在のあなぬけのヒモと同じ効果だった。
■カード解説
・カゲボウズ(PCG8)3、カゲボウズ(WCP)1、ジュペッタ4
上記のリストでは、PCG8のカゲボウズ3枚とWCPのカゲボウズ1枚を使っている。WCPのカゲボウズには強いワザがあるものの、全部PCG8のカゲボウズにするはずだった。そうしなかった理由? 僕が3枚しか持っていなかったからだ。なかまをよぶを除けば、かくせいはたねポケモンが持ちうる最良のワザのひとつだ(もちろん、進化すればの話だが)。2ターン目にジュペッタでアグレッシブに行く上では、パーフェクトなワザだろう。
ジュペッタが採用されている理由はたったひとつしかない。サーナイト/エルレイドを殺すためだ。Wレインボーエネルギーと湖の結界があり、かつトラッシュにジュペッタが落ちていれば、ジュペッタは140ダメージを出せて相手の場にサーナイトやエルレイドを倒せる。「GG」に対しては、1進化を立てるのは2進化よりも遥かに容易である以上、ほぼ毎回勝つことができる。加えて、ジュペッタがサーナイトやエルレイドを一撃で落とすための条件はかなり少ない――相手がサイコロックを撃ってこちらのポケパワーを止めてきたとしても、こちらとしては全然かまわない。
・コイキング2、ギャラドス2
この2枚が組み合わされば、エネ1枚でかなりのダメージを出せる。しかも、ブーバーンへの完璧な対抗策になっている。ギャラドスのポケボディー、ドラゴンDNAは、じたばたのダメージを30追加で撃てる。ささいなことに見えるかもしれないが、ブーバーンと対峙したときには、打点が急速に増えることになる。そして忘れないでいただきたいのが、ブーバーンへの対策という役割こそ、ギャラドスに要求されている全てだ、ということだ。W虹を貼ればあばれちらすも使えるが、ゲームを通じてじたばただけ撃っていればギャラドスはだいたいそれでいい(特に、クレセリアと組み合わせられれば)。
・クレセリア2、クレセリアLV.X2
どこかでクレセリアのワザを使ったことがあると言えたらいいのだが、一度もそんな機会はなかった。クレセリアLV.XはたねポケモンなのでW虹が貼れず、つまりワザを使うにはエネが3枚必要だ。ただクレセリアLV.Xが一番使われるのは、ポケパワーで場のダメージを操作するためだ。そうやってきぜつする射程に入れ、たいていの場合で対戦相手を困った状況にさせられる。
大事なことだが、クレセリアLV.Xが場に2体というのは、思っているよりもよく起こる。このデッキは予定どおりの動きをできるようにデザインされている(相手がGGならジュペッタを場に、相手がブーバーンならギャラドスを場に、等々)ため、クレセリアLV.Xを2体立てるタイミングも巡ってくるのだ。
・ヤジロン2、ネンドール2
これらのポケモンは、場の組み立てのためだけに存在している。上述したように、ネンドールは総じてポケカをより良い方向へと変えてくれた。そのおかげでプレイヤーは、デッキ内のポケモンを確実に場に出せるようになったのだから。ネンドールは毎ターンサポーターのように機能することから、たいていプレイヤーは、まず何よりもネンドールを場に出すことに注力する。また、不要なカードを山札の下に置くこともできる。もちろん、いつまでも不要なカードがデッキの底にあるというわけにはいかないが、マスターボールやTVレポーターとのシナジーを考えてみてほしい――山札の底にあるカードは、再び引き込むリスクがないのだ。
ここに書いておくべき大事なことはもうひとつある。だいたいにおいてネンドールは、サーナイトのサイコロックなどのワザのターゲットになるのだ。ネンドールの「活動歴」の後半では、よくレントラーLV.Xのポケパワー、かがやくまなざしを使ってベンチから引っ張り出して、きぜつさせるといったことが行われた。こういったことがないならば、理に適っていて有力なのは2-2ラインだ。そう、もしもコスモパワーを止めにくるのがサーナイトばかりならば、ジュペッタで容易に突破して、ゲーム中に安心してネンドールを使うことができる。
・ミュウ1
かつて使われたピィ(ネオ1)と似たようなものを探した結果、ミュウを使うことにした。手札をすべて使い切ったあと、ミュウをバトル場に送り出してサイコバランスを撃つ。すべての対戦で使うわけではないものの、初手がひどいときにも安心できる手段になってくれた。
・サポーターライン(TVレポーター4、モノマネむすめ2、ミズキの検索3、ホロンの導師2)
この記事のために自分のデッキリストを引っ張り出してみたら、サポーターラインには本当に衝撃を受けた。何よりも、たいていのプレイヤーが自動的に4投するはずのホロンの導師が2枚しか入っていなかったことに困惑した。自分のミスではないかと思う一方で、なぜデッキをこういう形にしたのか、その理由を何とか説明してみたいとも思う。
このデッキの主目的のひとつは、正しい1進化ポケモンを場に出して仕事をしてもらうことであって、すべてのポケモンを場に出す必要まではない。1ターン目のホロンの導師は確かに強いが、その一方で、スーパーボールなら代わりにたねポケモンを引きつつ、そのターンにサポーターも使うことができる。ホロンの導師とスーパーボールでたねポケモンを引くことができ、ミズキの検索ではどんなポケモンでも引くことができ、マスターボールでは何かをランダムに引ける。これこそ、一番必要な1進化をできるだけ早く引くための正しい組み合わせに感じられる。
考慮すべきことはもうひとつある。たね中心のデッキが存在しなかった当時は、ゲームスピードは今よりもずっと遅かった。ポケモンコレクターが使えた時代を経験したプレイヤーならばホロンの導師も真っ先に4枚にするかもしれないが、ポケモンコレクターが使えた頃には、ゲームスピードはずっと速くなっていたのだ。それだけでなく、ポケモンコレクターはユクシーも引くことができ、ゆえにそのままドロー能力にもなった。この要素がなく、またホロンエンジンも欠いていた以上は(そもそもこの大会はホロンの幻影以降レギュだったのだ)、ホロンの導師をフル投入する動機は大幅に減る。
〔※訳注:いわゆるホロンエンジン(ホロンのトランシーバーを中心にホロン系のカードで展開する構築のこと)は、ホロンの幻影の2つ前、ホロンの研究塔に収録されていたカード。ホロンの導師だけは後で再録されていたため、この時点ではこのカードだけ使えていた〕
それでも結局、ホロンの導師2枚は少なく感じる。どうにもしっくりこないのだ。もちろんこれは、ハマナのリサーチとポケモンコレクターが存在したフォーマットを経たあとでの感覚になるのだが。
そうだ、ところでハマナのリサーチは? 他のサポーターを押しのけてTVレポーターを使っているという点でも、同じことを感じるかもしれない。理由は、このデッキではカードを捨てたいからだ。TVレポーターやホロンの導師があれば、ジュペッタをトラッシュに送り込んでうらみつらみの打点を上げる手段になる。ハマナではこれができないために、デッキから弾き出されることになった。
・ワープポイント4
このカードはこのデッキではかなりの意味があるため、フル投入されている。クレセリアLV.Xを場に出す助けになるだけでなく、ときには簡単に倒せるポケモンを相手のベンチから引っ張り出すこともできる。またこのカードは、バトル場を縛ってくるデッキに対しても役に立つ(ネンドールとギャラドスはそれぞれ逃げるコストが2と3のため、バトル場で縛られることがよくある)
・マスターボール3、スーパーボール3
プレイヤーの多くは、スーパーボール(古いほうの効果だ)は堅実な選択だと思う一方で、マスターボールには疑問を感じるかもしれない。個人的には、ジュペッタを探してデッキを深く掘れるマスターボールは心強い。よくあるプレイは、ジュペッタを引くためにマスターボールを使い、それをTVレポーターかホロンの導師で捨てる、というものだ。マスターボールで引けないときは、だいたいTVレポーターで引ける。マスターボールは、ジュペッタを引く追加の手段なのだ。
もちろん、ジュペッタを引けないときは、他のポケモンを引けているのでそれで満足だ。デッキ内には20枚のポケモンが入っているため、マスターボールが空振りすることはめったにない。
・夜のメンテナンス1
たいていは、トラッシュからポケモンを戻すのに使われる。ジュペッタが良いのは、ワザでジュペッタをトラッシュから戻せる点だ。このおかげで、夜のメンテナンス1投がさらに効率よくなっている。
・湖の結界3
このデッキで一番重要なカードは、おそらく湖の結界だろう。サーナイトやエルレイド、そしてブーバーンに書いてある「+30」の弱点を2倍に書き換えるスタジアムだ。それらのカードの入ったデッキに対して確実に勝つ上で、このスタジアムは欠かせない。W虹やスクランブルエネを使ってくる相手への対策として、クリスタルビーチを使うこともかなり考えたが、あくまで当時に最も主流だったデッキの弱点色に的を絞ることにした。
後の時代ではジュペッタ/ハピナスのデッキがクリスタルビーチを活用することになるので、クリスタルビーチとて考慮に値しないカードではないのだ。ただ、大会を通じて湖の結界は相当に役に立ったので、これは正しい選択だったと思う。
・エネルギーライン(超エネ8、W虹4、ホロン水超2)
ホロンエネ水超を除けば、このエネルギーラインはかなり単純だ。超エネルギーがついていれば、ホロンエネ水超は、ワザの効果を防いでくれる(ダメージは除く)。この組み合わせはギャラドスと一緒に使うことで、対戦相手に、ギャラドスへダメージを与えざるを得なくさせた。そこまでゲームを決定付ける要素に見えないかもしれないが、これはエルレイドのソニックブレードに対して、もうひとつの対処法になっていたのだ。ソニックブレードはダメージでなく効果なので、ギャラドスを倒すには、相手は出力を最大化したサイコカッターを使わざるを得なかった。
それを除けば、エネルギーラインは非常に基本に忠実だ。W虹は、ジュペッタがエネ1枚でワザを使えるようになる。
■このデッキから学べること
ポケカでは、特定のデッキに対しての(あるいは、多くのデッキに対しての)一番わかりやすい対策カードが、そう、実際に一番分かりやすい対策カードになっているという事態が存在する。これが当たり前のように聞こえるのは承知だが、にもかかわらずプレイヤーたちは、いくつかの理由によって、問題に対する最も単純な解答を見落としがちだ。アリスメティックにおいては、ジュペッタとギャラドスがどちらも、流行のデッキに対する明確な対抗策になっていた。にもかかわらず、Jimmy Ballardがやったのと同じ地点にたどり着けた人はほとんどいなかったのだ。2010年の世界大会で使ったハガネールGRデッキに関して、僕は同じことを言ったことがある(ttp://www.examiner.com/article/pokemon-tcg-decks-steelix-tank)。
なぜそうなってしまうのだろうか。仮に、草ポケモンを倒すための解答が炎ポケモンを使うというあまりに単純なことだったとして――にもかかわらず誰も炎を使おうとしないのなら――そこには何か別の要素があるのだ。こういったことが起こる理由として僕が考えるものを、いくつかここに素描してみたい。
・個々人の先入観
対策カードというものに対して先入観を抱いているプレイヤーもいるかもしれない。とりわけ、他のプレイヤーたちがそのカードに否定的な意見を述べている場合には。プレイヤーの多くは「理論付け」をしたがる――つまり、実際のプレイテストよりも抽象的な語句でポケカについて考えたがる。誰かがガマゲロゲEXのようなカードの強さに気づいたとしても、他の誰かがすぐにこう言うだろう。「まあ、ビリゲノがいるから厳しいかな」
こういったことはあちこちで起こっている。特定のカードがポケカコミュニティから「使えない」という烙印を押されるのはよくあることだ。フレア団のしたっぱのことを考えてみてほしい。ガマゲロゲEXのデッキにはかなり効くサポーターだ。このカードについて、どんな考えが頭の中をよぎっただろうか? 僕に関して言えば、このカードはポケカコミュニティ全体からダメなカードだとひたすら言われていたことを思い出す。本当に効果的な対抗策を見つけたいなら、先入観は、多くのプレイヤーが乗り越えなければならないものだ。
・「ギミック的」
ときには、対策カードとしてはあまりに場面が限定的であったり、「ギミック的」すぎるように思えるカードもある。だが今年の世界大会では、Igor Costaがもう少しでシェイミEXで大会を制するところだった。誰もが(僕も含め)、たいていのマッチアップで、使える場面が限定的すぎると思っていたカードだ。また、かつてのレックウザ/シビビールに、コイン投げの方のビクティニを1枚入れるのは革命的なことだった。賭けてもいいが、プレイヤーの多くは、このコンボを「ギミック的」すぎるという理由で軽視していた。
・わかりきった弱さ
明らかな対策カードを軽視するのが正しい場合も多々ある。特定の流行デッキに対して良い相性を保ったとしても、他のデッキ全体に対しては壊滅的なことになる、という場合もあるだろう。こういった、効果の薄さがわかりきっているように思える場合、その評価が正しいこともある。だがときとして、それが原因で有効な対抗策をあまりに早く諦めてしまうことだってありうる。
この点に関しては、僕は確たる言葉を述べることができない。実際には、非常に有力な対策カードでも、メタ内の他の流行デッキには全く力を発揮できない、という場合もある。僕に言えるのは、他のマッチアップに対しても勝ち筋をできる限り探すべきだ、ということぐらいだ。ジュペッタとギャラドスの組み合わせに関して、僕も元々アイディアを持ってはいたが、途中で諦めた。だがクレセリアLV.Xとネンドールを入れることで、その2枚も機能するようになったのだ。
・ときには、解答が存在しないこともある
それが絶望とまでは言わないにせよ、ポケカでは、メタ内の動向に対するシンプルな解答が存在しないこともある。アリスメティックのおかげで僕は初めて地区別選手権で優勝することができたが、その一方で、残りのシーズンは、サーナイト/エルレイドがどんどん流行していった。結局はアリスメティックも解体された。さて、そのシーズンのアメリカ選手権と世界大会はどのデッキが優勝したのだろうか? その通り、サーナイト/エルレイドだ。
だが、結論に入ってしまう前に、読者の皆さんに勧めてみたい。自分の持っているアイディアを、他の人に渡してみよう。自分が見落としているものでも、他の人なら見つけられるかもしれない。あるいは、自分のプレイテストではデッキパワーがすべて出し切れていないかもしれない。状況がどうあれ、アイディアを諦める前に、新鮮な視点で他の人に見てもらうといい。
■結論
固定されたメタゲーム内での非常に限られたデッキの選択という、この記事の内容を楽しんでもらえたら幸いだ。今回のデッキを使ったときの元々の大会レポートに興味があれば、ここ(ttp://pokegym.net/forums/showthread.php?71385-Erik-Nance-s-1st-Place-SE-Regionals-Report-%28with-Arithmetic%29)で読むことができる。
これから新シーズンに移行するが、どこかの時点でプレイヤーたちが、現環境は行き詰っている感じたとしても、驚くにはあたらない。倒すのが困難な、意地の悪いコンボもちらほらある。だが、諦めるのはまだ早い。その時代の流行デッキへの、あなただけの対抗策を探してみよう。たとえそれが、相手のテンポを崩すためにフレア団のしたっぱを叩きつけるような、当たり前のものだったとしても(正直に言えば、僕はあまりこのカードが好きではないのだが)。周囲が失敗しても、あなたならうまくいくかもしれないのだから。
この記事から学べる最後の教訓は、おそらくコミュニティの持つ力だろう。Jimmy Ballardの手助けがなければ、僕はRegionalsで無残に負けていたはずだ。彼があれこれ親切にしてくれたおかげで、僕は優勝という大きな結果を残すことができた。もしあなたがどこのポケカコミュニティにも属していなくても、忘れないでほしいのだが、ポケカコミュニティは、興味を持っているプレイヤーなら誰でも親切に受け入れてくれる。情報とアイディアの共有は、ポケカコミュニティの持っている強力な要素だ。それを放っておく手はない。
もし記事に対して何か思うことがあれば、遠慮なくコメントしてほしい。そしていつものように、読んでくれてどうもありがとう。
◆ ◆ ◆ ◆ ◆
以上になります。お読みいただきありがとうございました。
過去環境についての記事を訳すのは今回で2度目になります。
前回も思ったのですが、「過去カードよく知らないしなー」とスルーされないかと若干心配しながら訳していましたw(カードテキストを全部載せたら分量が膨大になってしまいますし……)
このごろはSixPrizesを中心に、過去環境の振り返り記事が流行りらしく、僕も定期的に読んでいます。単に回顧が目的のものもあれば、今回の記事のようにかなり面白いものもあるので、定期的にピックアップしようかなとは思っています。
余談ですが、今回の記事は、リザードンメガバトルのときにカエンジシの強さを過小評価していた自分への戒めでもあります。
余談その2。最近はポケカDN勢を中心にMtG熱が増しているようにも見えます。僕は今でもMtGの記事をよく読みますが、これをきっかけにポケカDNでも記事やデッキ解説を書く人が増えてくれたら、と思います。
面白そうな記事が未訳のままいくつか貯まっているのですが、そのなかのひとつをようやくご紹介します。
内容をおおざっぱに言えば、07-08シーズンのトップメタに対する、とあるアンチデッキの解説。なのですが、読んでみると、記事の主眼はそこではないことに気づきます。
どんなTCGにも存在する、トップメタへのアンチカード。ポケカでのそのようなアンチカードについて、どう考え、どう使っていくべきなのか。
記事中盤のデッキ解説も、記事後半の考え方も、ポケカに慣れた人にとってこそ、新鮮でとても面白い内容だと思います。
読むにあたって07-08シーズンのメタについて知っておくと便利なので、サーナイト/エルレイドに関してはこのあたり(http://ukinins.diarynote.jp/201402141235031960/)をご参照ください。また、DP時代のカードも検索すれば簡単にテキストがわかるので、ぜひ目を通してみてください。
いつもどおり、訳語の至らなさや誤訳の責任は、すべて僕うきにんに属します。
読みやすさを考慮して、改行を変更した部分があります。
(今回も例によって無許可翻訳なので、何かあればすぐに削除します)
◆ ◆ ◆ ◆ ◆
“It All Adds Up” -- Summarizing Arithmetic, The Little Rogue That Could
by Erik Nance
Friday, September 19, 2014
ttp://sixprizes.com/2014/09/19/it-all-adds-up-summarizing-arithmetic-the-little-rogue-that-could/
■イントロダクション
もしあなたがポケカを始めたのが比較的最近ならば、サーナイトやエルレイドについて他のプレイヤーと話をしているとき、そこにひとつの特徴があるのに気づいたことがあるかもしれない。ポケカを長くやっているプレイヤーにとって、サーナイトとエルレイドは、1シーズン全体を根本的に支配していたという点において、特別な重要性を持っている。「サーナイト/エルレイド」「サナレイド」「GG」「PLOX」……これらは、07-08シーズンのポケカの大半を支配したデッキに付けられた名前の数々だ。
あのシーズンにプレイしていた古参プレイヤーたちは、このデッキに関して真っ二つの立場を取った。前例のないフォーマットから生まれた激しいミラーマッチを楽しむプレイヤーがいる一方で、当時を露骨に嫌な顔をして振り返りながら、あれはポケカ史上で最もつまらない期間だったと言うプレイヤーもいる。しかし、それでもなお、この支配勢力を打ち倒すために努力を重ねたプレイヤーたちもいた。その中の一人が、Jimmy Ballardだ。
Jimmy Ballardのことをあまり知らない人のために言えば、彼はこれまでのポケカにおいて、最もクリエイティブなデッキビルダーのうちの一人だ。彼のデッキは大きな大会で優勝したことがそれほどあるわけではない。その一方でデッキはたいてい好成績を残すし、メタ外デッキと呼ばれることもほとんどない。付言すれば、彼は、ひたすら丸い穴に四角い杭を打ち込もうとするような大多数のメタ外デッキからは距離を置いていた。ある意味で彼は、「ガチ勢の中のメタ外デッキビルダー」だ。
彼が発案したデッキには、ピジョット/イーブイ進化系、「アンブッシュ」(エンペルト/ガラガラ)、「ソーセージ」(ジュペッタ/ハピナス)、そして「アリスメティック」などがある。このリストの最初のデッキで彼は、2006年世界大会で2位という成績を収めた。そして最後のデッキのおかげで僕は2007年のSoutheast Regionalsで優勝することができた。この記事でも、そのデッキを中心に扱う予定でいる。
〔※訳注:最初のイーブイデッキに関してはttp://bulbapedia.bulbagarden.net/wiki/Eeveelutions_%28TCG%29〕
横道に逸れたが、話を始めよう。今回の記事では、アリスメティックを直接に扱う。どのようなデッキなのか、どう動くのか、そして現代の我々はそのデッキから何を学べるのか。デッキの解説はカード1枚1枚行うつもりでいる。そしてまた、主流のデッキへの明確に効果的な対策カードを、なぜ多くのプレイヤーが見逃しがちなのか、その理由も説明したいと思う。
■では、アリスメティックとは?
正直に言って僕は、Jimmy Ballardが自分の編み出したデッキにつける名前をどうやって思いつくのかわからない。2007年のアメリカ選手権で、僕は「ソーセージ」という奇妙な名前をした彼の別のデッキを使ったが、その日は1日じゅう微妙に落ち着かなかった。とはいえ、勝てる可能性が高くなるのならば、僕はデッキの名前が「グルーピーグローワームマックスプロペラ」だったとしても喜んで使うだろう。ちなみに、今ちょうどデッドマウスの"Infra Turbo Pigcart Racer"がプレイリストに出てきたところだ。まあ要するに、何にだって相応の名前はある。
〔※訳注:デッドマウスのは実在の曲名〕
ことアリスメティックに関して言えば、以前に、このデッキ名はふさわしいものなんだと聞いたことがある。このデッキの基本戦術をこなす上で必要なのは――ご想像のとおり――算数だけだからだ、と。デッキ内のカードを見れば、確かにそのように思える。
〔※訳注:今回はデッキ名をカタカナで呼んでますが、アリスメティック("arithmetic")は「算術・計算」といった意味です〕
ジュペッタ(DP3)はサーナイト/エルレイドへの高速カウンターであり、序盤からゴーストヘッドでダメカンを乗せたり、うらみつらみでダメージを与えたりできる。うらみつらみは、トラッシュにジュペッタがあるかないかで、40か80のダメージを与えられるワザだ。ギャラドス(DP2)は当時、ブーバーン(DP4)にとって難攻不落の壁であり、ポケボディを利用すればコイキングのじたばたが30ダメージ追加で使うことができた。つまり足し算。
その一方で、クレセリアLV.Xは手軽にダメカンの置き換えができた。ポケパワーのまんげつのまいで、片方の場からダメージを引いて、もう片方の場にダメージを足す。これは相手の場のポケモンにダメージを追加で与えたり、ギャラドスの打点を強化することにも使えた。どちらにしても、足し算と引き算だ。
ネンドール(DP4)はこれらのカードの接着剤の役割を果たす。コスモパワーは多くのプレイヤーにとってお馴染みで、ポケカにおいて最良のポケパワーのうちのひとつだ。ネンドールに馴染みのない人のために言えば、このカードはサポートポケモンで、これのようなデッキの場の組み立てを可能にする。それゆえ、ネンドールが存在していた当時のデッキリストと現在のデッキリストは、非常に違って見える。
■デッキ詳細
端的に言えば、アリスメティックが成功した理由は、当時最も流行していた2つのデッキへのカウンターになっていたからだった。サーナイト/エルレイドと、ブーバーン派生(バシャーモ(DP4)入りもあった)だ。ギャラドスとジュペッタは単体ではそこまで強いカードではないが、それら2つのデッキと対戦した際には、この2枚ならダメージを多く与えることができた。
以下のリストは、僕が2007年のSoutheast Regionalsを優勝したときのものだ。
4 カゲボウズ
4 ジュペッタ(DP3)
2 コイキング
2 ギャラドス(DP2)
2 クレセリア
2 クレセリアLV.X
2 ヤジロン
2 ネンドール(DP4)
1 ミュウ(DP3)
4 TVレポーター
2 モノマネむすめ
3 ミズキの検索
2 ホロンの導師
4 ワープポイント
3 マスターボール
3 スーパーボール
1 夜のメンテナンス
3 湖の結界
8 超エネルギー
4 Wレインボーエネルギー
2 ホロンエネルギー水超
メモ:しばらくポケカをやってない人のために言えば、マスターボールとスーパーボールは当時と効果がまったく変わっていることに注意してほしい。当時のマスターボールは、現在のスーパーボールと同一のテキストだ。山札を上から7枚見てポケモンを1枚選び、それを相手に見せてから残った6枚を山札に戻してシャッフルする。一方でスーパーボールは、たねポケモン(exは除く)を1枚山札から探し、ベンチに出す。また、当時のワープポイントは、現在のあなぬけのヒモと同じ効果だった。
■カード解説
・カゲボウズ(PCG8)3、カゲボウズ(WCP)1、ジュペッタ4
上記のリストでは、PCG8のカゲボウズ3枚とWCPのカゲボウズ1枚を使っている。WCPのカゲボウズには強いワザがあるものの、全部PCG8のカゲボウズにするはずだった。そうしなかった理由? 僕が3枚しか持っていなかったからだ。なかまをよぶを除けば、かくせいはたねポケモンが持ちうる最良のワザのひとつだ(もちろん、進化すればの話だが)。2ターン目にジュペッタでアグレッシブに行く上では、パーフェクトなワザだろう。
ジュペッタが採用されている理由はたったひとつしかない。サーナイト/エルレイドを殺すためだ。Wレインボーエネルギーと湖の結界があり、かつトラッシュにジュペッタが落ちていれば、ジュペッタは140ダメージを出せて相手の場にサーナイトやエルレイドを倒せる。「GG」に対しては、1進化を立てるのは2進化よりも遥かに容易である以上、ほぼ毎回勝つことができる。加えて、ジュペッタがサーナイトやエルレイドを一撃で落とすための条件はかなり少ない――相手がサイコロックを撃ってこちらのポケパワーを止めてきたとしても、こちらとしては全然かまわない。
・コイキング2、ギャラドス2
この2枚が組み合わされば、エネ1枚でかなりのダメージを出せる。しかも、ブーバーンへの完璧な対抗策になっている。ギャラドスのポケボディー、ドラゴンDNAは、じたばたのダメージを30追加で撃てる。ささいなことに見えるかもしれないが、ブーバーンと対峙したときには、打点が急速に増えることになる。そして忘れないでいただきたいのが、ブーバーンへの対策という役割こそ、ギャラドスに要求されている全てだ、ということだ。W虹を貼ればあばれちらすも使えるが、ゲームを通じてじたばただけ撃っていればギャラドスはだいたいそれでいい(特に、クレセリアと組み合わせられれば)。
・クレセリア2、クレセリアLV.X2
どこかでクレセリアのワザを使ったことがあると言えたらいいのだが、一度もそんな機会はなかった。クレセリアLV.XはたねポケモンなのでW虹が貼れず、つまりワザを使うにはエネが3枚必要だ。ただクレセリアLV.Xが一番使われるのは、ポケパワーで場のダメージを操作するためだ。そうやってきぜつする射程に入れ、たいていの場合で対戦相手を困った状況にさせられる。
大事なことだが、クレセリアLV.Xが場に2体というのは、思っているよりもよく起こる。このデッキは予定どおりの動きをできるようにデザインされている(相手がGGならジュペッタを場に、相手がブーバーンならギャラドスを場に、等々)ため、クレセリアLV.Xを2体立てるタイミングも巡ってくるのだ。
・ヤジロン2、ネンドール2
これらのポケモンは、場の組み立てのためだけに存在している。上述したように、ネンドールは総じてポケカをより良い方向へと変えてくれた。そのおかげでプレイヤーは、デッキ内のポケモンを確実に場に出せるようになったのだから。ネンドールは毎ターンサポーターのように機能することから、たいていプレイヤーは、まず何よりもネンドールを場に出すことに注力する。また、不要なカードを山札の下に置くこともできる。もちろん、いつまでも不要なカードがデッキの底にあるというわけにはいかないが、マスターボールやTVレポーターとのシナジーを考えてみてほしい――山札の底にあるカードは、再び引き込むリスクがないのだ。
ここに書いておくべき大事なことはもうひとつある。だいたいにおいてネンドールは、サーナイトのサイコロックなどのワザのターゲットになるのだ。ネンドールの「活動歴」の後半では、よくレントラーLV.Xのポケパワー、かがやくまなざしを使ってベンチから引っ張り出して、きぜつさせるといったことが行われた。こういったことがないならば、理に適っていて有力なのは2-2ラインだ。そう、もしもコスモパワーを止めにくるのがサーナイトばかりならば、ジュペッタで容易に突破して、ゲーム中に安心してネンドールを使うことができる。
・ミュウ1
かつて使われたピィ(ネオ1)と似たようなものを探した結果、ミュウを使うことにした。手札をすべて使い切ったあと、ミュウをバトル場に送り出してサイコバランスを撃つ。すべての対戦で使うわけではないものの、初手がひどいときにも安心できる手段になってくれた。
・サポーターライン(TVレポーター4、モノマネむすめ2、ミズキの検索3、ホロンの導師2)
この記事のために自分のデッキリストを引っ張り出してみたら、サポーターラインには本当に衝撃を受けた。何よりも、たいていのプレイヤーが自動的に4投するはずのホロンの導師が2枚しか入っていなかったことに困惑した。自分のミスではないかと思う一方で、なぜデッキをこういう形にしたのか、その理由を何とか説明してみたいとも思う。
このデッキの主目的のひとつは、正しい1進化ポケモンを場に出して仕事をしてもらうことであって、すべてのポケモンを場に出す必要まではない。1ターン目のホロンの導師は確かに強いが、その一方で、スーパーボールなら代わりにたねポケモンを引きつつ、そのターンにサポーターも使うことができる。ホロンの導師とスーパーボールでたねポケモンを引くことができ、ミズキの検索ではどんなポケモンでも引くことができ、マスターボールでは何かをランダムに引ける。これこそ、一番必要な1進化をできるだけ早く引くための正しい組み合わせに感じられる。
考慮すべきことはもうひとつある。たね中心のデッキが存在しなかった当時は、ゲームスピードは今よりもずっと遅かった。ポケモンコレクターが使えた時代を経験したプレイヤーならばホロンの導師も真っ先に4枚にするかもしれないが、ポケモンコレクターが使えた頃には、ゲームスピードはずっと速くなっていたのだ。それだけでなく、ポケモンコレクターはユクシーも引くことができ、ゆえにそのままドロー能力にもなった。この要素がなく、またホロンエンジンも欠いていた以上は(そもそもこの大会はホロンの幻影以降レギュだったのだ)、ホロンの導師をフル投入する動機は大幅に減る。
〔※訳注:いわゆるホロンエンジン(ホロンのトランシーバーを中心にホロン系のカードで展開する構築のこと)は、ホロンの幻影の2つ前、ホロンの研究塔に収録されていたカード。ホロンの導師だけは後で再録されていたため、この時点ではこのカードだけ使えていた〕
それでも結局、ホロンの導師2枚は少なく感じる。どうにもしっくりこないのだ。もちろんこれは、ハマナのリサーチとポケモンコレクターが存在したフォーマットを経たあとでの感覚になるのだが。
そうだ、ところでハマナのリサーチは? 他のサポーターを押しのけてTVレポーターを使っているという点でも、同じことを感じるかもしれない。理由は、このデッキではカードを捨てたいからだ。TVレポーターやホロンの導師があれば、ジュペッタをトラッシュに送り込んでうらみつらみの打点を上げる手段になる。ハマナではこれができないために、デッキから弾き出されることになった。
・ワープポイント4
このカードはこのデッキではかなりの意味があるため、フル投入されている。クレセリアLV.Xを場に出す助けになるだけでなく、ときには簡単に倒せるポケモンを相手のベンチから引っ張り出すこともできる。またこのカードは、バトル場を縛ってくるデッキに対しても役に立つ(ネンドールとギャラドスはそれぞれ逃げるコストが2と3のため、バトル場で縛られることがよくある)
・マスターボール3、スーパーボール3
プレイヤーの多くは、スーパーボール(古いほうの効果だ)は堅実な選択だと思う一方で、マスターボールには疑問を感じるかもしれない。個人的には、ジュペッタを探してデッキを深く掘れるマスターボールは心強い。よくあるプレイは、ジュペッタを引くためにマスターボールを使い、それをTVレポーターかホロンの導師で捨てる、というものだ。マスターボールで引けないときは、だいたいTVレポーターで引ける。マスターボールは、ジュペッタを引く追加の手段なのだ。
もちろん、ジュペッタを引けないときは、他のポケモンを引けているのでそれで満足だ。デッキ内には20枚のポケモンが入っているため、マスターボールが空振りすることはめったにない。
・夜のメンテナンス1
たいていは、トラッシュからポケモンを戻すのに使われる。ジュペッタが良いのは、ワザでジュペッタをトラッシュから戻せる点だ。このおかげで、夜のメンテナンス1投がさらに効率よくなっている。
・湖の結界3
このデッキで一番重要なカードは、おそらく湖の結界だろう。サーナイトやエルレイド、そしてブーバーンに書いてある「+30」の弱点を2倍に書き換えるスタジアムだ。それらのカードの入ったデッキに対して確実に勝つ上で、このスタジアムは欠かせない。W虹やスクランブルエネを使ってくる相手への対策として、クリスタルビーチを使うこともかなり考えたが、あくまで当時に最も主流だったデッキの弱点色に的を絞ることにした。
後の時代ではジュペッタ/ハピナスのデッキがクリスタルビーチを活用することになるので、クリスタルビーチとて考慮に値しないカードではないのだ。ただ、大会を通じて湖の結界は相当に役に立ったので、これは正しい選択だったと思う。
・エネルギーライン(超エネ8、W虹4、ホロン水超2)
ホロンエネ水超を除けば、このエネルギーラインはかなり単純だ。超エネルギーがついていれば、ホロンエネ水超は、ワザの効果を防いでくれる(ダメージは除く)。この組み合わせはギャラドスと一緒に使うことで、対戦相手に、ギャラドスへダメージを与えざるを得なくさせた。そこまでゲームを決定付ける要素に見えないかもしれないが、これはエルレイドのソニックブレードに対して、もうひとつの対処法になっていたのだ。ソニックブレードはダメージでなく効果なので、ギャラドスを倒すには、相手は出力を最大化したサイコカッターを使わざるを得なかった。
それを除けば、エネルギーラインは非常に基本に忠実だ。W虹は、ジュペッタがエネ1枚でワザを使えるようになる。
■このデッキから学べること
ポケカでは、特定のデッキに対しての(あるいは、多くのデッキに対しての)一番わかりやすい対策カードが、そう、実際に一番分かりやすい対策カードになっているという事態が存在する。これが当たり前のように聞こえるのは承知だが、にもかかわらずプレイヤーたちは、いくつかの理由によって、問題に対する最も単純な解答を見落としがちだ。アリスメティックにおいては、ジュペッタとギャラドスがどちらも、流行のデッキに対する明確な対抗策になっていた。にもかかわらず、Jimmy Ballardがやったのと同じ地点にたどり着けた人はほとんどいなかったのだ。2010年の世界大会で使ったハガネールGRデッキに関して、僕は同じことを言ったことがある(ttp://www.examiner.com/article/pokemon-tcg-decks-steelix-tank)。
なぜそうなってしまうのだろうか。仮に、草ポケモンを倒すための解答が炎ポケモンを使うというあまりに単純なことだったとして――にもかかわらず誰も炎を使おうとしないのなら――そこには何か別の要素があるのだ。こういったことが起こる理由として僕が考えるものを、いくつかここに素描してみたい。
・個々人の先入観
対策カードというものに対して先入観を抱いているプレイヤーもいるかもしれない。とりわけ、他のプレイヤーたちがそのカードに否定的な意見を述べている場合には。プレイヤーの多くは「理論付け」をしたがる――つまり、実際のプレイテストよりも抽象的な語句でポケカについて考えたがる。誰かがガマゲロゲEXのようなカードの強さに気づいたとしても、他の誰かがすぐにこう言うだろう。「まあ、ビリゲノがいるから厳しいかな」
こういったことはあちこちで起こっている。特定のカードがポケカコミュニティから「使えない」という烙印を押されるのはよくあることだ。フレア団のしたっぱのことを考えてみてほしい。ガマゲロゲEXのデッキにはかなり効くサポーターだ。このカードについて、どんな考えが頭の中をよぎっただろうか? 僕に関して言えば、このカードはポケカコミュニティ全体からダメなカードだとひたすら言われていたことを思い出す。本当に効果的な対抗策を見つけたいなら、先入観は、多くのプレイヤーが乗り越えなければならないものだ。
・「ギミック的」
ときには、対策カードとしてはあまりに場面が限定的であったり、「ギミック的」すぎるように思えるカードもある。だが今年の世界大会では、Igor Costaがもう少しでシェイミEXで大会を制するところだった。誰もが(僕も含め)、たいていのマッチアップで、使える場面が限定的すぎると思っていたカードだ。また、かつてのレックウザ/シビビールに、コイン投げの方のビクティニを1枚入れるのは革命的なことだった。賭けてもいいが、プレイヤーの多くは、このコンボを「ギミック的」すぎるという理由で軽視していた。
・わかりきった弱さ
明らかな対策カードを軽視するのが正しい場合も多々ある。特定の流行デッキに対して良い相性を保ったとしても、他のデッキ全体に対しては壊滅的なことになる、という場合もあるだろう。こういった、効果の薄さがわかりきっているように思える場合、その評価が正しいこともある。だがときとして、それが原因で有効な対抗策をあまりに早く諦めてしまうことだってありうる。
この点に関しては、僕は確たる言葉を述べることができない。実際には、非常に有力な対策カードでも、メタ内の他の流行デッキには全く力を発揮できない、という場合もある。僕に言えるのは、他のマッチアップに対しても勝ち筋をできる限り探すべきだ、ということぐらいだ。ジュペッタとギャラドスの組み合わせに関して、僕も元々アイディアを持ってはいたが、途中で諦めた。だがクレセリアLV.Xとネンドールを入れることで、その2枚も機能するようになったのだ。
・ときには、解答が存在しないこともある
それが絶望とまでは言わないにせよ、ポケカでは、メタ内の動向に対するシンプルな解答が存在しないこともある。アリスメティックのおかげで僕は初めて地区別選手権で優勝することができたが、その一方で、残りのシーズンは、サーナイト/エルレイドがどんどん流行していった。結局はアリスメティックも解体された。さて、そのシーズンのアメリカ選手権と世界大会はどのデッキが優勝したのだろうか? その通り、サーナイト/エルレイドだ。
だが、結論に入ってしまう前に、読者の皆さんに勧めてみたい。自分の持っているアイディアを、他の人に渡してみよう。自分が見落としているものでも、他の人なら見つけられるかもしれない。あるいは、自分のプレイテストではデッキパワーがすべて出し切れていないかもしれない。状況がどうあれ、アイディアを諦める前に、新鮮な視点で他の人に見てもらうといい。
■結論
固定されたメタゲーム内での非常に限られたデッキの選択という、この記事の内容を楽しんでもらえたら幸いだ。今回のデッキを使ったときの元々の大会レポートに興味があれば、ここ(ttp://pokegym.net/forums/showthread.php?71385-Erik-Nance-s-1st-Place-SE-Regionals-Report-%28with-Arithmetic%29)で読むことができる。
これから新シーズンに移行するが、どこかの時点でプレイヤーたちが、現環境は行き詰っている感じたとしても、驚くにはあたらない。倒すのが困難な、意地の悪いコンボもちらほらある。だが、諦めるのはまだ早い。その時代の流行デッキへの、あなただけの対抗策を探してみよう。たとえそれが、相手のテンポを崩すためにフレア団のしたっぱを叩きつけるような、当たり前のものだったとしても(正直に言えば、僕はあまりこのカードが好きではないのだが)。周囲が失敗しても、あなたならうまくいくかもしれないのだから。
この記事から学べる最後の教訓は、おそらくコミュニティの持つ力だろう。Jimmy Ballardの手助けがなければ、僕はRegionalsで無残に負けていたはずだ。彼があれこれ親切にしてくれたおかげで、僕は優勝という大きな結果を残すことができた。もしあなたがどこのポケカコミュニティにも属していなくても、忘れないでほしいのだが、ポケカコミュニティは、興味を持っているプレイヤーなら誰でも親切に受け入れてくれる。情報とアイディアの共有は、ポケカコミュニティの持っている強力な要素だ。それを放っておく手はない。
もし記事に対して何か思うことがあれば、遠慮なくコメントしてほしい。そしていつものように、読んでくれてどうもありがとう。
◆ ◆ ◆ ◆ ◆
以上になります。お読みいただきありがとうございました。
過去環境についての記事を訳すのは今回で2度目になります。
前回も思ったのですが、「過去カードよく知らないしなー」とスルーされないかと若干心配しながら訳していましたw(カードテキストを全部載せたら分量が膨大になってしまいますし……)
このごろはSixPrizesを中心に、過去環境の振り返り記事が流行りらしく、僕も定期的に読んでいます。単に回顧が目的のものもあれば、今回の記事のようにかなり面白いものもあるので、定期的にピックアップしようかなとは思っています。
余談ですが、今回の記事は、リザードンメガバトルのときにカエンジシの強さを過小評価していた自分への戒めでもあります。
余談その2。最近はポケカDN勢を中心にMtG熱が増しているようにも見えます。僕は今でもMtGの記事をよく読みますが、これをきっかけにポケカDNでも記事やデッキ解説を書く人が増えてくれたら、と思います。
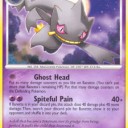

コメント